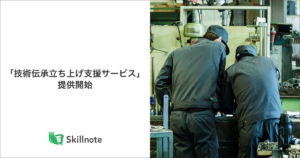お知らせ
-

Skillnote、ユーザー企業の戦略的技術伝承を支援する新たなサポートプログラム「技術伝承立ち上げ支援サービス」を提供開始
〜製造業における技術力の維持・強化を推進し、若手従業員の戦力化やキャリアアップにも貢献〜 製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnote(本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下Skillnote […… -

岡崎市民病院、医師や看護師などの資格管理に「Skillnote」を導入
製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnote(本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下Skillnote)は、岡崎市民病院(愛知県岡崎市、院長 小林靖、以下 岡崎市民病院)がクラウド型スキルマネジメントシステム「S… -

EYストラテジー・アンド・コンサルティング様、SAPジャパン様と「スキルベース組織」をテーマにイベントを開催しました
2024年4月26日にEYストラテジー・アンド・コンサルティング様、SAPジャパン様、Skillnoteの三社で『スキルベース組織の未来 ~日本企業におけるスキルを基軸にした人材マネジメントのあり方を考える~』と題したイ […… -

環境試験器で世界トップシェアのエスペック、アフターサービス本部に「Skillnote」を導入
製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnote(本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下Skillnote)は、エスペック株式会社(本社 大阪府大阪市、代表取締役 執行役員社長 荒田知、以下 エスペック)がクラウド型… -

生産スケジューラ「Asprova APS」、スキルマネジメントシステム「Skillnote」と連携開始
製造業の生産現場における最適な計画立案と戦略的な人材育成を実現 アスプローバ株式会社(本社:東京都品川区、取締役社長:田中 智宏、以下:アスプローバ)と株式会社Skillnote(本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆 […… -

Skillnote、「SAP AWARD OF EXCELLENCE 2024」にて「Partner Innovationアワード」を受賞
日本初の製造業向けIndustry Cloud認定、SAP社と共同提案による複数の案件獲得、各国におけるGo To Market協業の推進を評価 製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnote(本社 東京 […… -

日本初の製造業スキルマネジメントに関するカンファレンス「スキルマネジメントカンファレンス2024」、盛会のうちに終了
製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnote(本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下Skillnote)は、株式会社日本能率協会コンサルティング(本社 東京都港区、代表取締役社長 小澤勇夫、以 […… -

シチズン時計、機械式時計の開発部門に「Skillnote」を導入
製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnote(本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下Skillnote)は、シチズン時計株式会社(本社 東京都西東京市、代表取締役社長 佐藤敏彦、以下 シチズン時計)がクラウド型ス… -

日本初の製造業スキルマネジメントに関するカンファレンス「スキルマネジメントカンファレンス2024」を開催決定
製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnote(本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下Skillnote)は、株式会社日本能率協会コンサルティング(本社 東京都港区、代表取締役社長 小澤勇夫、以 […… -

総合機械メーカー大手の不二越、産業用ロボットの製造拠点に「Skillnote」を導入
製造業のスキルマネジメントを牽引する株式会社Skillnoteは、NACHIブランドで知られる総合機械メーカー大手の株式会社不二越が産業用ロボットの製造拠点にクラウド型スキルマネジメントシステム「Skillnote」を導入したことを発表しま…