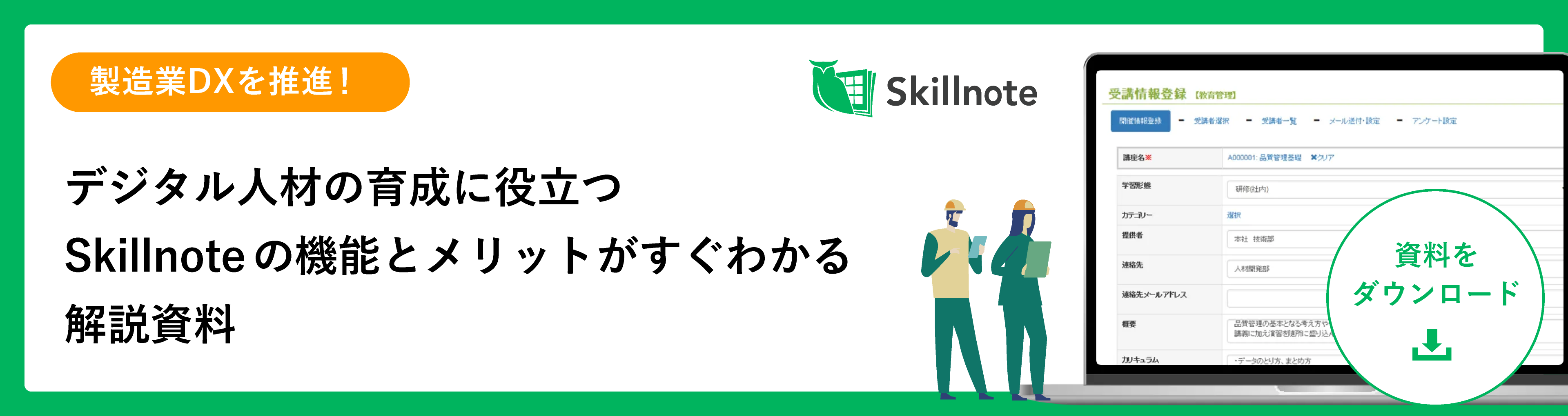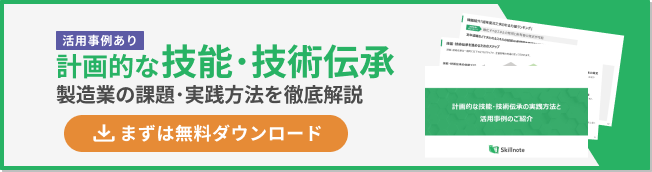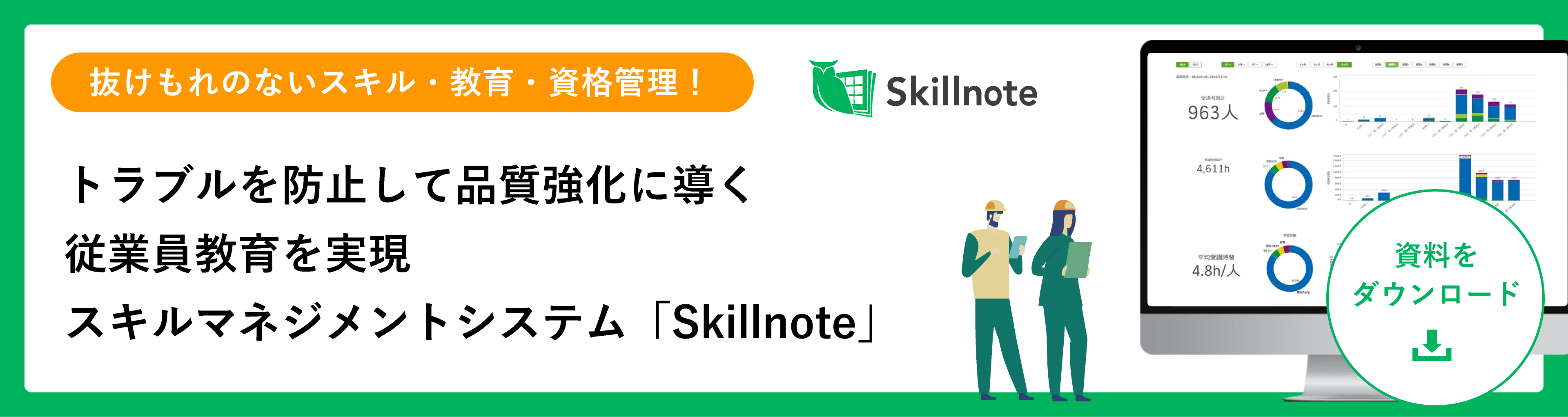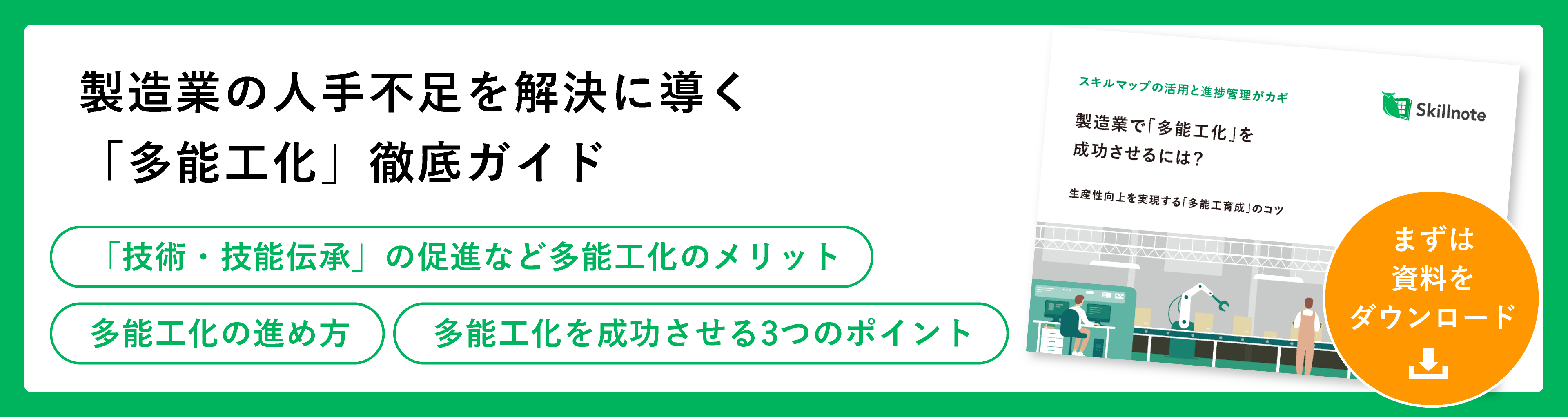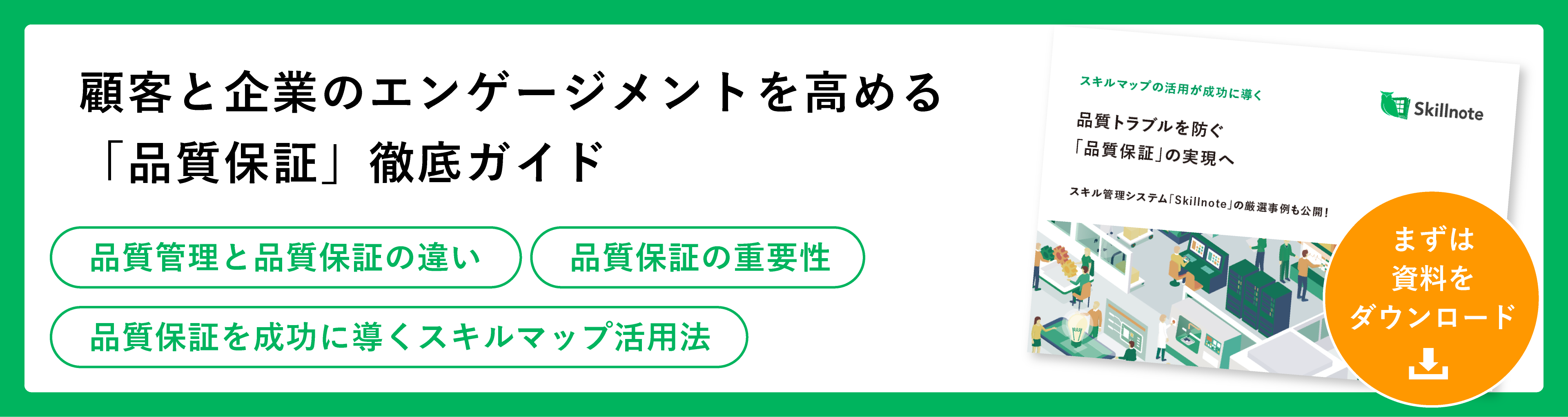ファクトリー・オートメーション(FA)とは? 注目される理由、市場規模、メリット・デメリット、代表されるシステムの紹介や企業の実例を解説

製造業のデジタル化が加速するなか、ファクトリー・オートメーション(FA)の重要性が増しています。とくに、人手不足や生産性向上の課題に直面する企業にとって、FAは必要不可欠なソリューションです。
本記事では、FAとスマートファクトリーやIndustry4.0との違い、注目される理由、市場規模、メリット・デメリット、代表されるシステムの紹介や企業の実例を解説します。
ファクトリー・オートメーション(FA)とは?
ファクトリー・オートメーション(FA)は、製造工場における生産工程の自動化を実現する技術やシステムの総称です。機械化による作業の効率化、品質の安定化、コストの削減を目的としています。具体的には、産業用ロボット、センサー、制御装置などのハードウェアと、それらを制御するソフトウェアを組み合わせて、製造プロセス全体の自動化を図ります。
FAシステムの特徴は、人間の作業を機械やコンピュータに置き換えることで、24時間365日の稼働を可能にし、人的ミスを最小限に抑えられる点にあります。また、データの収集・分析により、生産工程の最適化や予防保全も実現できます。

スマートファクトリーとの違い
FAとスマートファクトリーは、しばしば混同されますが、その特徴と目的は異なります。FAが個々の機械やプロセスの自動化に焦点を当てているのに対し、スマートファクトリーはIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)を活用し、工場全体をデジタル化・ネットワーク化することを目指しています。
スマートファクトリーでは、製造設備や製品からリアルタイムでデータを収集し、分析・活用することで、生産性の向上や品質管理の高度化を実現します。FAが「自動化」を主眼としているのに対し、スマートファクトリーは「知能化」「最適化」に重点を置いていると言えます。

Industry4.0との違い
Industry4.0は、FAやスマートファクトリーを包含する、より広範な産業革命の概念です。ドイツ政府が提唱したこの構想は、製造業のデジタル変革を推進する包括的なフレームワークとして位置づけられています。
Industry4.0では、サイバーフィジカルシステム(CPS)やIoT、AIなどの先端技術を活用し、製造業のみならず、サプライチェーン全体のデジタル化・スマート化を目指しています。FAはIndustry4.0を実現するための重要な要素技術の一つとして位置づけられています。
ファクトリー・オートメーション(FA)の市場規模
FAの世界市場は着実な成長を続けており、とりわけアジア太平洋地域での需要が顕著です。製造業のデジタル化ニーズの高まりを背景に、年平均成長率(CAGR)は約10%を維持しています。とくに、産業用ロボット、センサー、制御機器などのFA機器市場が急速に拡大しており、2025年までにグローバル市場規模は3,000億ドルを超えると予測されています。
ファクトリー・オートメーション(FA)が注目される2つの理由
グローバル競争の激化
製造業のグローバル化に伴い、企業間の競争は一層激しさを増しています。新興国の製造業の台頭により、品質と価格の両面で競争力が求められるなか、FAの導入は企業の生き残りのための重要な戦略です。生産コストの削減、生産性の向上、品質の安定化といったFAがもたらす効果は、グローバル市場での競争力維持に直結します。
また、カスタマイズ製品への需要増加や短納期化といった市場ニーズに対応するためにも、柔軟な生産体制の構築が不可欠となっています。
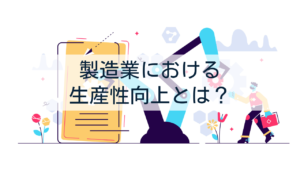
少子高齢化に伴う慢性的な人手不足
日本をはじめとする先進国では、少子高齢化による労働人口の減少が深刻な課題となっています。
製造現場における熟練工の高齢化や若手労働者の確保困難といった問題に直面するなか、FAによる自動化は有効な解決策として注目されています。単純作業や危険作業を機械に任せることで、限られた人材を より創造的な業務や管理業務に振り向けることが可能です。また、FAの導入により、技能伝承の課題も部分的に解決できます。

ファクトリー・オートメーション(FA)が活躍する4つの分野
加工
加工分野におけるFAは、金属やプラスチックなどの素材を目的の形状や性質に変換する工程を自動化します。CNCマシン、レーザー加工機、産業用ロボットなどを活用し、切削、研磨、溶接、熱処理などの作業を高精度に実行します。
これにより、人手では困難な微細加工や、危険を伴う高温・高圧での作業も安全に行うことが可能となります。また、プログラミングによる制御により、複雑な加工パターンも正確に再現できます。
組み立て
従来の人手による組み立てでは、作業者の技術レベルやコンディションにより品質にばらつきが生じることがありました。しかし、ロボットやオートメーションシステムを導入することで、24時間365日常に一定の品質を維持しながら生産を続けることが可能になります。
とくに、精密な電子機器や自動車部品などの組み立てでは、ミクロン単位の精度を要求されるケースも多く、人間の手作業では限界があります。FAによる組み立て工程の自動化は、このような高精度な作業を安定して行うことができ、不良品率の大幅な削減にも繋がっています。
マテハン
マテリアルハンドリング(マテハン)は、原材料や部品、完成品などの物質を効率的に移動・保管するシステムを指します。
FAにおけるマテハンの自動化とは、自動倉庫システムや無人搬送車(AGV)、コンベアシステムなどの技術のことで、人手を介さずに資材を必要な場所へ正確に届けることが可能になりました。人為的ミスによる誤配送や遅延の減少が期待できます。
また、ICタグやバーコードを活用した在庫管理システムと連携することで、リアルタイムの在庫状況把握が可能となり、過剰在庫や欠品リスクを最小化できます。さらに、作業員が重い荷物を運ぶ必要がなくなるので、労働環境の安全性向上や労働災害の防止にもつながっています。
管理
FAにおける管理の自動化は、製造業のデジタルトランスフォーメーションにつながります。生産ラインの各工程からリアルタイムのデータ収集・分析が可能になりました。
品質管理においても、自動検査システムやAI画像認識技術を活用することで、人間の目では見えない微細な欠陥も検出することができ、製品品質の大幅な向上に貢献しています。
また、品質管理で収集したデータを分析することで、生産プロセスの最適化や予知保全(設備の故障を予測し予防すること)も可能になり、ダウンタイムの削減と生産効率の向上が実現します。
ファクトリー・オートメーション(FA)の目的
FAの主要な目的は、生産性向上、コスト削減、品質改善、作業環境の安全性確保など多岐にわたります。
しかしながら、人手不足やコストの増加に悩まされる企業にとって、一番の目的は生産性を向上させ省人化を行うことにあるのではないでしょうか。
FAには多くのメリットがあるので、導入の際には何が一番の目的なのか見失わないよう留意しましょう。
ファクトリー・オートメーション(FA)のメリット
前述の通り、FAには多くのメリットが期待できます。
人件費の削減
FAの導入により、従来人手で行っていた作業を機械やロボットに置き換えることで、大幅な人件費削減が可能となります。特に、24時間稼働が必要な工程や、繰り返し作業が多い工程では、その効果が顕著です。
また、人員配置の最適化により、より付加価値の高い業務に人材を振り向けることができます。長期的には、採用・教育コストの削減にもつながり、企業の収益性向上に貢献します。
品質の維持・向上
自動化システムによる製造では、人的要因による品質のばらつきを排除できます。プログラムされた通りの精密な動作により、常に一定の品質水準の維持が可能です。また、センサーやカメラによる品質検査を組み込むことで、不良品の早期発見と対策が可能となります。これにより、顧客満足度の向上とクレーム対応コストの削減を実現できます。
作業員の安全性向上
危険を伴う作業や有害物質を扱う工程をFAで自動化することで、作業員の安全性が大幅に向上します。高温・高圧環境での作業や、重量物の搬送など、労働災害のリスクが高い作業を機械に任せることで、従業員の健康と安全を守ることが可能です。また、作業環境の改善により、従業員の満足度向上やモチベーション維持にもつながります。
生産効率の向上
24時間365日の連続稼働が可能なFAシステムにより、生産能力を最大限に引き出すことができます。人手による作業と比べて、作業スピードの向上と休憩時間の削減により、生産効率が飛躍的に向上します。また、段取り替え時間の短縮や、複数工程の同時進行により、リードタイムの短縮と生産量の拡大を実現できます。これにより、納期短縮や受注増加への対応が可能となります。
ファクトリー・オートメーション(FA)のデメリット
多くのメリットがあるFAですが、デメリットも把握しておきましょう。
多額の初期コストがかかる
FAシステムの導入には、設備投資やシステム構築に多額のコストが必要となります。産業用ロボット、制御装置、センサーなどのハードウェアに加え、システム設計や施工費用、そして運用のためのソフトウェア開発費用なども必要です。中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。
しかし、長期的な視点では、生産性向上やコスト削減により、投資以上の価値を生み出すことが可能です。政府の補助金制度なども活用することで、初期投資の負担を軽減できます。
仕事を奪われる不安感の蔓延
FAの導入により、従来人の担っていた作業が機械に置き換わることで、従業員の間に雇用不安が広がる可能性があります。
とくに、単純作業や定型作業に従事していた従業員にとって、この不安は切実な問題となります。しかし、これは同時に、デジタルスキルを習得し、より高度な業務にシフトするチャンスでもあります。従業員のスキルアップ支援や、新たな役割の創出により、この課題に対応することが重要です。

FA導入を担うデジタル人材が必要
FAシステムの導入・運用には、専門的な知識と技術を持つデジタル人材が不可欠です。システムの設計、プログラミング、保守管理など、高度な技術力が要求される業務が発生します。しかし、このようなスキルを持つ人材は現在不足しており、育成には時間とコストがかかります。この課題に対しては、スキル管理システムを活用した体系的な人材育成プログラムの導入が効果的です。

ファクトリー・オートメーション(FA)の代表的なITシステム
FAの代表的なシステムを紹介します。自社で課題となっている部分にアプローチできるシステムがないか検討してみてはいかがでしょうか。
設計や製造におけるFA
製造におけるITシステムとしては、製品の設計から実際の製造、検査までの一連の工程をサポートし、人的作業を自動化・効率化するシステムがあります。
APS
APS(Advanced Planning and Scheduling)は、生産計画システムのことです。複雑な製造環境下での効率的な生産スケジューリングを可能にし、受注から出荷までの全工程を一元管理します。生産リードタイムの短縮や在庫の最適化が実現できます。
AGV
AGV(Automated Guided Vehicle)は、工場内で定められた経路に沿って自律的に移動し、材料や製品を運搬する無人搬送車です。最近では人工知能を活用した経路認識技術などにより、設定された軌道を正確に走行します。人手による運搬作業を自動化することで、労働力の削減と運搬作業の効率化・安全性向上を実現します。
CAD
CAD(Computer-Aided Design)は、コンピュータ上で製品の設計図面を作成するシステムです。従来の手作業による製図と比較して、正確で複雑な設計が可能であり、修正や複製も容易に行えます。
CAM
CAM(Computer-Aided Manufacturing)は、CADで作成された設計データを基に、工作機械や産業用ロボットなどの製造装置を制御するシステムです。設計から製造への一貫したデータ流通を実現し、人手による入力ミスを防止するとともに、複雑な加工指示を正確に機械に伝達します。
CAE
CAE(Computer-Aided Engineering)は、コンピュータ上で製品の性能や機能をシミュレーションするシステムです。構造解析、流体解析、熱解析など様々な物理現象を仮想的に再現し、製品の挙動を予測することができます。
NC/CNC
NC/CNC(Numerical Control/Computer Numerical Control)は、工作機械の動作をプログラムにより数値制御するシステムです。工具の移動経路や速度、切削条件などをコンピュータで制御することで、複雑な加工を高精度に実現します。熟練工の技能に頼らず均一な品質の製品を生産できるため、技能伝承問題の解決や生産性向上に大きく貢献しています。
PDM
PDM(Product Data Management)は、製品に関する様々なデータを一元管理するシステムです。設計図面や部品表、技術文書など製品に関連する全ての情報を統合的に管理し、必要な時に必要な情報を迅速に取り出せる環境を提供します。複数部門間でのデータ共有や版管理を効率化し、設計変更の追跡や品質管理の強化に貢献します。
PLM
PLM(Product Lifecycle Management)は、製品の企画・設計から製造、販売、保守、廃棄に至るまでの全ライフサイクルを一元管理するシステムです。PDMの機能を包含しつつ、より広範な製品情報と業務プロセスを統合管理します。

基幹システムにおけるFA
基幹システムは、社内の情報流通や意思決定の効率化を図るITシステムです。企業内の様々なデータを一元管理し、可視化と共有を促進することで、業務効率の向上と迅速な経営判断を支援する重要な役割を担っています。
ERP
ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業の経営資源を統合的に管理し、経営の効率化を図るシステムです。会計、販売、生産、人事など企業活動の様々な領域のデータを一元管理し、部門間の情報共有を促進します。リアルタイムでの経営情報把握が可能となり、迅速な意思決定と経営戦略の実行を支援します。
MES
MES(Manufacturing Execution System)は、工場の生産現場と経営層を繋ぐ生産実行システムです。現場作業者への作業指示出しや設備稼働状況の把握も行い、生産性向上に貢献します。

MRP
MRP(Material Requirements Planning)は、生産計画の立案と資材調達計画を作成するシステムです。最終製品の生産計画から、必要な部品や原材料の必要量と調達タイミングを算出し、適切な発注計画を立案します。
社外関係者管理システムにおけるFA
社外関係者管理システムは、顧客やサプライヤーなど社外のステークホルダーとの関係を効率的に管理し、情報共有や連携を強化するITシステムです。
CRM
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客との関係を一元管理するシステムです。顧客情報、問い合わせ履歴、購買履歴などを統合的に管理し、営業活動や顧客サポートの質を向上させます。顧客ニーズの把握や満足度向上に役立ち、長期的な顧客関係の構築と売上向上に貢献します。
SCM
SCM(Supply Chain Management)は、原材料の調達から製造、流通、販売に至るまでのサプライチェーン全体を最適化するシステムです。取引先企業との情報共有を促進し、需要予測の精度向上や在庫の適正化、リードタイムの短縮などを実現します。
ファクトリー・オートメーション(FA)の事例
トヨタの生産方式
トヨタ自動車は、独自のトヨタ生産方式(TPS)とFAの技術を融合させ、世界最高水準の生産効率を実現しています。「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」を柱とするTPSに、最新のFA技術を組み合わせることで、徹底したムダの排除と品質向上の実現が可能です。とくに、自動車組立ラインでは、ロボットと人間が協働する「人間中心のオートメーション」を実践し、柔軟性と効率性を両立させています。
参考記事:トヨタ生産方式 | 経営理念 | 企業情報 | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト
三菱電機のFA-IT 統合ソリューション「e-F@ctory」における5G活用
三菱電機は、独自のFA-IT統合ソリューション「e-F@ctory」に5G通信技術を導入し、次世代のスマートファクトリーを実現しています。工場内の全ての機器がリアルタイムで接続され、膨大なデータを瞬時に収集・分析することが可能になりました。これにより、生産状況の可視化、予知保全、柔軟な生産体制の構築などが実現し、変種変量生産にも迅速に対応できる体制を整えています。
参考記事:e-F@ctory | ソリューション | 三菱電機FA

製造業人材DXの成功事例を公開!
スキル×人材マネジメントなら「Skillnote」が正解!
●製造業で人材DXを成功させるコツがわかる
●スキルマップの作成・運用・データ共有がぺーパーレス化
●スキル管理システムの活用で計画的な人材育成に成功
よくある質問
- FAとDXの違いは何ですか?
-
FA(ファクトリー・オートメーション)は、製造工場における生産工程の自動化を実現する技術やシステムの総称です。機械化による作業の効率化、品質の安定化、コストの削減を目的としています。具体的には、産業用ロボット、センサー、制御装置などのハードウェアと、それらを制御するソフトウェアを組み合わせて、製造プロセス全体の自動化を図ります。一方、DX(デジタルトランスフォーメーション)は企業がデジタル技術や膨大なデータを活用して業務プロセスや組織を改善して、競争優位性を高めていくことです。
- ファクトリーオートメーションのデメリットは?
-
FAシステムの導入には、設備投資やシステム構築に多額のコストが必要となります。産業用ロボット、制御装置、センサーなどのハードウェアに加え、システム設計や施工費用、そして運用のためのソフトウェア開発費用なども必要です。中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。
しかし、長期的な視点では、生産性向上やコスト削減により、投資以上の価値を生み出すことが可能です。政府の補助金制度なども活用することで、初期投資の負担を軽減できます。
- ファクトリーオートメーションの市場規模は?
-
FAの世界市場は着実な成長を続けており、とりわけアジア太平洋地域での需要が顕著です。製造業のデジタル化ニーズの高まりを背景に、年平均成長率(CAGR)は約10%を維持しています。とくに、産業用ロボット、センサー、制御機器などのFA機器市場が急速に拡大しており、2025年までにグローバル市場規模は3,000億ドルを超えると予測されています。