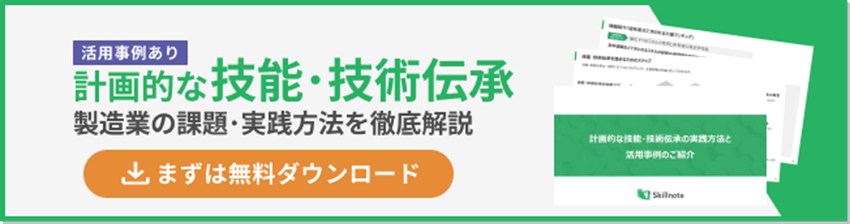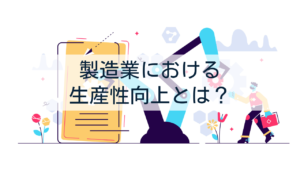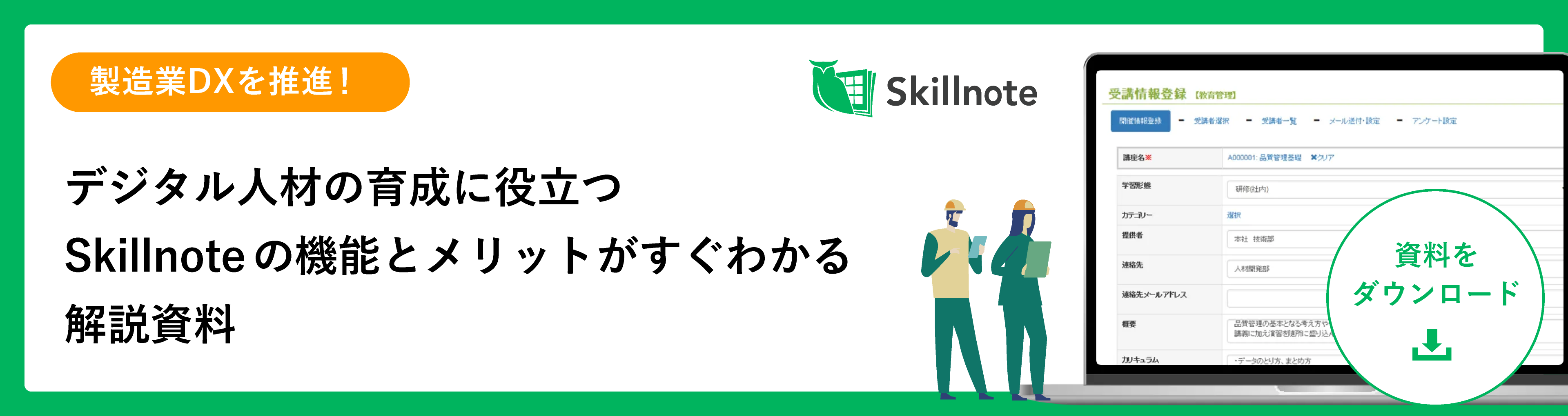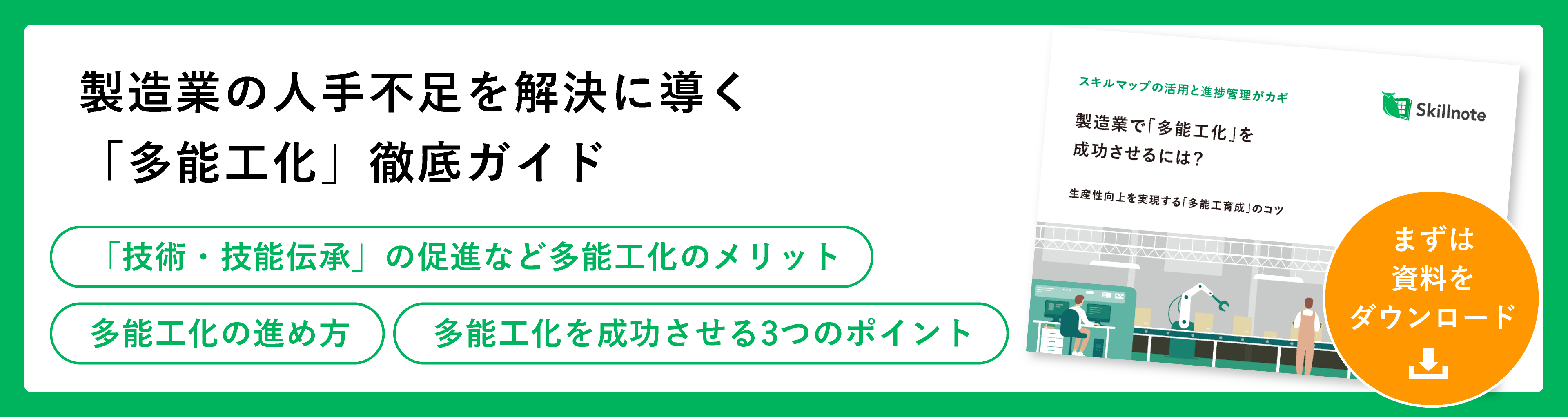昨今の製造業界は、光熱費・材料費の高騰、人材不足など、さまざまな課題を抱えています。とくに人材不足は深刻。20年間で高齢就業者数が32万人増加(厚生労働省「2023年版ものづくり白書」)し、高齢化のため技術継承が難しいケースもあります。そのような状況下で課題解決の糸口として知っておきたいのは、ドイツ政府が2011年に掲げた「インダストリー4.0」です。インダストリー4.0の概念や背景、日本版インダストリー4.0について解説します。
目次
インダストリー4.0とは
インダストリー4.0(第4次産業革命)とは、2011年にドイツ政府が「2020年に向けたハイテク戦略の実行計画」で示した10の施策の中の1つです。
インダストリー4.0のコンセプトを具現化したものが「スマートファクトリー」。生産プロセス全体をデジタル化し、さまざまなデータを管理して製造プレセスを効率化させることで、生産性の向上を実現した工場です。スマートファクトリー化することで、作業の効率性の向上だけではなくコスト削減、人材不足対策にもつながります。
あわせて読みたい
スマートファクトリーとは? 意味や目的、メリットを解説
急激な為替変動や資源価格の高騰、人材不足など外部環境の変化により、製造業にとって厳しい状況が続いています。この状況を打開する方法として注目を集めているのが、スマートファクトリーの実現です。
この記事では、スマートファクトリーの概要や目的、スマートファクトリーに取り組むメリットや実現に向けた流れを解説します。
ドイツでインダストリー4.0が推進される理由
ドイツはなぜ国を挙げてインダストリー4.0を推進するのでしょうか。その理由を探っていきましょう。
アジア・アメリカの製品への危機感
理由の1つに、他国の技術力が向上していることへの危機感があると言われています。アジア諸国ではボトムアップ型の生産方式、アメリカはトップダウン型の思想を取り入れたリーン生産方式といった、独自の施策を打ち出し成果を出しています。一方、ドイツは日本同様、高齢化に伴い人材不足が深刻化しています。産業全体に占める製造業の割合が高いにもかかわらず、製造業の不振が続いています。そのため業務の効率化は必須。デジタル技術を活用することで効率化へとつながる、インダストリー4.0が推進されているわけです。
あわせて読みたい
なぜ製造業で人手不足が深刻化しているのか?データから原因・影響・対策を徹底解説
終身雇用制の崩壊や少子高齢化の影響で、人手不足が深刻な問題となっています
この記事では経済産業省の「ものづくり白書」などで示されたデータを中心に製造業の人手不足の実態と理由、対策について解説します。
マイスター制度がスマートファクトリーを促進
ドイツでは、一定の技術や知識を持ち国家試験に合格した人物をマイスターとして認定し優遇措置をする「マイスター制度」を導入しており、技術を伝える道筋ができています。デジタル技術を活用したスマートファクトリーが推進されやすい素地があると言えます。
あわせて読みたい
【成功事例あり】技術伝承とは? 暗黙知と形式知・技能伝承との違い・成功させるコツ・デジタル技術活を…
製造業など、ものづくりに関わる企業を中心に「技術伝承」という用語が使われています。団塊の世代の定年退職が始まった2007年以降、頻繁に使用されるようになりました。
しかし、技術伝承の当事者となる方の中には、技術伝承という言葉の意味をしっかり把握できていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、技術伝承の概要に加えて、製造業で技術伝承が重要視される理由、実際に技術伝承を進めていく際の課題と対策を紹介します。

インダストリー4.0の中心となる6つのテクノロジー
デジタル技術を導入していくインダストリー4.0には、どのようなテクノロジーが活用されているのでしょうか。中心となる6つのテクノロジーを紹介します。
IoT(モノのインターネット)
工場の機器やセンサーをインターネットに接続して活用していきます。リアルタイムでデータを取得できるため、効率良く生産できるようになります。生産プロセスを自動管理していくことで、各種コストの削減に貢献します。
エッジコンピューティング
データが生成される場所でデータを処理するネットワーク技術です。この技術を活用することで、リアルタイムでのデータ分析が可能になります。
クラウドコンピューティング
違う場所にあるサーバーで、データやアプリケーションなどを実行管理する技術です。オペレーションの自動化の推進につなげやすくなります。大量のデータを扱え、保存もできるので分析などにも役立ちます。
AI(人工知能)
取得したデータを活用し、さまざまなタイプの「効率化」に貢献する技術です。自動化をはじめ、品質検査や製造ラインの保全、製品の不良などの判別にも役立ちます。
セキュリティ
データやシステムをサイバー攻撃から守るための技術です。情報の取り扱いに対する姿勢は、企業の信頼性にも関わるため非常に重要です。
デジタルツイン
実際の「モノ」から得たデータをサイバー空間に再現する技術です。サイバー空間上でさまざまなシミュレーションが可能となるため、新製品づくりに役立ちます。また、試作品などをつくる手間や費用が軽減でき、コスト削減につながります。
インダストリー4.0の4つの設計原則
インダストリー4.0には、4つの設計原則があります。それぞれ説明しましょう。
相互運用性(Interoperability)
人やモノにかかわらず、製造に関係する全てをつないでいくという原則です。工場内の機械の連携はもちろんですが、人のサポートをロボットが行うなど、さまざまなシーンで相互的な運用を目指します。
情報の透明性(Information Transparency)
収集したデータを活用して仮想モデルをつくり、可視化することです。情報を有効的に活用し、サイバー空間に作成されたモデルを見て解釈できるようにすることがポイントです。
技術的アシスト(Technical Assistance)
技術的アシストとは、人が行うと危険な作業や重労働は機械やロボットで代替するという意味です。技術的アシストにより、スタッフの安全が確保され生産性の向上に貢献します。
あわせて読みたい
産業用ロボットとは? 種類・メリット・導入時の注意点・代表的なメーカーについて解説
人手不足の深刻化を背景に、製造業では産業用ロボットが注目されています。
人間と同じように作業をしたり、人間に代わって危険な場所での作業をしたりする作業用ロボットは、人手不足を解消する手立てとして期待されています。
本記事では産業用ロボットを導入するメリットや注意点について解説しています。製造業の管理責任者、人事担当者の方はぜひ本記事を参考にしてください。
分散的意思決定(Decentralized Decision-making)
収集したデータをサイバー空間で分析しフィードバックする「CPS(サイバーフィジカルシステムの略)」を活用し、業務ごとの状況に応じた意思決定を可能な限り自律化することです。
インダストリー4.0の目的
そもそもインダストリー4.0は、人と機械、そして企業資源が相互的に通信することで情報を共有し製造プロセスを効率化します。これまでの事業活動の変革や新たなビジネスモデルの構築を目的につくられました。
実際にインダストリー4.0を推進することで、どのようなことが実現できると予測されるのか探っていきましょう。
生産性の向上
インダストリー4.0を導入することで、生産性の向上が見込めます。日本の製造業の就業者数は約20年間で157万人減少し、なかでも若者の就業者数は121万人減っています。今後の製造業を考えていく際には、人材不足を補いつつも生産性向上の実現が重要となります。インダストリー4.0は、どちらにも配慮された選択肢と言えます。
あわせて読みたい
製造業における生産性向上とは? そのポイントとメリット、低下する理由、手順を解説
生産性向上に向けた取り組みを行いたいと思っていても、そのための人材や時間が不足していてなかなか対策が取れていないと思っている担当者の方も多いと思います。
この記事では、製造業において生産性向上が重視される理由や、生産性向上によるメリット、生産性向上を実現するためのポイントを解説します。
カスタマイゼーションの実現
スマートファクトリー化により工場は、完全自動化に近づく上、取得したデータを分析することで顧客ニーズを知ることができます。また、サイバー空間で試作品の確認できるなど柔軟な対応も可能なため、顧客の要望に合った商品を特注でつくりなります。きめ細やかなサービスを提供できるでしょう。
イノベーションの促進と新しいビジネスの創出
インダストリー4.0は、既存ビジネスの変革と新たなビジネスモデル創出も目的の1つとしています。たとえば、既存商品の製造販売だけではなく、「サービスとしての機械」として捉えた新プランを考えていくなど、新しいビジネスにつながるヒントに満ちた選択肢と言えます。
透明性のあるリアルタイムな意思決定の実現
在庫のリアルタイム確認や、サイバー空間で高度なシミュレーションをつくって共有することにより、双方が口頭やイメージだけではなく視覚的な確認をした上で意思決定できるようになります。
日本版インダストリー4.0「Connected Industries」
2011年にドイツ発の「インダストリー4.0」以来、2015年4月にはフランスが「未来の産業」、同年5月には中国が「中国製造2025」など、さまざまな国が目指すべき産業の姿を明確に示してきました。
一方、日本は「目指す社会の姿」としてSociety 5.0を示してきたことに加えて、産業に関して「Connected Industries(コネクテッド・インダストリーズ)」として2017年3月に世界に向けて発信しました。
基本的な考え方は、「さまざまなつながりにより新たな付加価値が創造される産業社会」であり、インダストリー4.0と基本の考え方は同じです。以下の3つが柱となっています。
1 人と機械・システムが対立するのではなく、協調する新しいデジタル社会の実現
2 協力と協働を通じた課題解決
3 人間中心の考えを貫き、デジタル技術の進展に即した人材育成の積極推進としています。
日本におけるインダストリー4.0の現状と課題
日本におけるインダストリー4.0およびコネクテッド・インダストリーズ(以下、インダストリー4.0に統一)は、あまり進んでいないのが現状です。スマートファクトリー化には、AIやIoT、データサイエンスに精通した人材が必要です。しかし、IT人材不足は顕著です。事実、総務省「令和3年情報通信白書」によると、IT人材は「大幅に不足している」「やや不足している」と回答した企業は89%に達しました。
あわせて読みたい
製造業におけるデジタル人材とは? 定義、必要とされる理由、求められる資質、育成方法・ポイントを解説
少子高齢化やベテラン技術者の定年退職により、製造現場では人手不足やノウハウの継承などの課題を抱えている企業が多くなっています。 これらの課題を解決するための方…
また、セキュリティ面において課題があります。インダストリー4.0を実現するためには、デジタル環境の整備が必要です。製造工場には、セキュリティ対策に配慮されたインターネット環境が整備されていないケースも見られます。効率化のためには、取引先との連携も必要になってくるでしょう。業務の流れの共有だけではなく、セキュリティ対策に関するマニュアルも作成し、サプライチェーンにも徹底する必要があります。
2025年の崖
インダストリー4.0の実現は、とくに中小企業にとって解決すべきポイントが多くあります。しかし、経済産業省は、2018年の「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート」で「2025年の崖」と表現を使い、システムの見直しをしていかなければ2025年から年間で現在の約3倍、約12兆円もの経済損失が発生すると予測しています。国内企業のシステム全体の6割が、2025年には20年以上稼働しているシステムになると言われており、改善が急がれています。
経済産業省では、社内のDX推進状況や計画について自己診断ができる「DX評価指標」を提供しています。自己診断をしてみることで、現状が把握でき課題が見えてくるかもしれません。古いシステムを見直す際、スマートファクトリー化を検討すると、さらなる効率化が期待できます。
あわせて読みたい
製造業DXとは?期待される効果や進まない理由、導入のためのステップや取り組み事例を紹介
近年ますます注目されている製造業DX。DXによって、日本国内の製造業が直面している課題の解決が期待されています。さまざまな業種でDXは進んでいますが、IPA(独立行政…
インダストリー4.0を実現させるポイント
インダストリー4.0のコンセプトであるスマートファクトリーは、どのように実現できるのでしょうか。以下で流れを紹介します。
開始前に、しっかりとプランニング・現状分析を行う
プロジェクトを動かす前に、まずは現状把握や分析を実施しましょう。上層部だけで話をするのではなく、現場や関係各所と話をして足並みを揃えておくことが大切です。
スモールスタートを心がける
スマートファクトリーの実現のためには、コストがかかります。最初はスモールスタートから始めるとよいでしょう。
スマートファクトリーの導入事例
スマートファクトリー化を生産性向上につなげるためにも、企業は自社にとって何が課題かを把握する必要があります。ここでは企業のスマートファクトリー化事例を紹介します。
受配電機器の生産を行っている富士電機の大田原工場では、スマートファクトリー化に向けて、さまざまな取り組みをしてきました。これまでもIoT技術の活用はしていましたが「生産性向上にどう結びつけるか」が課題だったそうです。そこで、エネルギー使用状況、生産状況、品質情報など、さまざまな情報をリアルタイムで確認できるダッシュボードを導入。映像・データなどを画面上に表示することで、現場で発生した問題にも迅速に対応できるようになりました。
日立製作所の事例
日立製作所では、工場の製造ラインの稼働状況、作業者の動き、在庫、物流まで、リアルタイムで把握できるスマートファクトリー化を実施。取得したデータを活用し、さまざまな問題点を可視化。サプライチェーンの最適化につながりました。
進化版インダストリー5.0の存在も
各国ではインダストリー4.0に続く「インダストリー5.0」についての議論が出ています。これまでのインダストリー4.0では、デジタル活用が要となっていました。インダストリー5.0では、4.0ではコアな扱いではなかった地球環境の保全を目指す「持続可能性(サステナビリティまたはサステナブル)」、人を尊重し人と機械が協業する産業を目指す「人間中心(ヒューマンセントリック)」、予測不可能な事態に陥っても迅速に回復する「回復力(レジリエンスまたはレリジエント)」の要素が追加されました。
このような傾向を踏まえ、今後の製造業は、今まで以上に人と技術(機械)、そして地球環境をより大切にしていくことが求められていきそうです。
製造業人材DXの成功事例を公開!
スキル×人材マネジメントなら「Skillnote」が正解!
●製造業で人材DXを成功させるコツがわかる
●スキルマップの作成・運用・データ共有がぺーパーレス化
●スキル管理システムの活用で計画的な人材育成に成功
→詳しくはこちらから