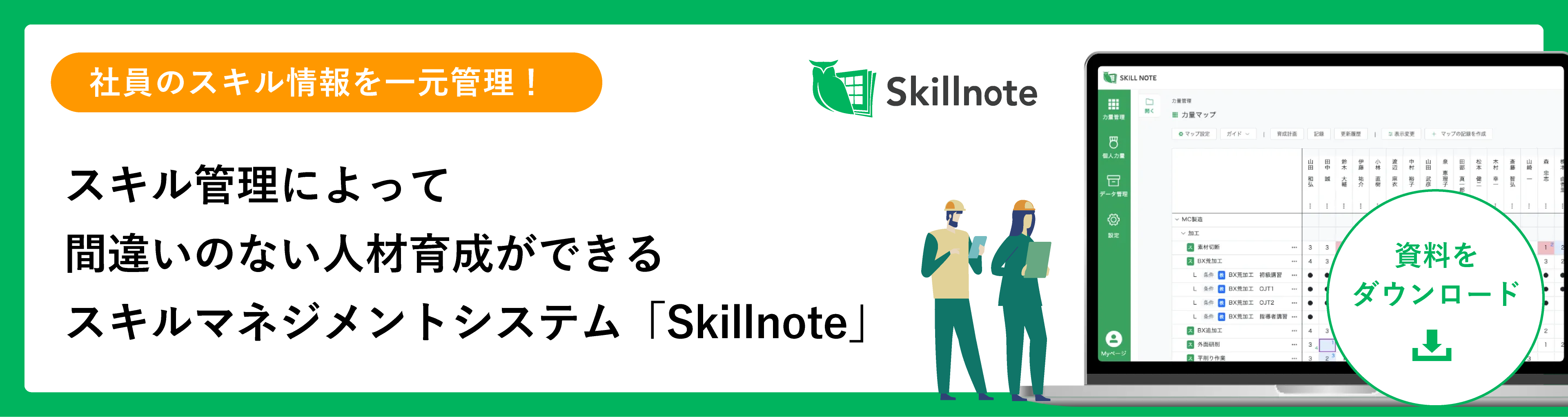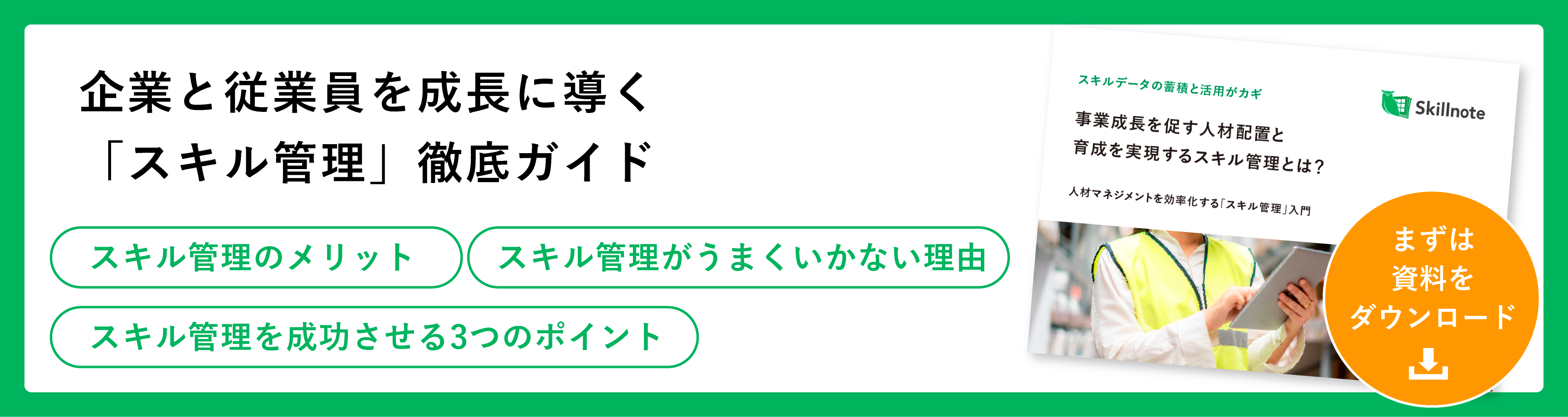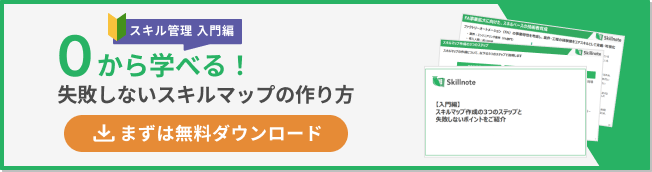テクニカルスキル(業務遂行能力)とは? 3つの種類のスキル、習得メリット、注目される理由、向上させる方法

少子高齢化によって生産年齢人口が減少しており、どの業界においても人材の技術・スキルの属人化の解消や、従業員の多能工化を取り組んでいく必要があります。
この取り組みに対し、「スキル」や「知識」を中心としたマネジメント手法が効果的です。具体的には、ロバート・カッツ氏が提唱した「テクニカルスキル(業務遂行能力)」が挙げられ、従業員個別の問題だけでなく、チームや組織全体の課題を解決してくれます。
本記事では、テクニカルスキル(業務遂行能力)について、3つの種類のスキルや習得のメリット、注目される理由などを交えて解説します。
「テクニカルスキル(業務遂行能力)」とは?
「テクニカルスキル(業務遂行能力)」とは、従業員が業務を遂行するうえで、必要になる専門的な知識・技術のことを指します。
この理論は、ハーバード大学の教授であるロバート・カッツ氏が「Skills of an Effective Administrator」(1955年)によって提唱されたものです。この説によれば、テクニカルスキルは「管理者に必要な仕事力、ビジネススキルの1つ」とされています(※)。
(※)参考:Harvard Business Publishing「Skills of an Effective Administrator」
テクニカルスキルが注目される理由
ロバート・カッツ氏が提唱した「テクニカルスキル」は1955年に提唱された理論であるものの、今日においてスキルや知識を中心としたマネジメント手法とともに注目されつつあります。このテクニカルスキルが注目される理由を紐解くことによって、自社にとっての必要性や課題、また具体的な施策を検討しやすくなるでしょう。
ここでは、テクニカルスキルが注目される理由について、解説します。
- ビジネス環境の変化で高度な知識・スキルが必要になった
- 企業の教育投資が注目されてきた
①ビジネス環境の変化で高度な知識・スキルが必要になった
1990年代終盤以降、金融危機やリーマンショック、コロナ禍などのさまざまな経済的危機がありました。また、インターネットやソーシャルメディアの成長により、人々の価値観も多様化しています。
このような背景にともなって、サービスや商品が溢れている現在では、より高品質な体験価値が重視されるようになりました。これはビジネス環境の変化とも関連しています。商品の開発や質の高いサービスの提供のために、高度な知識・スキルが求められるようになり、「テクニカルスキル」の考え方が重要視されているのです。
②企業の教育投資が注目されてきた
時代の変化や日本が抱える課題から、とくに人材教育の必要性が高まっています。これは日本政府も同じ認識を持っています。
具体的に、内閣府が2018年に公表した「年次経済財政報告」では、「企業が教育投資を増加させると、労働生産性も高まる」と示されました(※1)。また、政府による検証も行われ、「平均的には1人当たり人的資本投資額の1%の増加は、0.6%程度労働生産性を増加させる可能性が示唆される(※2)」という結果を出しています。
テクニカルスキルに対して直接的に言及していないものの、政府として企業の人材教育の必要性を訴えている根拠となるでしょう。
(※1)参考:内閣府「令和4年度 年次経済財政報告」
(※2)引用:内閣府「第2章 人生100年時代の人材と働き方」176ページ
カッツ理論の「ヒューマンスキル」と「コンセプチュアルスキル」との違い
ロバート・カッツ氏が提唱する「Skills of an Effective Administrator(以下「カッツ理論」)」のなかには、テクニカルスキルだけでなく、「ヒューマンスキル」や「コンセプチュアルスキル」があります。これらのスキルは、どれも管理者に必要なビジネススキルとして挙げられており、それぞれの業界・職種・業種に応じて、スキルのバランスが必要と提唱されました。
テクニカルスキルの考え方を取り入れる前に、根底となるロバート・カッツ氏の理論を理解し、実際にどのようなスキルが自社に求められるのかをイメージすることが大切です。
ここでは、カッツ理論の「ヒューマンスキル」と「コンセプチュアルスキル」との違いについて、前提となる知識やマネジメントの3段階を解説します。
【前提】カッツ理論とは?
ロバート・カッツ氏が提唱した「カッツ理論」では、優秀な管理者の選抜と育成に効果的なアプローチを示すことを目的としています。このアプローチに必要な管理者のスキルとして、以下の3つが必要としました。
- テクニカルスキル
- ヒューマンスキル
- コンセプチュアルスキル
ただ、管理者の立場や職務、業務内容によって、それぞれのスキルレベルが異なるとしています。詳細は「カッツ理論におけるマネジメントの3段階」で紹介するため、ここでは、ヒューマンスキルとコンセプチュアルスキルについて、紹介します。
参考:Harvard Business Publishing「Skills of an Effective Administrator」
「ヒューマンスキル」とは、良好な人間関係を構築するスキル
「ヒューマンスキル」とは、管理者がチームを率いて協働する際に求められるスキルのことを指します。コミュニケーション力や交渉力、マネジメント能力などの「人」を主体としたスキルです。
「コンセプチュアルスキル」とは、個人やチームを客観視するスキル
「コンセプチュアルスキル」とは、物事の本質を正確に捉える能力のことを指します。個人やチームが持っている可能性を見抜き、効果的に運用できる能力です。
ッツ理論におけるマネジメントの3段階
カッツ理論において、管理者の立場や職務、業務内容によって、求められる3つのスキルの割合が異なります。たとえば、現場での監督責任者では高度かつ専門性が高いテクニカルスキルが必要であり、またトップの経営層であればチームや組織全体を俯瞰できるコンセプチュアルスキルが必要です。
このように、テクニカルスキルの必要性が理解できていても、「実際に求められる割合」も把握してから、施策を講じる必要があります。ここでは、カッツ理論におけるマネジメントの段階について、紹介します。
参考:Harvard Business Publishing「Skills of an Effective Administrator」
ロワーマネジメント:テクニカルスキル
「ロワーマネジメント(lower management)」とは、現場に近い立場で業務をおこなう管理者を指します。企業のなかでも、商品の製造やサービスの提供に直接的に携わる段階です。
ここでは、商品やサービスに関する高度かつ専門的な「テクニカルスキル」が求められ、他の二つの段階と比べてもその比重は最も大きいものとなります。
ミドルマネジメント:ヒューマンマネジメント
「ミドルマネジメント(middle management)」は中間管理職のことを指します。経営層と現場監督者との中間に当るポジションであり、経営層から企業のビジョンや方針を示され、また部下への教育・育成に携わります。
ミドルマネジメントは社内でさまざまな人と関わることから、コミュニケーション力や交渉力などが問われる「ヒューマンスキル」が求められます。
トップマネジメント:コンセプチュアルスキル
「トップマネジメント(top management)」は経営者やその周辺にいる経営層の立場を指します。チームや組織を俯瞰し、それぞれの可能性を最大限に引き出すためのビジョンや方針を示すことが求められる段階です。
スキルとしては、物事の本質を見抜く「コンセプチュアルスキル」がもっとも求められ、一方でテクニカルスキルの割合は低くなっています。
テクニカルスキルの3つの種類
ロバート・カッツ氏が提唱する「テクニカルスキル」はさらに細分化することが可能です。具体的には、「汎用スキル」「専門スキル」「特化スキル」にわけられ、それぞれで取得すべきスキル内容が異なります。
具体的な施策検討のためにも、テクニカルスキルの種類を理解し、自社・自チームに必要なポイントを見つけましょう。
ここでは、テクニカルスキルの3つの種類について、解説します。
①汎用スキル
「汎用スキル」はテクニカルスキルの基礎となるものであり、日常の業務をおこなううえでも必要です。具体的には、商品やサービスの知識、また業務を遂行するにあたっての知識が挙げられます。また、ビジネスマナーやツールの操作方法なども、汎用スキルに含まれます。
②専門スキル
「専門スキル」は、高度でかつ専門的な業務を遂行するために必要なスキルです。汎用スキルよりも求められる知識や技量が高く、スキルを有する人材も少なくなってしまいます。たとえば、資格が求められる作業や、法律・会計に関する業務などが挙げられます。
③特化スキル
「特化スキル」は専門スキルをより高めたもので、唯一無二の存在になる市場においても価値の高いスキルです。ノウハウや経験などが積み重なって、「プロフェッショナル」とも呼ばれるものとなります。
テクニカルスキルの4つのメリット
従業員がテクニカルスキルを身につけることは、企業にとって業務効率化以外のさまざまなメリットがあります。これからテクニカルスキルにまつわる施策の導入を検討していれば、自社の課題感や描いているビジョンなどを踏まえて、それぞれのメリットを理解しておきましょう。
ここでは、テクニカルスキルのメリットについて、以下の4つを解説します。
- 業務効率化
- 業績向上
- 従業員のモチベーション向上
- 顧客満足度上昇
①業務効率化
テクニカルスキルを身につければ、業務を遂行するために必要なツールの使い方や、サービスのオペレーションなどの業務を短時間で実行できるようになります。また、従業員がそれぞれの業務を理解することで、エラーが起こりづらくなり、業務ミスの対応も少なくできます。
②業績向上
テクニカルスキルが従業員に浸透していれば、一つひとつの業務が丁寧かつスムーズに進められるため、提供される商品やサービスの質が高まりやすくなります。良質なものを数多く提供できれば、顧客からの購買も促進でき、組織全体の業績も向上しやすくなるでしょう。
③従業員のモチベーション向上
テクニカルスキルではスキルの汎用化が可能となるため、身に付けていなかったスキルを従業員が得られやすくなるでしょう。スキルを得た従業員は、これまでにできなかったことができるようになり、成功体験や組織・チームの活躍によって業績を体感でき、モチベーションの維持・向上につながります。
④顧客満足度上昇
テクニカルスキルによって業務の質が高まれば、製造している商品や提供されるサービスの質も高まりやすくなります。
これは顧客から見れば、より良い商品・サービスが手に入ることつながるため、顧客満足度が満たされるようになるでしょう。また、窓口業務においてもテクニカルスキルが発揮され、接客対応の向上にもつながり、企業イメージとしても顧客からの信頼を得られます。
テクニカルスキルを向上させる方法
テクニカルスキルを得るための施策は、短期的・単発的な計画では大きな効果が得られません。自社の課題や状況を整理し、長期的な計画を練った上で検証を重ねながら実行することが大切です。
最後に、テクニカルスキルを向上させる方法について、以下の4つを解説します。
- 業務ごとのテクニカルスキルを整理する
- スキルマップを活用してスキルのレベルを可視化・管理
- 従業員ごとのスキルアップに向けた計画をつくる
- 研修(OFF-JTやOJT、講習など)でスキルアップを図る
①業務ごとのテクニカルスキルを整理する
まず、施策の実行にあたって、自社が抱えるどの業務がテクニカルスキルに該当するのかを洗い出す必要があります。これは商品やサービスによって求められる業務が異なるためです。
スキルの洗い出しの際には従業員個別だけでなく、チーム全体を見ることが大切です。それぞれの業務工程でスキルを精査すれば、漏れがなく、また個別単位での業務も把握しやすくなります。
なお、洗い出した情報は可視化できるようにデータで管理するのが良いでしょう。
②スキルマップを活用してスキルのレベルを可視化・管理
近年、ナレッジマネジメントにおいて、「スキルマップ」が注目されています。このスキルマップとは各従業員やチームで有するスキル・資格などを一覧にした表であり、抽象度の高い「スキル」を具体的に可視化できるツールです。
先ほどの調査で洗い出したテクニカルスキルをスキルマップに落とし込めば、各従業員・チームの「できること」を明確にできます。また、施策の効果検証や社内のメンテナンスなどにも利用できます。
③従業員ごとのスキルアップに向けた計画をつくる
スキルマップを用いれば、従業員が抱える現状やチームにとって必要なスキルが明確になります。これらを整理して、従業員ごとに必要なスキルや伸ばしたいスキルを決めていきましょう。
計画を立てる際には、必ず「チーム全体で見たうえで必要なスキルは何か」を検討することが大切です。立てた計画はスキルマップを使って、定期的に確認・指導をしていく必要があります。
④研修(OFF-JTやOJT、講習など)でスキルアップを図る
従業員ごとの計画が固まれば、それぞれに対して具体的なスキルアップを図ります。スキルアップには、社内の研修制度や社外研修、またセミナーや講演会などの手段が挙げられます。また、研修制度にはOFF-JTやOJT、講習などの選択肢も存在します。
自社の課題や優先すべきスキル、またスキル習得に必要な要素も踏まえて、適切な手段を選ぶことが大切です。
企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!
「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!
●スキル管理のメリット
●スキル管理がうまくいかない理由
●スキル管理を成功させる3つのポイント
よくある質問
- テクニカルスキルの具体例は?
-
テクニカルスキルには、汎用スキル、専門スキル、特化スキルの3つの種類があります
- テクニカルスキルを日本語で何といいますか?
-
「テクニカルスキル」とは、従業員が業務を遂行するうえで、必要になる専門的な知識・技術のことを指します。日本語では、「業務遂行能力」と言います。
- カッツ理論とは?
-
ロバート・カッツ氏が提唱した「カッツ理論」では、優秀な管理者の選抜と育成に効果的なアプローチを示すことを目的としています。このアプローチに必要な管理者のスキルとして、以下の3つが必要としました。
● テクニカルスキル
● ヒューマンスキル
● コンセプチュアルスキル