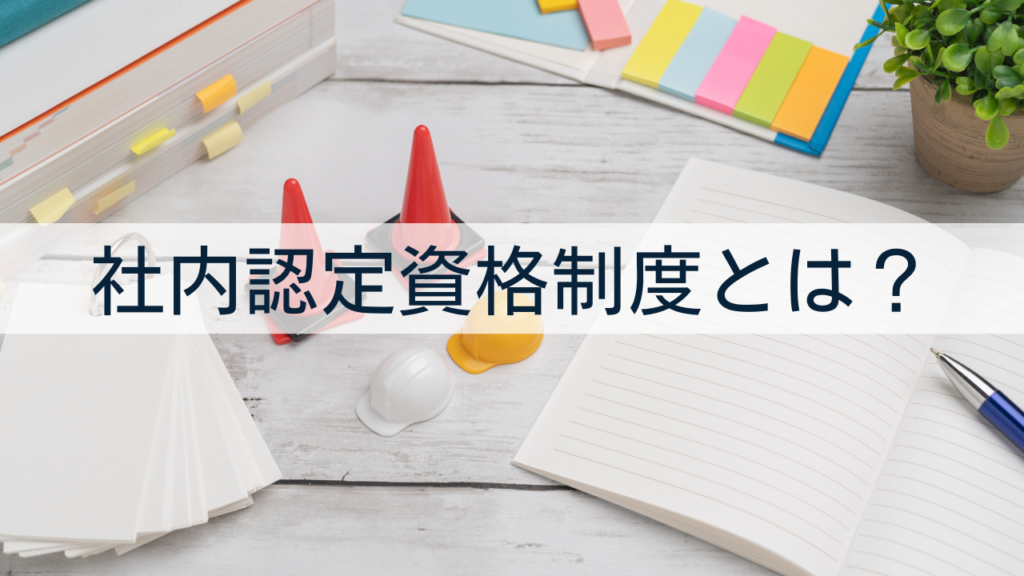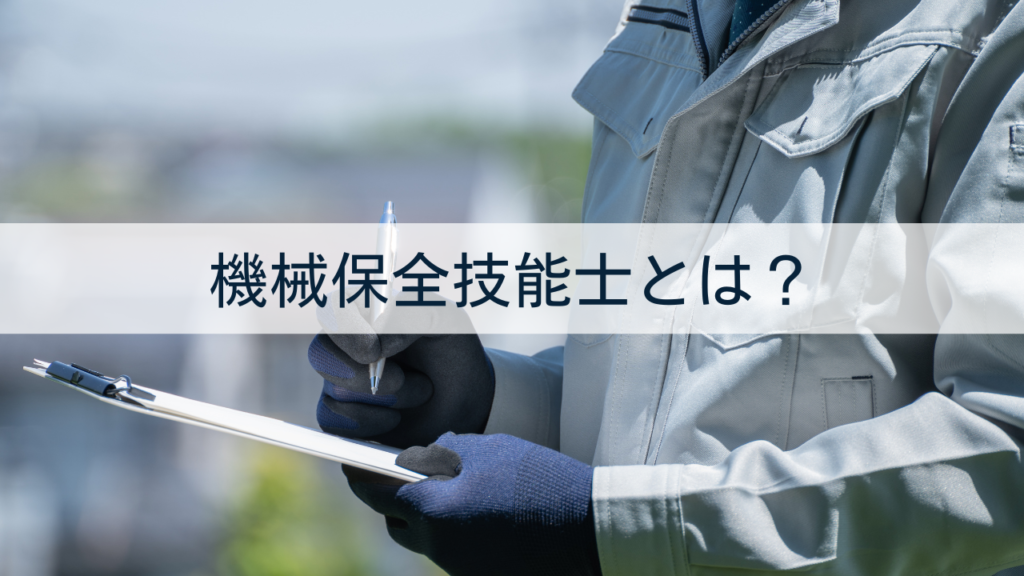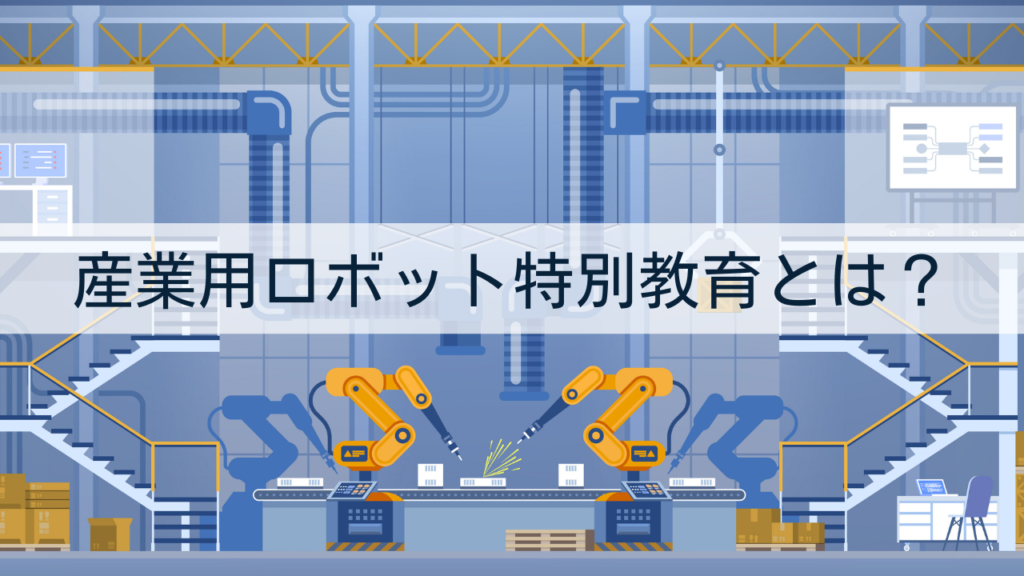資格– tax –
-

職長教育とは? 安全衛生責任者教育との違い・講習内容・受講方法まで徹底解説
建設業や製造業で役職につく際に受講を受ける必要がある教育に、職長教育・安全衛生責任者教育があります。 これらの教育は、危険を伴う可能性のある業務を行う場合においても、従業員が働きやすい職場環境を構築し、安全に業務を遂行するために必要不可欠なものです。 この記事では、職長教育と安全衛生責任者教育について、概要や受講内容、受験方法などについて解説します。 -

社内認定資格制度とは? 製造業における導入目的・メリット・構築ポイントを解説
社内認定資格制度とは、個々の企業が自社で雇用している従業員を対象として、独自に構築している資格制度のことを指します。社内資格の取得を通じてスキルの可視化・人材育成・モチベーション向上を図れるため、製造業を中心に導入が進んでいます。この記... -

資格管理とは? 資格を管理する目的とメリット、方法、収集項目、資格の種類、システム導入のメリットを解説
企業で行う業務の中には、資格を持っていないと担当できない業務や資格を持っていることで有利に進められる業務があります。資格管理とは、従業員が保有している資格や免許、特別教育などの情報を一元的に把握・整理し、業務分担や人材配置、人材育成に活... -

【無料テンプレート付】ISO9001で求められる教育訓練記録とは?力量管理・教育訓練記録の作成と評価のポイント
教育訓練記録は、従業員が業務に必要な力量を身につけるために行った教育・訓練の結果を記録したもので、その教育・訓練が有効だったかの評価を含む情報を指します。 ISO9001の力量管理でも、要求事項として教育訓練記録などの文書化した情報の保持が求められています。 ここでは、ISO9001の力量管理で求められている教育訓練記録などの文書化された情報について概要を説明しています。 -

機械保全技能士とは? 特級・1級・2級・3級の試験内容、合格率、難易度、勉強方法を解説
製造現場でよく耳にする機械保全技能士。この記事では機械保全技能士になるための「機械保全技能検定」の試験内容や合格率、取得のメリットを解説します。 -

【徹底解説】ITSS(ITスキル標準)とは?7段階レベル・11職種とスキルマップ活用法
ITSS(IT Skill Standard/ITスキル標準)は、日本における教育の指標として、高度な専門知識と技術を持つITプロフェッショナル人材の育成のために作られました。この記事ではITSSの概要と、実際にスキルマップなどを使って企業が運用していく際のポイントをご紹介します。 -

有資格者一覧表とは?【Excelテンプレート付き】作成・運用の目的と法令で必要な資格一覧
有資格者一覧表とは、「会社として管理が必要な資格(認定や免許等を含む)を洗い出し、従業員一人ひとりの持っている資格を一覧にした表」のことです。企業が「従業員の誰がどんな資格を持っているのか」を正確に把握することは、法令順守や安全管理、品... -

【修了証テンプレート付き】特別教育とは?業務一覧・実施方法・免許や技能講習との違いを徹底解説
労働安全衛生法で定められた一定の業務に従事する労働者は、特別教育を受けなければなりません。 本記事では、特別教育が必要な業務の一覧をはじめ、教育の内容、講師の要件や免許・技能講習との違いなどを詳しく解説します。修了証のテンプレートも用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。 -

産業用ロボット特別教育とは?資格の必要性・義務内容・受講方法・教育コストを徹底解説
人手不足が問題となっている製造現場において、産業用ロボットの市場規模が急速に拡大しています。 産業用ロボットの規模の拡大とともに大きな課題として浮上するのが安全面での対策です。産業用ロボットに関わる従業員には特別教育の受講が義務づけられています。 この記事では、産業用ロボットの特別教育について対象者や受講内容、受講方法などを解説します。 -

建設業法に準じた効率的な資格管理の方法とは? 防ぎたいリスクと3つの課題、スキルマップ・スキル管理システムの活用方法
建設業では建設業法に基づいて適切な資格管理を行う必要がありますが、管理業務は非常に煩雑であり、課題を抱えている企業も多くあります。この記事では、資格管理業務の現状とよくあるリスクを踏まえたうえで、改善するためのポイントをご紹介します。 建...