人事評価システムとは? 製造業の人事評価の課題、課題を解決する機能、導入のポイントを解説

製造業の現場では、職種が多岐にわたることや工程によって必要な技能や知識が幅広いため、必要なスキルが非常に多いという特徴があります。そのため個人の成果が数字に表れにくく、人事評価を難しく感じる管理職や、評価結果に不透明性を感じる従業員が少なくありません。
本記事では人事評価システムの主要な機能や、上記のような製造業の人事評価の課題、課題を解決する機能、導入のポイントについて具体例を挙げながら解説します。製造業ならではの課題を解決できるような人事評価システム導入の参考にしてください。
人事評価システムとは?
人事評価システムは、人事評価の依頼や評価結果の配布・回収、目標設定、結果集計を行うシステムです。紙やExcelの人事評価システムで起きていた転記ミスを防ぎ、進捗を即座に確認できます。結果を分析すれば、人材配置や教育計画の策定や実施にも活用でき、計画的な人材育成を後押しします。
人事評価システムの主要な機能
人事評価システムの機能は提供会社によってさまざまですが、本章では主要な機能を紹介します。
従業員情報の管理
人事評価システムは氏名、所属、資格、職歴などをカルテ形式で一元管理します。検索や抽出が簡単になり、配置や昇格検討の資料を瞬時に用意が可能です。たとえば、フォークリフト資格保有者だけを抽出して新ラインへの配置検討を行う、履歴を時系列で表示し昇格要件の充足度の確認なども簡単にできます。
目標管理
会社・部門・個人の目標を連動させ、進捗をグラフなどで見やすく表示できます。管理職は遅れを早期に発見し、課員へのフォローアップや支援策の検討が可能です。たとえば「不良率を月1%下げる」という目標に対し、実績を毎週取り込めば即座に差異が分かります。
とは?-300x169.png)
人事評価機能
点数入力とコメント記入を同じ画面で行うため、評価者の負担軽減にもつながります。また指標ごとに重みを設定できるので、職種ごとの配点調整も可能です。また、過去評価と並べて表示できるため、成長の軌跡を一目で把握できます。
評価ワークフロー管理
一次評価、二次評価、最終承認の流れを自動で通知します。進行状況は色分けなど分かりやすく表示され、遅れも一目で把握できます。操作履歴が残るため、不正な修正があればすぐ判明し、内部統制の面でも有効です。
人事評価システム導入のメリット
人事評価システムの導入には、評価業務の効率化以外にもさまざまなメリットがあります。
人事評価業務の効率化
人事評価システムの導入で、紙の配布やExcelでの集計が不要になります。事業規模などに寄りますが、年間で数十時間〜数百時間の作業を削減できるとされています。また、入力漏れは赤字など目立つ形で表示されるため、担当者はすぐ対処が可能です。提出状況が一覧で可視化され、催促も簡単に行えます。評価の周辺業務が効率的になり、削減した時間を育成施策に振り向けられるので、部門の付加価値を高められます。
従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上
評価基準とプロセスが可視化されると、従業員は「努力が正当に評価される」という安心感を得ます。逆に評価制度が不透明だと従業員は会社に不信感を抱きますので、離職率の低下にもつながります。目標と実績がリアルタイムで確認でき、さらに進捗が遅れた場合に本人と上司に通知が届けば、早期フォローが可能です。
人材育成・配置の最適化
評価データとスキル情報を重ねることで、誰がどの技能をどの熟練度で保有しているかを、色分けなどで分かりやすく表示できます。
たとえば、溶接レベルが不足している製造ラインを赤く表示し、候補者を自動抽出して研修計画を作成します。教育履歴が更新されるとマップの色が変わり、育成効果を即確認できます。加えて、欠員が出た際は要件を満たす代替要員を簡単に検索でき、ライン停止リスクが軽減します。このような適材適所が進めば歩留まり改善やリードタイム短縮にもつながり、組織全体の生産性向上を後押しします。
製造業における人事評価3つの課題
1.評価が難しい
製造工程への貢献を評価しにくい
営業職などは契約件数などで個人を明確に評価できるのに対し、製造業のライン作業は複数人で進めることが多いため、個人の貢献が数字に表れにくい特徴があります。また市況などの外部要因で生産量が変わることも多く、生産数量だけの評価では不公平です。
このように製造業では、製造工程への貢献が評価しにくいため、不良率や改善提案数などより多面的な評価を行うことが必要になります。

成果が見えにくく目標設定が困難
製造業の評価の難しさは、成果の見えにくさにも起因します。保全活動や改善活動は成果が長期で表れるため数値化しづらく、目標設定が難しいケースがあります。中間目標やプロセス目標を設定するなどの工夫を行うと評価する側もされる側も評価への納得感が高まります。
たとえば「不良率の低減」という最終目標に対し、「不良率の高い品種を10種類以上洗い出す」「一番不良率の高い品種の原因分析を行う」「原因になっていた老朽部品10個のうち2個の取り替えを完了する」など、細分化したプロセス目標を設定し、進捗率で評価します。定期レビューを行うことで、目標のずれを早期に修正できます。
2.職務ごとのスキルが多く、評価業務が煩雑
職務ごとのスキルが多すぎる
製造業では、製造、検査、保全、技術など職務が多様で、職務を横断した共通の評価シートでは職務に必要なスキルを網羅できません。日常業務も多いなか、各職場で必要なスキルを洗い出すのは難しいでしょう。また評価シートに記載するスキル項目には定期的な見直しが必要ですが、現場任せではなかなか見直しが進まないケースも多いようです。
同一の評価シートで管理できない
部署ごとに必要な評価項目や評価軸が異なるため、紙やExcelでの人事評価ではその部署でしか分からない内容になりがちです。そのため最終的な人事部の確認がおろそかになる恐れがあります。部署特有の項目を手軽に追加できる人事評価システムであれば、フォーマット自体は全社共通としつつ、人事部にも見やすい内容になります。
3.評価結果への納得感が薄い
前述のとおり、製造業では個人評価の難しさや必要なスキルの多さから、人事評価が不透明になりがちです。評価後の上司との面談だけでは、人事評価の詳細まで各従業員に伝えるのは難しいのが現状でしょう。しかし、人事評価システムを活用し、従業員と以下のような情報をこまめにやり取りすると、評価結果への納得感が増す傾向にあります。
- 事前に評価軸を共有する
- 評価結果をコメントで残す
- 上司との面談記録を人事部にも共有する
- 360度評価や相互フィードバックを併用し評価者の偏りを減らす
従業員の納得感が高まれば、離職率の低下と定着促進が期待できます。
課題を解決する人事評価システムの機能
上記のように製造業における人事評価は複雑になりがちで、個人の力で従業員に適切な評価を行うのは困難です。
これらの課題を解決するのが人事評価システムになります。人事評価システムにはさまざまな機能があり、煩雑な人事評価の効率化が可能です。
人事評価が効率化できれば、実際の各従業員への評価や面談時間の確保など、人事評価への納得感が増すような業務に時間を割くことができるようになります。
定量評価と定性評価を組み合わせた「評価テンプレート」
人事評価システムでは、生産数や不良率などの定量指標と、改善提案や協調性などの定性的な行動指標を組み合わせたテンプレートが作成可能です。 定性・定量の両面から評価することで、製造工程への貢献度を多角的に評価できます。指標の重みは画面で変更できるので、事業環境の変化にも対応可能です。 また、人事評価システムの機能によっては、生産管理システムと連携させることで、生産数・残業時間・不良率などのKPIを自動取得できます。加えて、センサーやIoTデバイスが収集する作業スピードや稼働率、設備の稼働状況もリアルタイムで反映し、客観的な定量指標の強化も可能です。集計結果はレーダーチャートで出力できるので、その従業員の強みと弱みを一目で把握でき、育成計画策定にも役立ちます。

多様な職務に対応する「柔軟な評価項目設定」
人事評価システムでは、職種・工程ごとの評価項目を簡単に追加、削除、並べ替えできます。たとえば、組立工程では「作業時間短縮率」、物流工程では「ピッキング精度」、保全部門では「MTTR(平均修復時間)や保全提案数」、安全担当には「ヒヤリハット報告件数」など職務固有の指標を盛り込めます。システムが連携されていれば、実績値が自動紐付けされるため、現場の入力負荷は最小限に抑えられます。
また、ドラッグ操作で順序を変えられるため、毎年の制度改定にもすぐ対応できます。またテンプレートは履歴管理され、過去との比較も容易です。
評価プロセスの透明性を高める「評価ワークフロー管理」
評価開始から承認完了までの進行を一覧表示でき、評価プロセスの透明性を高められます。担当者と期限が明確なので、評価の遅延も防ぐことができます。
フィードバックの質を向上させる「コメント・面談記録機能」
人事評価への納得感を上げるにはフィードバック面談が必須です。人事評価システムでは、評価結果に対するコメント機能や面談記録の保存機能がありますので、評価理由の共有が促進され、従業員の納得感と信頼性が高まります。
また、過去の履歴を参照すれば従業員の長期的な評価推移が確認できるので、評価面談の質の向上にも役立ちます。
技術やスキルの多様性を管理する「スキルマップ機能」
業務に必要な資格やスキルを一元管理し、スキルの有無や習熟レベルを可視化する機能です。育成計画や適材適所の人員配置に活用が可能になります。たとえば、フォークリフト免許、溶接資格など必要な免許を保持していない従業員には外部講習を案内できます。
スキルマップとは?
スキルマップとは、業務に必要なスキルに対し各従業員の持っているスキルを一覧にした表です。各職場の従業員が保持するスキルの見える化で多能工化が進み、従業員育成の計画が立てやすくなるなどのメリットがあります。
スキル管理システムとは?
スキル管理システムとは、各従業員のスキル情報の登録・更新・分析を自動化する専用ツールです。組織としての強みや弱みを把握することができ、経営戦略や事業計画の立案にも活用可能になります。人事評価と組み合わせれば、スキルデータを計画的な人材育成・教育訓練や、戦略的な人材配置にも役立てられます。

人事評価システムを導入する際のポイント
目的に合った機能があるか
まず評価制度の目的を整理し、必要な機能をリストアップしましょう。デモで操作感を確認し、不足があれば追加開発や他ツール連携を検討します。導入後に機能を追加しにくい部分はとくに慎重に検証することが重要です。社内のロードマップと比較し、将来も使えるかも含めて判断しましょう。
使いやすいか
人事評価を行うのは各職場の管理職や従業員ですので、使いやすさは非常に重要です。画面が直感的に操作できるのであれば現場に定着しやすくなります。スマートフォン対応や操作説明の動画があるとさらに利便性が増します。試用期間を設け、現場からの意見を反映すると失敗を防ぎやすいです。
他のシステムと連携できるか
勤怠や給与システムとデータを共有できると、総務部などの入力作業が減り非常に便利です。データの二重管理がなくなり、転記ミスも防げます。また、生産管理システムと連動し、生産実績と比較分析すれば評価サイクルが速くなるでしょう。
提供形態(オンプレかクラウドか)
社内サーバーを用いるオンプレ版はカスタマイズしやすいですが、初期費用が高めです。一方、クラウド版は月額課金ではじめやすく、拠点追加も簡単です。まずは自社の情報管理ポリシーを確認し、費用と運用負荷を比べて選定しましょう。
料金は適切か
ユーザー数や追加機能で料金が変動するので、見積もり時には導入サポートやデータ移行費用を確認しましょう。費用対効果を算出し、削減時間と離職率低下などの効果を経営層へ示すと採択が進みます。将来の利用者増加を想定し、段階的な料金体系を選ぶと安心です。
多言語対応が可能か
海外に工場がある場合は、多言語表示が不可欠です。画面や通知メールなどが各言語で出力できるか確認しましょう。自動翻訳辞書を共通化すると、評価基準の意味がずれません。音声入力や読み上げ機能があれば、コミュニケーションがさらに円滑になります。
セキュリティは万全か
評価データは個人情報なので暗号化通信が必須です。二段階認証やIP制限があると不正アクセスを防げ、情報漏えいリスクを減らせます。また、データセンターの災害対策や定期的な脆弱性診断も確認が必要です。
企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!
「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!
●スキル管理のメリット
●スキル管理がうまくいかない理由
●スキル管理を成功させる3つのポイント
→詳しくはこちらから
- 人事評価システムとは何ですか?
-
人事評価システムは、人事評価の依頼や評価結果の配布・回収、目標設定、結果集計を行うシステムです。紙やExcelの人事評価システムで起きていた転記ミスを防ぎ、進捗を即座に確認できます。結果を分析すれば、人材配置や教育計画の策定や実施にも活用でき、計画的な人材育成を後押しします。


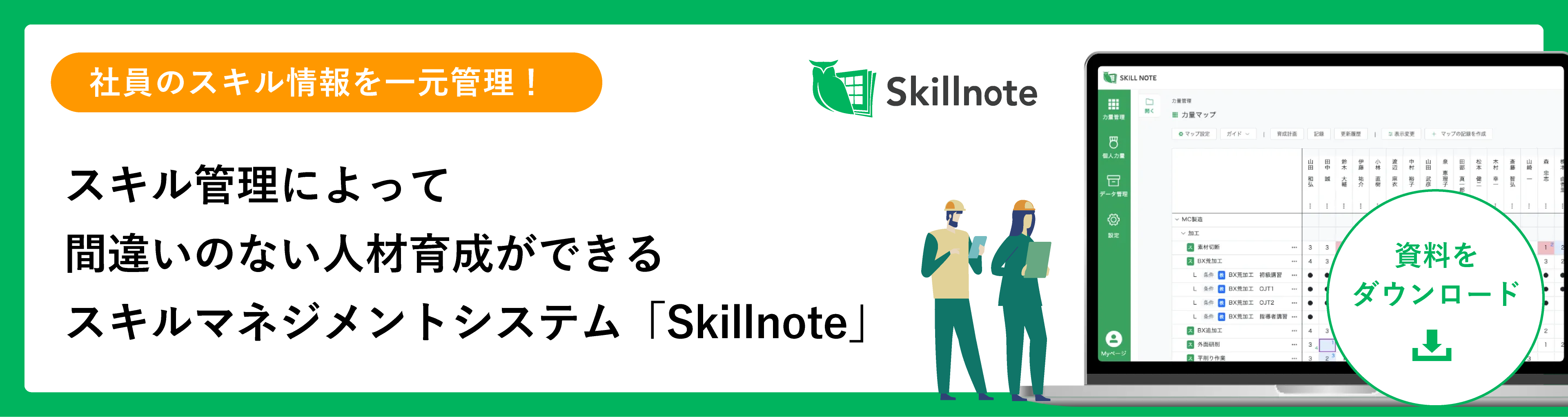
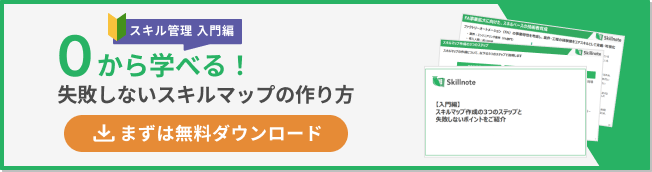





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)













