予知保全×スキルデータ活用──現場の生産性を高める仕組み
DESIGNQ-419_-1200_630.png)
製造業の設備老朽化が深刻です。1分のライン停止で最大2億円の損失が発生するケースもあります。設備リプレイスには莫大なコストがかかるなか、予知保全とスキルデータの組み合わせが注目されています。本記事では、故障予兆の検知から最適な保全要員の即座配置まで、ダウンタイム最小化を実現する予知保全×スキルデータ活用の仕組みを詳しく解説します。
設備の老朽化に内在するリスク
設備の老朽化をどう解決するかは、製造業の喫緊の課題です。設備が老朽化することで、故障リスクは高まります。それまで稼働していた設備が突然故障すれば、ライン停止を余儀なくされます。製造業にとってライン停止は莫大な損害を招きかねない重大なリスクです。企業には対応が求められています。
大きな損害が発生するリスクがある。
経済産業省がまとめた「2020年版ものづくり白書」に、生産設備を導入してから経過した年数に関するデータが載っています。それによれば、金属工作機械では約45%、鋳造装置では約50%、第二次金属加工機では約70%が生産設備を導入してから15年以上経過しているのです。2018年の調査データということもあり、現在とはやや状況は異なるかもしれませんが、製造業の設備状況の大枠はこれで十分汲み取れます。もちろん新しい設備でもダウンタイムは発生しますが、老朽化した設備の比ではないことは明らかです。
ライン停止は莫大な損害につながることは先述しましたが、MONOistの2021年の記事では自動車の製造業を例に具体的な損失額が試算されています。それによれば、1分間の稼働停止で2万2,000ドル、1時間続けば130万ドルとのこと。これは日本円換算でおよそ2億円の損害が生まれる計算です。なかには1分間の稼働停止で5万ドルの損失が出る工場もあると言います。ライン停止がいかに大きな損害を招くかがわかります。
また、ライン停止は人的コストの損害も招きます。停止中は従業員の手が空いてしまうからです。もちろん使い慣れた設備には「使いやすさ」のメリットがありますが、ライン停止したときのリスクを鑑みればリプレイスを検討したほうがよいことは間違いありません。

ダウンタイムの回避など予知保全によるメリットは大きい
設備のリプレイスには莫大なコストがかかることも事実です。そこでコストを抑えつつリスクも避ける解決策が求められます。その有効な手段が予知保全へのスキルデータ活用です。
予知保全とは
予知保全とは「設備状況を常時監視して設備に不具合が発生する兆候を察知し、察知した情報を元に保全業務を行うこと」です。一方、設備の稼働期間や総稼働時間、総作動回数など、あらかじめ保全タイミングを決めて保全業務を行うのが予防保全です。予知保全は予防保全の一部に組み込まれており、予兆を基準に保全業務を行うことから予兆保全と呼ばれることもあります。

予防保全との違い
予知保全に比べて計画性の高い予防保全は、高頻度で行うことで、故障リスクを軽減できます。しかし、ダウンタイムが増えるというデメリットがあります。一方、予知保全は機械が故障する予兆を察して保全業務を行います。そのため、予防保全に比べてダウンタイムを回避しやすいというメリットがあります。
予知保全は在庫や人的コストを抑えられる
予知保全は予兆を基準に保全業務を行うというその性質上、在庫を抑えて交換時期を最適化できるというメリットがあります。そのため、在庫を抱えがちな予防保全に比べて部品を寿命に近い期間まで使用できます。
また、予知保全では予兆が出てから保全業務を行うため、保全業務にかかる人や時間を最小化できるというメリットもあります。
予知保全の難点
予知保全には難しさもあります。それは保全業務の基準である「予兆」をピンポイントで測ることが難しいということです。高性能なIoTシステムが必要とされることもあり、高度なデータ解析も必要となります。また、予兆に対して保全を行うかどうかの基準も個別に設定しなくてはいけません。取得すべきデータ、データの解析、解析結果から保全を行うタイミングの決定など、難しい判断を下した上で即座に保全業務に当たる必要があります。その際には、設備ごとに必要なスキルを持った従業員を配置しなくてはなりません。
予知保全にスキルデータ活用を組み入れることで得られるメリット
以上のように予知保全には独特の難しさがあることは事実です。しかし、ライン停止のリスクの軽減、在庫や人的コストの抑制など、適切に実施・運用できれば得られるメリットが多いことも明らかです。スキルデータを上手に活用できれば、そのメリットも最大化されます。
たとえば、設備保全を行うのに必要なスキルを持った従業員の数をスキルマップによって可視化したと考えましょう。そのとき、細かい作業レベルやレベルの分布、具体的な従業員名まで「見える化」できていれば、スキルの不足する保全業務領域を特定して応援や計画的な育成によって補充することができます。つまり、保全業務における従業員の最適配置を実現できるのです。これにより、いざというときに業務に当たれる従業員がいない、という最悪の事態を事前に回避することができます。
さらに、設備故障の予兆と保全に関するスキルデータを統合して従業員を配置することも可能になります。故障の予兆が起こったら、故障を直せるスキルを持ち、即座対応のできる従業員を検索して保全業務に当たらせることができるのです。
また、設備が多種多様なために必要となるスキルが多岐にわたる場合には、あらかじめ設備ごとに必要なスキルを社内資格として定義・認定しておくことで、従業員の検索・配置がスピーディーに行えるようになります。
このように予知保全にスキルデータを組み合わせて活用することで、設備故障に前もって対処し、ダウンタイムを最小化することができます。それは、設備を長く稼働させることにもつながります。その意味でスキルデータを予知保全に活用することは、SDGs的にも効果的な取り組みと言えるでしょう。
製品の品質向上を、「スキル管理」で実現しませんか?
製品の「品質向上」を目指すならスキルマネジメントシステム「Skillnote」!
●スキルデータの活用で「品質向上」に貢献
●「品質向上」に寄与するスキルマップがかんたんに作れる
●「品質向上」に成功した事例を大公開
→詳しくはこちらから

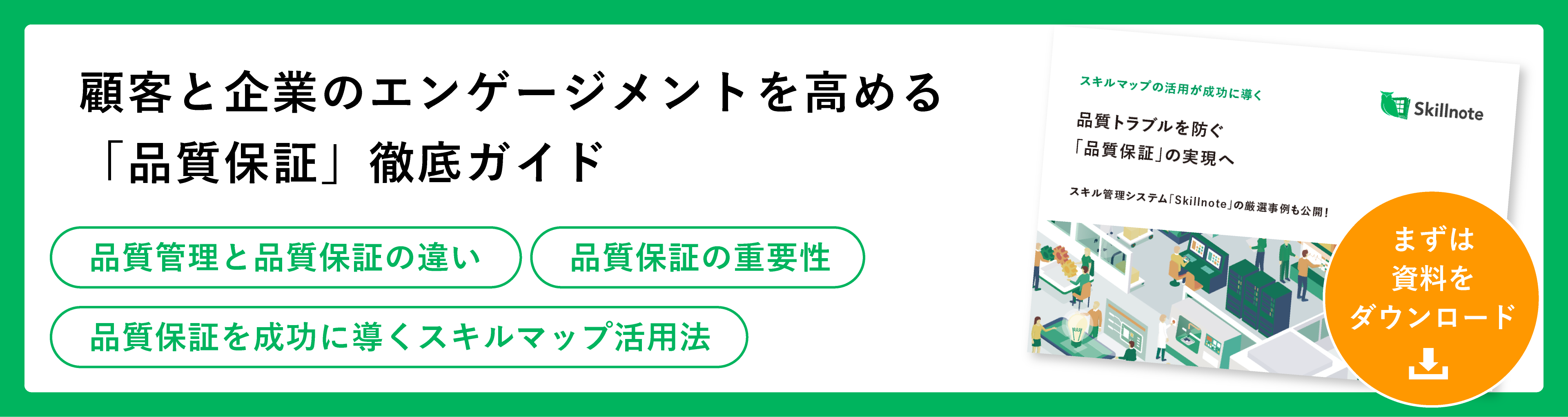





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)














