スキルベース組織とは?ジョブ型雇用との違い・注目さえる理由・効果と海外事例を解説

日本国内では大企業を中心にジョブ型雇用への移行が広がっています。一方、これまでジョブ型雇用の多かった米国では、新たな人材マネジメントへの取り組みが始まっています。この新たな人材マネジメントは「スキルベース組織」と呼ばれ、一部の企業では導入が開始されました。
スキルベース組織は2023年10月に米国ラスベガスで開催された「HR Technology Conference & Exhibition 2023」の注目キーワードとして、生成AIとともに紹介され一気に注目が集まっています。さらに、世界最大の会計事務所であるDeloit teInsightsは2022年9月にスキルベース組織に関する調査報告書を発行。その後、2023年3月にデロイト・トウシュ・トーマツ(以下デロイト)が翻訳・加筆した日本語版も発行されました。
本記事ではこの調査報告書を引用しながら、スキルベース組織とは何なのか、ジョブ型雇用との違い、期待できる効果や海外事例などを解説します。ぜひ最後までお読みください。
スキルベース組織とは
スキルベース組織(skills-based-organization)とは、従業員の持つスキルを中心に組織を構築・運営する新しい組織モデルです。ジョブ型雇用で仕事の最小単位であったジョブ(職務)をタスク(作業)まで分解し、従業員のもつスキルとタスクをマッチングさせる考え方です。
従業員の仕事は役割や職務記述書に固定されず、個々のスキルやプロジェクトの要件に応じて柔軟に変化するので、活躍の可能性が広がります。一方、組織の観点からは、プロジェクトやタスクごとに最適なスキルを持つ人材を柔軟に組み合わせられるので、効率的かつ創造的な業務遂行ができるというメリットがあります。
ジョブ型雇用との違い
ジョブ型雇用は組織が定義したジョブ(職務)に対して、それを遂行できる人材をマッチングさせる雇用システムです。採用の際にあらかじめ担当するジョブが明確に決まっていることが特徴です。ジョブに対して最適な能力や適性の人材が配置できるとされ、米国では長くこの方式がとられていました。近年では日本企業でもメンバーシップ型(職務内容を限定せずに採用を行い、人に応じて職務をつける雇用形態)からジョブ型に移行する企業が増えています。
なお、スキルベース組織とジョブ型雇用の違いは以下の4点が挙げられます。
柔軟性の有無
ジョブ型は職務記述書に縛られ役割が固定されるのに対し、スキルベース組織は従業員のスキルに応じて役割が柔軟に変化します。
人材活用の幅
ジョブ型では一人の従業員に多くのタスクを求めがちですが、スキルベースでは複数人がスキルを補完し合い、チーム全体で成果を出せます。
評価の基準
ジョブ型は役割や成果を中心に評価される一方、スキルベースは保有スキルや成長度も評価の対象となります。
市場変化への対応力
ジョブ型は業務変更に弱い傾向がありますが、スキルベースはスキルを軸に新しい業務や環境変化へ柔軟に適応できます。

ジョブ型雇用の問題点
米国でジョブ型雇用からスキルベース組織へ移行が始まったのは、ジョブ型雇用の問題点が顕在化してきたためです。デロイトの調査報告書では、ジョブ型雇用の問題点を以下のように述べています。
ジョブという考え方に基づき、仕事を機能ごとに標準化されたタスク(業務)に限定してしまうこと、そして組織階層の中で定められたジョブ(だけ)に基づいて、労働者に関する全てのことを決めてしまうことは、アジリティ(機敏性)や成長性、革新性、多様性、一体感、公平性といった、今日、企業にとって最も重要視される組織能力を毀損したり、労働者に適切なキャリアや経験を提供できないことにつながりかねません。
デトロイト・トウシュ・トーマツ「スキルベース組織―新たな仕事と労働者のモデル|デロイト・トウシュ・トーマツ調査資料」
たとえば、あるポジションに必要なジョブ(職務)が10種類のタスクから構成されていたとします。ジョブ型雇用ではこの10種類のタスク全て、あるいはほとんどに対応できるスキルの持ち主を採用しなければいけません。このため、なかなか人材が見つからないケースが多くありました。また、人材が見つからないため、10種類のうち9種類のスキルしか持たない従業員が採用され、持っているスキル以上のタスクをこなすケースも散見されました。
このように従業員をジョブで縛るのは、近年ビジネスで重要視されているスピード感や革新性、従業員の多様性や成長の機会を奪ってしまうことと考えられています。
しかし、スキルベース組織では、必要なスキル10種類のうち5種類を持つ2人、あるいは4種類を持つ人を3人など、複数人を採用して業務を遂行できます。これなら、企業も人材を見つけやすくなります。また、従業員側も自分のスキルにあわせていくつものタスクを行えるので、自分のスキルを数多く活かせる可能性が広がります。
スキルとは
スキルベース組織において、スキルはかなり広義で捉えられています。単純に「できる」「できない」といった能力だけではなく、個人の特性や適性も含まれるのです。
一方、日本国内の製造業では、スキルを「力量」と同義に捉えるケースが多いです。とくに、ISO 9001における力量とはこのハードスキルに該当します。スキルベース組織におけるスキルは力量にとどまりません。ソフトスキルや潜在的な能力も含めたより広い意味を指します。
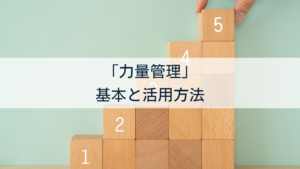
ユニリーバ社の例
スキルベース組織を先駆的に取り入れているイギリスのユニリーバ社では、「U-Worker(ユーワーカー)」という制度を設けています。ユーワーカーは短期プロジェクトごとにユニリーバと契約している労働者で、クラウド上に登録されています。福利厚生や最低賃金が保障されているのが特徴です。
ユニリーバでは部門単位の仕事がプロジェクトやタスク、成果物に細分化されつつあり、必要なタスクやジョブが発生した際にユーワーカーは仕事を受注します。
デロイトの報告書によると、ユニリーバ社の副社長であるPatrickHull氏はスキルベース組織が人材確保に貢献していると話しています。
私たちは、多くの組織と同じように各領域がサイロ化(連携していない状態)していたことによって、これまで考慮せずにいたかもしれない人々に対して、門戸を開くことができます。(今後さらに細分化したスキルにフォーカスできれば)外部からの採用や社内人材マーケットでよりターゲットを絞ることができるようになり、タスクやプロジェクトに適所適材な人材配置ができるようになります。それが業績の向上につながると考えています。
デトロイト・トウシュ・トーマツ「スキルベース組織―新たな仕事と労働者のモデル|デロイト・トウシュ・トーマツ調査資料」
スキルベース組織が注目を集める背景
現在スキルベース組織が世界的に注目を集めている背景には、社会や市場の大きな変化があります。ここでは下記の4点から解説します。
生成AIや自動化など急速な技術革新
生成AIや自動化の普及により、従来の職務が急速に変化していることで、従業員のスキルを軸に業務を再設計する必要性が高まっている。
人材不足の深刻化
日本を筆頭に先進国では人材不足が深刻化しており、スキル単位で人材を組み合わせるスキルベース型のアプローチが求められている。
働き方の多様化
副業やフリーランス、プロジェクト型など、多様な働き方が広がり、ジョブ型だけでは対応が困難になった。
従業員のエンゲージメントの低下
メンバーシップ型やジョブ型などの従来の雇用モデルでは従業員の成長機会は限定されやすく、スキルに焦点を当てることで従業員の働くモチベーションを引き出せると期待されている。
スキルベース組織で期待できる5つの効果
効果1:人手不足が解消される
米国は長年慢性的な人手不足に陥っており、スキルベース組織の運用でこの問題が解決できないか模索しています。「ジョブ型雇用の問題点」の章でも述べたとおり、多くのスキルが必要となる職種に対して十分なスキルを保有する人材を見つけるのは困難です。
しかし、スキルベース組織では1つの仕事に対して違うスキルを持つ複数のメンバーで対応できるため、人材を採用しやすくなります。
効果2:従業員のスキル開発が進む
スキルベース組織では、強みにできるスキルと足りないスキルが明確になります。このため、足りないスキルを補うスキル開発が容易になります。
デロイトの調査報告書でも、企業への「労働者の幸福に対する組織の責任の高まり」という章で以下のように述べられています。
仕事を行う人々と、そのために必要なスキルに焦点を合わせ直すこと、そして必要なスキルトレーニングを提供することで、雇用の可能性を高めることができます。例えば、自動化によって職を失った従業員や、もはやその役割を必要とされなくなった従業員が持つ基礎的なスキルや隣接スキルを特定することは、彼らを必要とする仕事に配置転換をするのに役立ちます。
デトロイト・トウシュ・トーマツ「スキルベース組織―新たな仕事と労働者のモデル|デロイト・トウシュ・トーマツ調査資料」
効果3:従業員のエンゲージメント向上
スキルベース組織では、個人のスキルに着目するためそれぞれの強みを活かせる可能性が広がります。さらに、スキルへの着目は、ジョブ型雇用よりも採用の公平性が上がるとされています。これらのことからも、スキルベース組織では、従業員のエンゲージメントが向上すると考えられています。
効果4:市場環境の変化に対応できる
近年は市場環境の変化が大きく、その速度は加速しています。そのため、ジョブ型雇用ではジョブディスクリプション(職務記述書)を作成しても、日々新しい業務が生まれ、すぐに古くなってしまうという課題がありました。このような経緯から、ジョブではなくスキルをベースにした人材戦略が市場変化に柔軟に対応できるものとして注目されるようになりました。
効果5:生産性向上・利益向上
ここまで述べてきたようなスキルベース組織が人材マネジメントにもたらすメリットは、企業の生産性や利益率の向上に貢献するものです。人手不足が解消され、従業員のスキル開発やエンゲージメントの向上が進めば、さらに生産性や利益率は向上するでしょう。
スキルベース組織を実践するには?
スキルベース組織は海外でも始まったばかりの新しい取り組みです。日本ではまだ独自の慣習も残っているため、スキルベース組織を取り入れるには人材に関する考え方から変えていく必要があります。しかし、これまで見てきたスキルベース組織の効果を考えると、いずれ日本でも導入を検討する企業が出てくるでしょう。
ここではスキルベース組織の導入に備え、人材戦略における主要な場面でスキルベース組織だとどのような対応になるのかを解説します。
スキルベース組織での人材採用
スキルベース組織での人材採用の場面では、ジョブ型雇用より多くの人材から採用が可能になります。
ある通信会社の事例では、人材確保が難しい機械学習の専門家を直接採用するのではなく、関連スキルを持つ人材を広く探しました。そして、採用後に必要な機械学習スキルを迅速に教育したそうです。これにより採用可能性のある人材は3倍に増加しました。
スキルベース組織での人材配置
スキルベースの人材配置では、従来の年功序列や肩書、ジョブにとらわれない、柔軟で効率的な組織運営が可能です。各ポジションやプロジェクトに必要なスキルを定義し、従業員のスキルデータベースと照合し、最適な人材をアサインします。
従業員のリスキリング
急速に変化するビジネス環境において、企業にとっても個人にとってもリスキングが重要です。リスキングとは「Re-skilling」、すなわちスキルの学び直しを意味します。
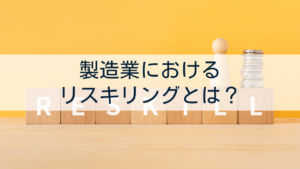
スキルベース組織ではジョブの枠組みに囚われずに学びを広げられるため、従業員の可能性は広がります。また、従業員自身が自分のスキルの方向性に決定権を持つことはキャリアの自律にもつながり、より学習意欲が高まると考えられています。
デロイトの調査報告書の「1人の働く個人としての労働者の能力開発」という章で以下のように述べられています。
労働者をジョブの保持者としてではなく、ユニークな個人としてみることの重要な側面は、全ての個人が継続的に学び、成長し、自分のスキルをどのように仕事に展開するかを決定する能力があると認識することです。ジョブの枠から解放されることで、労働者はより容易に新しいことに挑戦し、継続的に学習し、既存のスキルをベースに新しいスキルを強化し、EQや問題解決などの基礎的なケイパビリティを全く新しい方法で活用することができます。これこそ、学習を、仕事の流れの中で体験的に、目の前の問題に適用して行うことができる最良の方法です。
デトロイト・トウシュ・トーマツ「スキルベース組織―新たな仕事と労働者のモデル|デロイト・トウシュ・トーマツ調査資料」
スキルベース組織の下準備 スキル管理システム・スキルマップの導入
スキルベース組織は海外でも始まったばかりの取り組みですが、いずれ日本でも取り入れる企業が増えるものと予想されます。スキルベース組織の実現のためには、従業員のスキルのデータベース化を進めていく必要があります。スキルのデータベース化の方法として、スキル管理システムとスキルマップの活用を紹介します。
スキル管理システム
スキル管理システムとは、従業員が保有するスキルを管理するシステムです。企業によってその規模や項目は異なりますが、従業員の持っているスキル(能力や経験、研修の受講歴や資格の取得歴)が一元管理できます。
スキル管理システムを活用すれば、スキルデータという定量情報をベースに確実性の高い計画的な人材育成計画の作成や、戦略的な人材配置が可能となります。

スキルマップ
スキルマップとは、各従業員の持っているスキルを一覧にした表のことです。力量管理表や技能マップ、スキルマトリックスとも呼ばれます。
スキルマップでは、従業員のスキル情報が横並びで管理できます。スキルマップによって、ISO9001が要求する力量管理はもちろん、客観的なスキル情報を基にした人材育成や人材配置が可能になります。

企業と従業員を成長に導く「スキルベースの人材マネジメント」を解説!
スキルの見える化と活用を支援する「Skillnote」で、人材育成・適正配置を加速しませんか?
●スキルベース組織に対応するための第一歩
●スキルデータを活かした配置・育成の実現
●ISOや監査対応と両立するスキル管理
→今すぐ「Skillnote」のサービス資料をダウンロードする
よくある質問
- スキルベース組織とは?
-
スキルベース組織(skills-based-organization)とは、従業員の持つスキルを中心に組織を構築・運営する新しい組織モデルです。ジョブ型雇用で仕事の最小単位であったジョブ(職務)をタスク(作業)まで分解し、従業員のもつスキルとタスクをマッチングさせる考え方です。
- ジョブ型雇用とスキルベース組織の違いは何ですか?
-
ジョブ型雇用は組織が定義したジョブ(職務)に対して、それを遂行できる人材をマッチングさせる雇用システムです。採用の際にあらかじめ担当するジョブが明確に決まっていることが特徴です。スキルベース組織とジョブ型雇用の違いは以下です: 柔軟性の有無 ジョブ型は職務記述書に縛られ役割が固定されるのに対し、スキルベース組織は従業員のスキルに応じて役割が柔軟に変化します。 人材活用の幅 ジョブ型では一人の従業員に多くのタスクを求めがちですが、スキルベースでは複数人がスキルを補完し合い、チーム全体で成果を出せます。 評価の基準 ジョブ型は役割や成果を中心に評価される一方、スキルベースは保有スキルや成長度も評価の対象となります。 市場変化への対応力 ジョブ型は業務変更に弱い傾向がありますが、スキルベースはスキルを軸に新しい業務や環境変化へ柔軟に適応できます。
- スキルベース雇用とはどういうものですか?
-
スキルベース組織(skills-based-organization)とは、従業員の持つスキルを中心に組織を構築・運営する新しい組織モデルです。ジョブ型雇用で仕事の最小単位であったジョブ(職務)をタスク(作業)まで分解し、従業員のもつスキルとタスクをマッチングさせます。ジョブ型に対してスキルベース組織では、必要なスキル10種類のうち5種類を持つ2人、あるいは4種類を持つ人を3人など、複数人を採用して業務を遂行できます。これなら、企業も人材を見つけやすくなります。また、従業員側も自分のスキルにあわせていくつものタスクを行えるので、自分のスキルを数多く活かせる可能性が広がります。


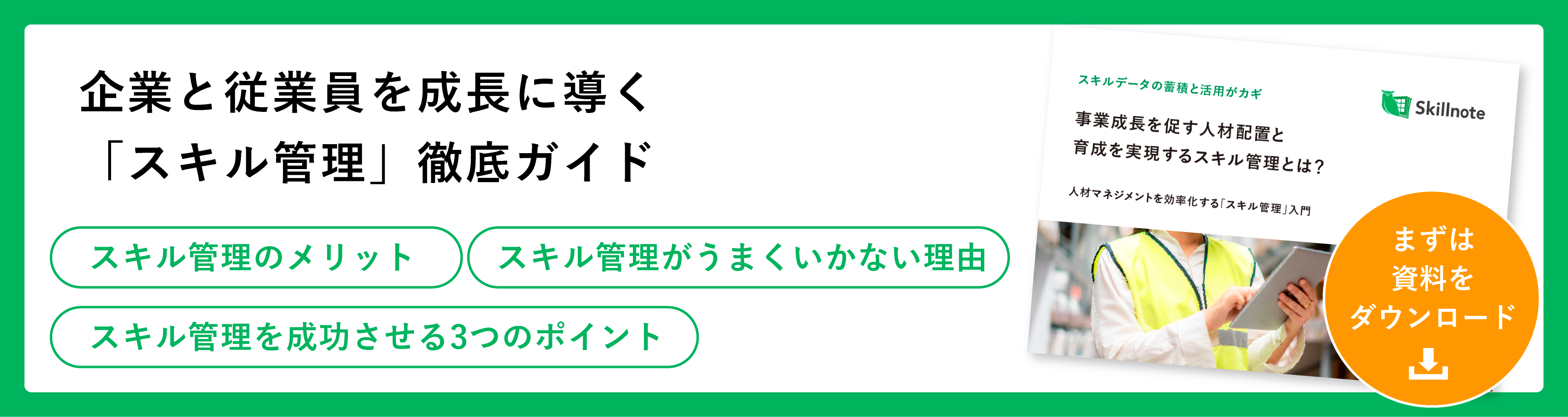
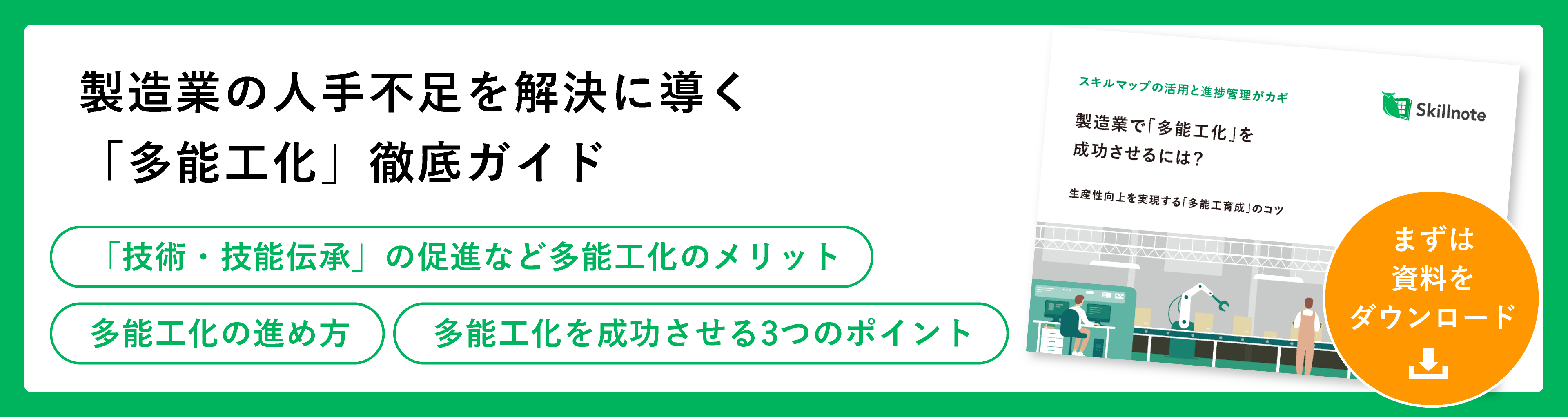
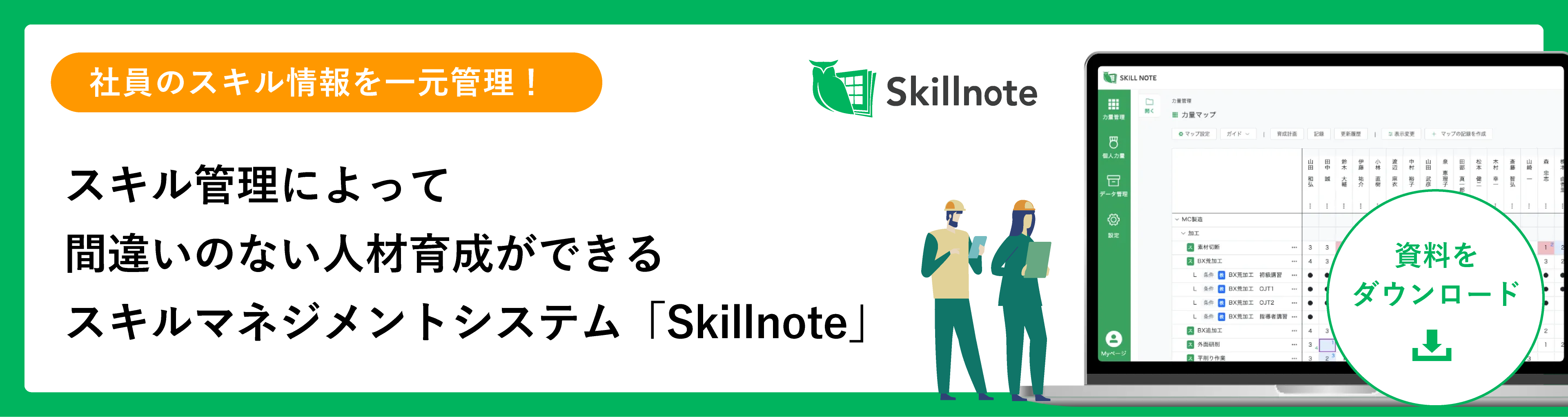





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)













