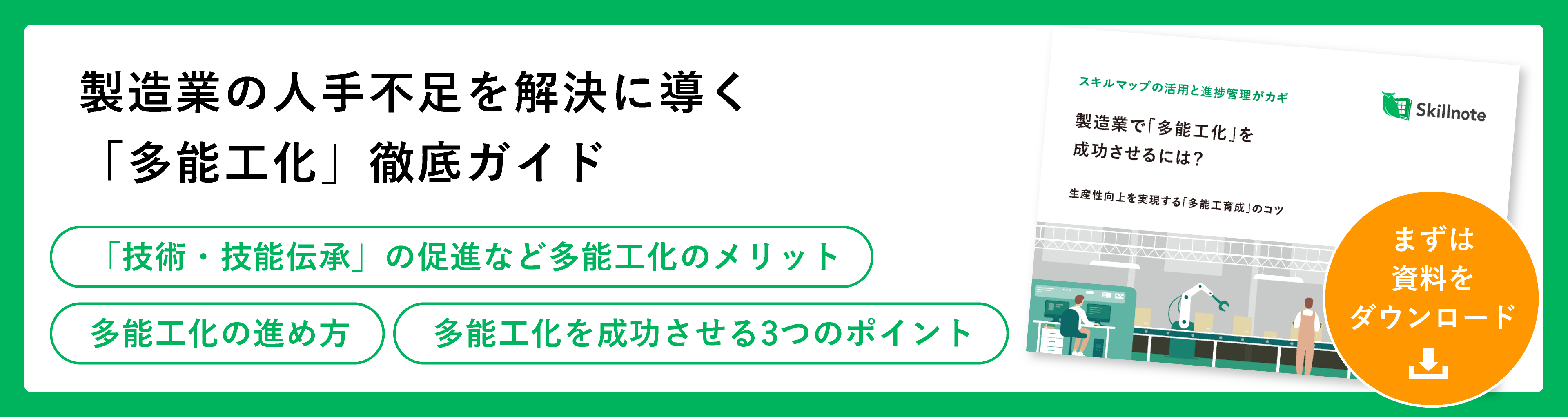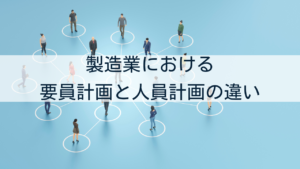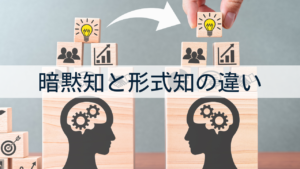多能工化(マルチスキル化)とは、組織内で働き手一人ひとりが複数の業務に対応できるよう、教育・訓練を行うことを意味しています。従来の「単能工化」では、特定の作業に特化した人材しか育成できず、業務の偏りや生産性低下のリスクがあります。本記事では、多能工化の基本からメリット・デメリット、製造業で成功させるポイントまでを整理し、具体的な実践方法をご紹介します。
目次
多能工化とは
多能工化とは、1人の従業員が複数の業務に対応できる状態を指します。これにより、特定工程に偏らず、組織全体で業務を柔軟に回せるようになります。
単能工化とは
多能工化の反対語の単能工化とは、1人の従業員が1つの業務にしか対応できない状態であることを指します。単能工化においては、業務負荷の偏りや生産性低下、柔軟性の欠如といった課題を生むリスクがあります。
多能工化のメリット
多能工化を進めることで、製造現場や組織全体に以下の効果が期待できます。
業務量の平準化
特定工程に人員が集中せず、作業負荷を分散できます。また、稼働状況や業務量を可視化した上でリソースを投下できるため、負担が均等化され業務量の平準化を促進します。
業務の可視化
多能工化を進めるためには誰がどんなスキルを持っているかを、そして業務に必要なスキルや手順、業務内容を可視化する必要があります。業務が可視化されることにより、欠員やイレギュラーな事態に対してもリソースを透過でき、作業の停止などのリスクを軽減できます。
生産性向上
多能工化の促進により、難易度の高い作業や稼働率の高い業務に優先してリソースを透過できるため生産性が向上します。また、複数の業務を担当できる人材が増えることで、ライン停止や遅延時の対応が迅速になります。
柔軟性の高い組織
多能工化によって一人の従業員が複数の業務を担当できるようになるため、組織の柔軟性が高まります。休暇や欠員時にも柔軟に業務を回せるため、経営リスクを低減できます。
チームワークの強化
さまざまな業務に取り組む状況が普通になるため、メンバー同士のコミュニケーションは常日ごろから生まれやすくなります。また、互いの業務を理解することで、協力体制や情報共有がスムーズになります。
多能工化のデメリット
一方で、多能工化には以下のような課題も存在します。
人材育成に時間がかかる
1人が新たなスキルや複数の業務について取得したり覚えたりする必要があるため、当然ながら時間とコストがかかります。そのため、多能工化を優先して行う従業員の特定が重要です。
評価制度の見直しが必要
多能工化に合わせて評価制度も柔軟に変更する必要があります。なぜなら、多能工化によって、新たに習得したスキルや担当した業務が正当に評価されなければ、多能工化した従業員のモチベーションは低下し、離職するリスクも高まるからです。多能工化を進める場合は評価制度の見直しが必要です。
従業員の負担が増える
複数業務を担当することにより、従業員の心理的・身体的負荷が高まるリスクが生じます。多能工化の対象となった従業員のフォローやケアをできる体制を構築する必要があります。
多能工化の育成や推進が必要とされる背景
多能工化が求められる背景には、現在の日本社会で急速に進んでいる、人口減少や高齢化の影響による労働人口の減少があります。多くの産業において、今後の働き手をどのように確保していくかが課題となっており、製造業も例外ではありません。
さらに製造業では、多品種少量生産を実現できる柔軟な生産体制が求められるようになっています。日本経済が躍進を遂げた高度経済成長期以降、長らく少品種多量生産が主流でしたが、消費者のニーズは年々、多様化・細分化しています。こうした変化に伴い、従業員一人が単一の仕事を行う「単能工」から脱却した、多能工化(マルチスキル化)の推進が重要視されているのです。
多能工化の推進や育成において、よくある課題
多能工化の必要性および重要性は十分に理解できていても、実際に社内で多能工の育成を進めるにはさまざまなハードルがあります。人材育成の課題に直面し、お困りの担当者の方も大勢いることでしょう。よくある課題としては、以下のようなケースが挙げられます。
①従業員にどのスキルを身に付けてもらうか、適切なスキルの選定ができない
職場全体で共有すべき技能や技術が明確になっていないため、育成対象者を選べないケースや、逆に従業員の保有スキルを把握できていないために、優先すべきスキルが判断できない場合があります。
②各スキルの評価やレベルが揃っていない
育成担当者によってスキルの判定基準が異なる、バラツキがあるなど、正確なスキルの判断ができていないケースがよくあります。このような中でマルチスキル化を実践しようとすると、働き手側のモチベーション低下がおきやすく、従業員の離反にもつながりかねません。
③計画の遅れに対応できない
通常業務に加えて、限られた時間で育成を行うため、進捗や成果の見える化はとても重要です。しかし、忙しさから今の状態が見える化できず、計画の遅れに気づけないケースがあります。
多能工化を推進する3つのポイント
さまざまな課題やハードルはあるものの、製造業は今後、多能工化を積極的に進めていかなければ、企業としての競争力が落ちてしまうことは明白です。それぞれの課題を、どのようにクリアしていけばよいのでしょうか。
①自社にとって、重要なスキルの選定をする
自社にとってどのスキルの優先度が高いか明確にするには、スキルの見える化が先決です。業務をフロー、工程、作業から棚卸しをして、必要なスキルを確認することからはじめます。次に、スキルマップのようなツールを使い、スキルの所有者を見える化します。その結果から不足/強化すべきスキルを選定することが一般的です。
②スキルの評価基準を明確にする
何をもって「スキルが身についた」と判断するのか、評価基準を明確にすることも非常に重要です。誰がどの程度の頻度で評価を行うのか、どんな基準に基づいて評価を行うのか、その客観性はどのように担保するのかなど、評価される側の従業員が納得してスキルアップに取り組める環境を整えていきます。
③常に現状把握ができる仕組みを作る
優先的に育成するスキルと、評価基準を明確にした後は、計画的な人材育成を継続的に行っていく必要があります。その中で最も重要なのは、きちんと計画に沿った育成が進んでいるかどうか、常に現状と進捗状況を経営・マネジメント側が把握できるようにしておくことです。育成を実行する前には、人材育成がどの段階まで進んでいるかを可視化できる仕組みを構築しておきたいところです。
多能工化推進に成功している企業の特徴
当社が支援してきた中で、多能工化を着実に進めている企業には、次のような特徴があります。
①経営側の強い意志とリーダーシップがある
多能工化を推進するための仕組みを整えるには、時間も労力もコストも多くかかります。また従来とは異なる新たな取り組みを組織全体で行う必要があるため、何よりも経営側の強い意志と、折れないリーダシップが求められます。現状の課題と向き合い、仕組みが自走するまで粘り強く進めることが、多能工化を実現する何よりの近道になるでしょう。
②現場を巻き込み、合意を得ながら進めている
多能工化の推進は、企業側だけではなく、働き手側にも大きな影響をもたらします。仕事内容はもちろん、評価やキャリアパスにも大きく関わってくるためです。従業員からの合意を得て、協力体制を作ることができないと、本当の意味での仕組み作りは進みません。現場の課題やニーズを捉え、対話を重ねて環境を整えていくことが重要です。
③現状を可視化できるシステムやプラットフォームを活用している
育成計画を着実に進行していくうえでボトルネックになりがちなのは、データ集計の手間など、管理の煩雑さです。システムやプラットフォームを利用し、常に最新の情報が可視化でき、誰もが必要な情報にすぐアクセスできる状態を構築しておくことができれば、現場での運用が継続的に実施できるようになります。
まとめ
多能工化は、「育成するスキルと対象者の選定」「スキル評価の統一」「育成進捗の管理」という3つの課題をクリアすることで、製造現場の柔軟性と生産性を大幅に向上させることができます。
スキル管理システムを活用すると、育成計画の可視化や評価の統一が容易になり、多能工化を確実に推進できます。
「多能工化」によって人手不足を解消するには?
「多能工化」で製造現場の人手不足と業務効率化を両立!
●多能工化のメリットをすぐに理解する
●多能工化を進める具体的なステップを確認する
●成功事例から自社の多能工育成計画を立てる
→すぐに資料を無料ダウンロードする