製造業の人材戦略とは? 人手不足解決の立て方と4つの重要領域を解説

国内市場の縮小と少子高齢化が進む現在、製造業では人手不足が常態化し、生産体制そのものが揺らいでいます。とくに、ベテランの従業員の退職による技能伝承の断絶や品質・安全リスクの高まりも深刻化している現状があります。
これらを根本から解決に導く鍵が、経営と直結した「人材戦略」です。人材戦略とは企業の計画や目標を達成させるための人材の最適化を目指す戦略であり、製造業においても効果的なものとして注目されています。
本記事では、人材戦略について、戦略の立て方や製造業で重要な理由、策定のポイントを交えて解説します。
人材戦略とは、企業の計画や目標を達成させるための人材の最適化を目指す戦略
「人材戦略」とは企業の経営計画やビジョン、事業目標を達成させるために、人材の最適化を目指す戦略のことです。具体的には、企業の根幹となる経営戦略やビジョンと連動して、人材の採用や配置、教育・育成などを戦略に盛り込んでいます。
人材戦略によって、自社内の人的リソースを常に最大化できるため、さまざまな変化を遂げる市場にも柔軟に対応し、業界内でも競争優位性を保つことが可能です。とくに、少子高齢化による労働人口が減少している日本においては、人材戦略は磐石な企業運営をおこなうための鍵となっています。

人材戦略と人事戦略、戦略人事との違いとは?
人材戦略と似た用語として「人事戦略」や「戦略人事」が存在しますが、目的やアプローチ方法、その範囲が異なります。
どの用語も意味は近いものの戦略の立案や実行を司る担当者であれば、明確にその違いを把握しておかなければなりません。ここでは、人材戦略と人事戦略、戦略人事との違いについて、解説します。
人事戦略は、経営計画やビジョンの達成を人事全般でアプローチしていく戦略
「人事戦略」は人事運用全般からアプローチし、企業の経営計画やビジョンの達成を図っていく戦略のことです。企業には「モノ・ヒト・コト・カネ」と経営に欠かせない4つの領域が存在しますが、人事戦略は「ヒト」の領域そのものを司る戦略です。
人材戦略との違いは「戦略の対象がどの領域なのか」という点にあります。人材戦略はあくまでも「人材」を中心とした採用や配置、教育・育成が対象です。一方で、人事戦略は人事領域全般を対象としており、人材戦略よりも広範な戦略になります。
戦略人事は、人的リソースの最大化を目指すための戦略
「戦略人事」は、経営に必要な人的リソースの最大化を目指すための戦略です。人事戦略と異なり、現状のリソースに着目した考え方です。そのため、人事戦略よりも詳細かつ具体性の高い戦略設計が求められます。
一方で、人材戦略との違いは「どの側面を重きに置いているのか」といった点です。人材戦略ではあくまでも「人材」に重きを置き、他方で戦略人事は経営の側面に重きを置いています。
人材戦略で実行する施策の4つの領域
人材戦略を実効性の高いものにするためには、以下の4つの領域を最適化する必要があります。
- 採用
- 配置・異動
- 教育・育成
- 代謝
この4つの領域は単独で機能させても効果が限定的であり、相互連携してはじめて効果的な人材戦略として機能します。
とくに、製造業では従業員の技術・技能伝承や多能工化などと密接に関わるため、戦略全体のバランスが損なわれると、生産性を大幅に低下させる要因になりかねません。
4つの領域ごとに戦略設計に必要なポイントを理解し、人材戦略全体で設計を組んでいくことが大切です。ここでは、人材戦略で実行する施策の4つの領域について解説します。
①採用
採用は、「どのような人を、どのように迎え入れるか」を決定する人材戦略の”入り口”です。入社した人材が自社のフィールドで活躍するために、採用の段階で可能な限り就職希望者の素質や自社との相性を判断しなければなりません。
効果的な採用を実現するためには、職務要件の明確化やビジョンの浸透が必要です。会社の将来像に合った人材像を描き、就職希望者にその魅力を分かりやすく伝えることで、ミスマッチを防げます。

②配置・異動
「配置・異動」は従業員の能力や経験、経歴にもとづいて適切な職務やプロジェクトに関わる重要な人材戦略の領域の1つです。人材戦略では従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるような人員配置が必要不可欠です。
効果的な配置・異動を実現させるためには、従業員個々の能力や経験を適切に把握しておくだけでなく、従業員のキャリア希望や将来のビジョンのヒアリングも欠かせません。企業と従業員の双方のニーズがマッチしてこそ、満足度の高い人材戦略として機能します。

③教育・育成
採用や配置・異動が適切に行えたとしても、従業員一人ひとりの能力を最大限に発揮できなければ人材戦略は成り立ちません。教育・育成は様々な方法を用いて、従業員が持つ能力を最大限に高めるための領域です。
しかし、教育や育成は実施したとしても即効性が高いわけではない点に注意が必要です。人材戦略として教育・育成を実施する際には、必ず長期的な視点を持つ必要があります。

④代謝
人材戦略における「代謝」とは、人材が組織のなかで役割を変えたり、会社の外へ旅立ったりする流れを整える領域です。代謝は単なる従業員の配置転換を指すだけでなく、業務をスムーズに進めるための「再教育」も含まれています。
製造業において人材戦略が重要な理由
日本が抱える少子高齢化の影響は製造業においても顕著です。具体的には、生産年齢人口の減少が加速しており、業界全体の人手不足が顕在化しています。経済産業省「2023年版 ものづくり白書」では企業(製造業)の約56.3%が、事業に影響を及ぼす社会情勢の変化を「人手不足」として挙げました(※)。
加えて、熟練技術者が他の従業員に技術や技能を伝承せずに定年退職してしまうケースも増えており、生産力の低下も著しいものとなっています。
このような背景から、製造業において従業員一人ひとりの生産性を高める戦略が欠かせません。ここでは、製造業において人材戦略が重要な理由について、以下3点を解説します。
- 人材を定着させる
- タレントマネジメントを浸透させる
- スキルマネジメントを浸透させる
(※)参考:経済産業省「2023年版 ものづくり白書」

①人材を定着させる
人材戦略によってキャリアパスや評価基準を早期に共有すると、従業員は将来像を描きやすくなります。また、人材戦略のなかで業務調整やワークライフバランスの充実を図れば、従業員への業務負荷を軽減でき、人材の定着率が高まります。
具体的には、メンター制度で相談しやすい環境を整えたり、業務改善の提案を評価に反映させる仕組みを加えたりすることが挙げられるでしょう。現場での意見を汲み取ることで、従業員一人ひとりの意欲を高められ、結果的に生産性や働きがいの向上を促進できます。
②タレントマネジメントを浸透させる
タレントマネジメントは、従業員一人ひとりが持つ知識やスキル、経験を企業側で管理する仕組みのことです。この仕組みが全社的に浸透できれば、従業員が最大限のパフォーマンスで業務に従事できる環境が整えられ、従業員のモチベーション向上や企業の生産力の強化につなげられます。
タレントマネジメントを活用するケースは増えており、経営戦略やビジョンの実現には必要不可欠な要素として考えられています。

③スキルマネジメントを浸透させる
昨今では従業員が持つ知識やスキル、経験に着目した「スキルマネジメント」が注目されています。スキルマネジメントとは、従業員の保有するスキルや経験を適切に管理することで技術・技能伝承や従業員の多能工化を促す、主に製造業で活用されている仕組みのことです。
スキルマネジメントでは部門やチームに必要なスキルを明確化し、教育制度と連動させることで、不足しているスキルを効率的に補えるようになります。また、従業員ごとのスキルの習得状況が可視化できるため、企業側からのフォローアップを実行しやすくなります。
製造業での人材戦略の立て方とは?
製造業で人材戦略を策定する際は、経営戦略と密接に結び付き、プロセスを段階的に進めることが重要です。
時間とコストを過小評価すると途中で戦略が頓挫し、現場の信頼を損ねる恐れがあります。そのため、人材戦略策定の際には、入念な現状分析と全社的な巻き込みを行い、現場の実情を踏まえながら計画を具体化することが求められます。
ここでは、製造業での人材戦略の立て方について、以下のプロセスで解説します。
- 経営戦略・ビジョンを明確にする
- 人材ポートフォリオを策定する
- 現状を把握する
- 人材戦略の目標を決める
- 人材戦略を設計する
①経営戦略・ビジョンを明確にする
まず、中期経営計画やビジョンを具体的に示し、人材戦略の方向性をはっきりさせる必要があります。市場環境やトレンドを踏まえて必要な要件を抽出し、組織全体で共有します。
加えて、ビジョンと人材像を明確にする際には、経営層だけでなく、全社的な巻き込みを行うことで従業員の共感を得ることが可能です。理念への腹落ちが深まることで、人材戦略の実行性が高められます。
②人材ポートフォリオを策定する
次に、経営戦略やビジョンの達成に必要な「人物像」の策定を行います。理想とする人物像が「どのような理念を掲げて、どのような能力を、どのような分野で、どのように発揮していくのか」といったポートフォリオを具体化していくステップです。
ポートフォリオの策定時は、自社の既存技能と将来的な需要を比較し、内部での教育・育成と外部の採用とのバランスを可視化することが大切です。なお、人材ポートフォリオに必要な定義付けは以下のようなものが挙げられます。
| 必要な人材の定義 | 積極的なリーダーシップが発揮できる人材専門性の高いスキルを常に発揮できる人材経営理念やビジョンを踏まえて、行動を起こせる人材 |
| 必要なスキルの定義 | 現場の実情を踏まえたマネジメントスキル組織の枠を超えて、さまざまな人材を巻き込めるコミュニケーション力職務に必要な高度かつ専門的なスキル |

③現状を把握する
自社の経営計画やビジョン、人材ポートフォリオが定まれば、現状の把握を行います。具体的には、組織体制や部門ごとの人材配置、人材の能力や経歴、キャリア希望などの情報をまとめていきます。
現状把握では、タレントマネジメントシステムやスキルマネジメントシステムを活用し、人材やスキルに関連するデータを一元的に管理することが理想です。

④人材戦略の目標を決める
現状の把握を終えれば、人材戦略の目標設定を決定しなければなりません。目標設定は定性的なものだけではなく、定量的なものを含めて設定すると、従業員に必要な施策が明瞭になります。
加えて、一定期間ごとのフィードバックのための指標も決めておくと、実行した戦略の評価や課題の洗い出しがスムーズに進められます。
⑤人材戦略を設計する
最後に、採用や育成、配置や代謝の領域ごとの人材戦略を設計します。それぞれの領域で実行する施策を時系列で配置し、「どのような施策を実施するのか、どのくらいの予算が必要か、どの程度の規模で実施するのか」などを確定します。
人材戦略の運用が始まれば、設定した目標に対する進捗状況の定期的な確認が必要です。また、人材戦略を運営するにあたって支障があれば、迅速に改善策を打てる仕組みも整備しておく必要があります。
このように設計・開始後もメンテナンスを行うことで、より精度の高い戦略を設計可能です。
人材戦略を策定する際のポイント
人材戦略は企業の競争力を高めるだけでなく、従業員一人ひとりのキャリア形成にも大きな影響を与えます。しかし、策定時に多面的視点を欠くと、特定層への負担集中やモチベーション低下を招き、戦略が逆効果になるリスクが生じます。このような事態を避けるためにも、人材戦略を策定する際には必要なポイントをおさえておくとよいでしょう。
最後に、人材戦略を策定する際のポイントを解説します。
- 多様性を重視する
- 人材データを活用する
- スキルデータを活用する
- スキルマネジメントを行う
① 多様性を重視する
近年はグローバル化の影響もあり、年齢や性別、国籍を超えたダイバーシティの考え方が日本においても浸透しつつあります。名立たる大企業もダイバーシティにおける多様性のある働き方の実現に注力しています。
多様性を重視した考え方は、固定観念を大きく変え、企業にとって創造性や競争力を高める要因となるでしょう。多様な視点が交わることで改善提案やイノベーションが生まれやすくなります。
②人材データを活用する
昨今では従業員一人ひとりの詳細な情報をまとめたタレントマネジメントの考え方が注目されています。
IT技術の進化もあり、細かな情報の統合だけでなく、AIによる将来予測や配置の最適化などの機能も活用可能です。また、蓄積した人材データをもとに、従業員一人ひとりに適した教育・育成を策定できます。
③スキルデータを活用する
近年では、従業員一人ひとりの知識やスキル、経験を1つのデータにまとめた「スキルデータ」に関するサービスが提供されています。
このスキルデータを活用すれば、企業は業務プロセスと連動したスキル基準を定義し、資格や学習履歴を一元的に管理可能です。また、データをもとに従業員のリスキリング計画を最適化し、教育制度の効果を最大化できます。
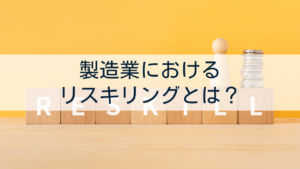
④スキルマネジメントを行う
「スキルマネジメント」は従業員個々のスキルを企業が把握し、従業員の適性に応じた事業運営が可能となる仕組みのことです。
スキルマネジメントは現在の状況だけでなく、将来的に喪失するスキルを可視化し、トラブルが生じないように先手を打った技術・技能伝承など様々な対策を講じることも可能にします。また、客観性の高いスキルデータをベースに従業員の適性に応じた人材配置が可能となるため、従業員の負担の軽減やモチベーションの向上も図れます。
企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!
「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!
●スキル管理のメリット
●スキル管理がうまくいかない理由
●スキル管理を成功させる3つのポイント

執筆者
スキルマネジメントMagazine編集部
スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者
スキルマネジメントMagazine編集部
スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

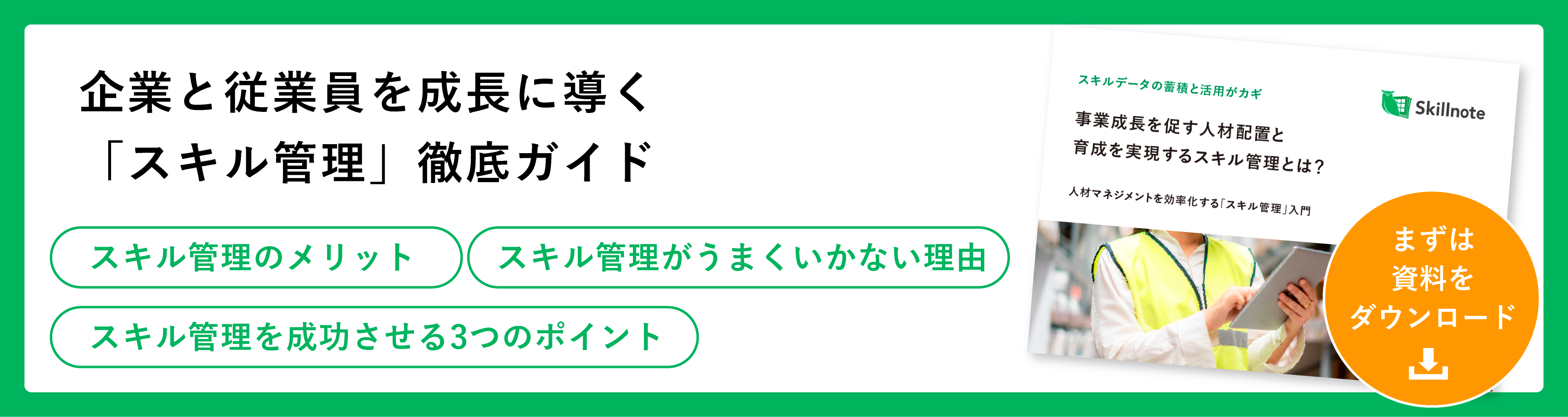





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)













