現場の安全確保に向けたスキルデータの活用

従業員の安全確保に日々取り組むなかで、安全衛生教育の受講状況や資格管理に苦労されている現場も多いのではないでしょうか。多忙な業務のなかでは、どうしても教育の受講漏れや資格の更新忘れが起こりがちです。従業員の安全確保対策の徹底には、スキルデータを活用した安全衛生教育の受講漏れや資格の失効・更新漏れの防止が効果的です。本記事では、教育の未受講者や資格の非保有者の検索から受講漏れを防ぐリマインドや教育計画の立案まで、従業員の安全確保に役立つスキルデータ活用法を解説します。
安全衛生教育を実行し従業員の安全を守ることは製造業の責務
労働安全衛生法の規定において、企業には労働災害が生じる危険が見込まれる業務に従事する全ての従業員に対して、講習や教育を継続的に実施することが求められています。企業に求められる講習や教育の例としては、事業場での安全衛生講習会や安全衛生大会、消火訓練や避難訓練、OJT、安全朝礼の実施などが挙げられます。また、これら以外にも、作業現場ごとにTBM(*)やKY活動(*)を行う必要があるほか、安全衛生パトロールを実施する義務、ヒヤリ・ハット事例や安全衛生対策を周知徹底する義務も課せられています。
このように多岐にわたる安全衛生教育を実行することは、企業が労働災害防止を徹底させ従業員の安全を守るための責務と言えます。最悪の場合、死傷者が発生する重大な事故にもつながり、ルールを守らない企業は重い刑事処分の対象にもなりえます。
もちろん、製造業の現場ではどの企業も従業員の安全確保に対して誠実に取り組んでいます。実際、目立つところに「○日間無事故達成」や「ヒヤリ・ハットの事例」の掲示をしている工場も少なくありません。一方で、多忙な業務のなかで、安全に対する思いが埋もれてしまっているのではないかと不安やもどかしさを感じている方も多いのではないでしょうか。下記ではその不安を解消へと導く、従業員の安全確保に役立てるスキルデータ活用法を説明します。

スキルデータのなかから教育未受講者・資格失効者を検索し、安全衛生教育計画を立案・実行
労災をなくすためには、次の活動が重要です。それは、スキルデータを活用して安全衛生教育の受講漏れを防止し、同時に、危険が見込まれる業務に関する資格の有効期限切れやその認定・更新教育の漏れを防ぐことです。この活動は、具体的には以下のステップを取ります。
- スキルデータのなかから該当する資格や教育の項目ごとに、従業員ごとの取得・受講状況や有効期限に関するデータを検索する
- 対象データが見つからない(失効している)、または失効が近い従業員を漏れなく抽出する
- 抽出された従業員を対象に育成計画を立て、進捗管理を行う
上記のステップを踏むことで対象者の教育漏れを防ぐことができます。さらに教育漏れを防ぐことに有効なのが、資格や教育の有効期限や教育開始期限の前後にメールなどで対象者にリマインドをかけることです。このとき、リマインドを一度で終わらせずに、何度も繰り返すことで受講漏れをゼロに近づけられます。
製造業の根幹を支える「守り」のスキルデータ活用
安全衛生教育に関するスキルデータ活用はいわば「守り」の活用です。人材育成やキャリア開発、配置や評価・報酬など人材マネジメントの領域における「攻め」のスキルデータ活用のような派手さはなく、表面的にも大きくプラスに働くわけではありません。
しかし、労働災害は一度起これば製造業の根幹を大きく揺るがすものです。労働災害を未然に防止するためにスキルデータを活用して、製品を生産し送り出すプロセスを平穏無事に進めましょう。

執筆者
スキルマネジメントMagazine編集部
スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者
スキルマネジメントMagazine編集部
スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

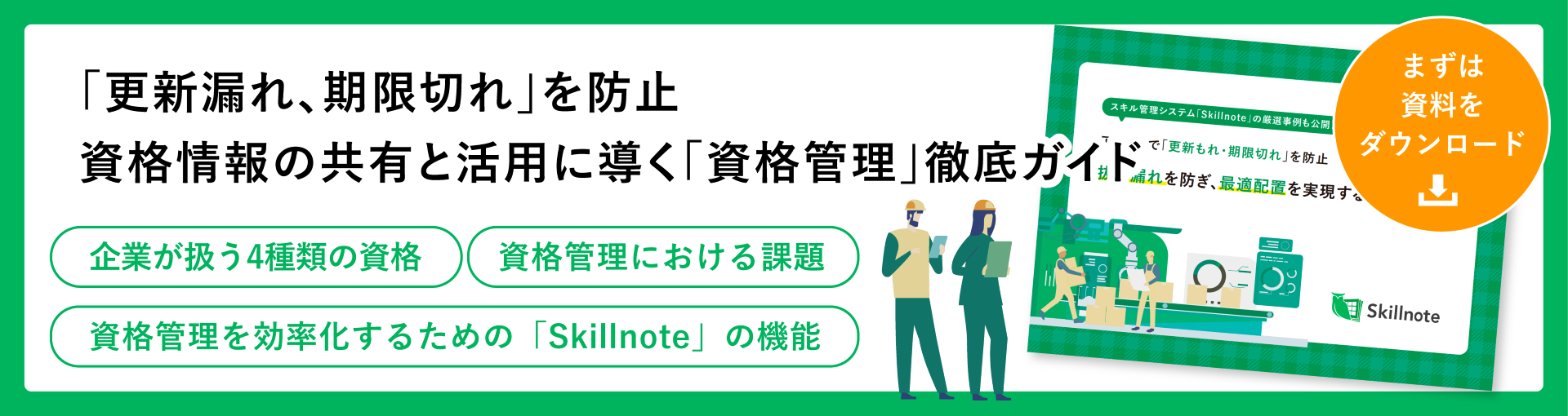





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)














