企業が安定的に成長するためには、「人材」への投資が必要不可欠です。従業員一人ひとりの業務経歴・スキル・資格といった属性情報を元に、効果的な人材マネジメントを行う必要があります。
しかし、従業員の属性情報を、紙ベースで管理するには膨大な時間が必要であり、かつ非効率です。そのため、従業員の属性情報をシステムのデータベース(=人材データベース)に登録し、活用する動きが広がっています。
本記事では、製造業を対象に人材データベースを構築する目的・管理すべき項目・データベース構築にあたってのポイントを中心に詳しく紹介します。
目次
人材データベースとは
「人材データベース」とは、従業員の属性情報をはじめとしたあらゆる情報をデータとしてまとめ、可視化したものです。属性情報の具体例としては、職務経歴や現在の担当業務および、保有しているスキルや資格、会社側からの人事評価などがあります。
人材データベースを構築する目的
人材データベースを構築する目的としては、以下の3点があります。
- 人事戦略に活かす
- タレントマネジメントを実践する
- スキル管理に活かす
それぞれの目的について詳しく解説します。
人事戦略に活かす
人材データベースは、人材に関するさまざまなデータを可視化します。そのため、現時点の人事課題や経営課題の分析にあたって、非常に有効な情報といえます。また、人材に関するデータを一元管理することで効率的に人材データの参照ができるため、人事評価や人材育成などのあらゆる人事施策を戦略的に進められるといったメリットがあります。
タレントマネジメントを実践する
従業員が持つ資格やスキルなどの属性情報を、経営資源の一つと認識し、従業員の適材適所な配置・人材育成・人材採用・離職防止といった施策に活用します。このように、従業員および製造現場の生産性最大化を図るための人材マネジメント手法を、タレントマネジメントと呼びます。
あわせて読みたい
製造業におけるタレントマネジメントとは? 目的やメリット、方法、スキル管理とスキルマップを解説
企業が経営目標を達成するためには、企業が成長することに貢献するスキルを持った人材を確保し、適切なポジションに配置することが重要です。現在、このような「タレントマネジメント」の考え方が注目を集め、実際に取り組む企業が増えています。
この記事では、タレントマネジメントの定義や概要、取り組むメリットや具体的な進め方について解説します。
スキル管理に活かす
少子高齢化やベテラン従業員の退職などによって、製造業では熟練技術者が減少しつつあります。そのため、ベテラン従業員が保有しているスキルやノウハウといった技術を、次世代に伝承することが喫緊の大きな課題です。技術伝承を効率的に行うためには、在籍する従業員がどのようなスキルを保有しているかを把握して、失われるリスクのあるスキルを特定して、計画的な対策を取る必要があります。
あわせて読みたい
スキル管理(スキルマネジメント)とは?目的・方法・スキルマップ活用のポイント
企業が事業を継続し存続し続けるためには、事業を行う際に必要なスキルを従業員が保有している必要があります。自社の従業員がどのようなスキルを保有しているか可視化するためには、スキル管理の取り組みが効果的です。
従業員の保有するスキルを適切に管理できれば大きな事業成果につながる可能性もあるため、スキル管理は企業にとって重要な取り組みと言えます。 この記事では、スキル管理の概要やスキル管理が重視される理由、スキル管理を行う際に重要な役割を担うスキルマップについて解説します。
人材データベースの構築にはシステムがおすすめ
先述のように、人材データベースを構築するためには従業員一人ひとりを対象に、膨大な項目の属性情報を管理する必要があります。
エクセルなどの表計算ソフトを使って人材データベースを構築することも可能ですが、それらを使った管理では、スキルデータの入力や更新、分析等の作業に大きな手間がかかります。また、ファイルの紛失や、属人化、最新のファイルが分からなくなるといったリスクも起こりやすくなります。
製造業においては、スキル管理システムの導入がおすすめです。製造業が管理すべきスキルは非常に複雑であり、細かなレベル基準が求められていますが、スキル管理システムはこれらの機能に対応しています。
あわせて読みたい
スキル管理システムとは?導入メリット・効果・活用シーン・種類をわかりやすく解説【導入事例あり】
いま、スキル管理が注目を集めています。しかし、現場ではスキルデータ(スキルや資格、経験、教育などの情報)をExcelなどで管理している場合も多く、データの一元管理や活用にまで手が回っていないことが多いかもしれません。
この記事では、スキル管理業務の効率化を図りたい方やスキル管理によって蓄積したデータを有効活用したい方に向けて、「スキル管理システム」を徹底解説していきます。タレントマネジメントシステムとの違いや、効果とメリット、選定ポイントも踏まえて解説しますので、ぜひご一読ください。
人材データベースの必須項目
人材データベースに登録しておくべき、必須項目を解説します。それは、以下の6つです。
- 基本属性
- 実績・履歴
- 勤怠
- スキル・資格
- マインド
- 職務内容
以下では、各項目について詳しく紹介します。
基本属性
基本属性とは、従業員の基本的な情報を指します。具体的には、「氏名」「年齢」「性別」「企業内の所属部署」「役職」「人事情報である等級」などがあります。
基本属性で登録すべき情報の多くは、個人情報に該当するため、厳格に管理をする必要がありますので、注意しましょう。
実績・履歴
これまでの「職務経歴」「学歴」「所属部署の履歴」「人事評価の履歴」「研修ごとの受講履歴」「業務成果」「受賞表彰歴」などの、自社に入社する前から現在に至るまでの実績や履歴を指します。
勤怠
従業員の勤怠状況も人材データベースで管理すべき項目です。具体的には、「残業時間」「職務場所への入室時間/退出時間」「早退回数」「欠勤回数および休暇日数」といった項目が含まれます。
スキル・資格
従業員が保有している「スキル」「スキルのレベル」「保有資格」などが対象です。製造業の現場では、特定のスキルや資格を保有していないと、作業ができないケースがあります。そのためスキルや資格の管理は製造業において、人員の適正配置や育成を実現するためにも非常に重要です。
マインド
人員の適正配置・人材教育にあたっては、従業員のマインドも考慮する必要があります。マインドには、「適性検査結果」「本人が希望するキャリア志向」「現在の業務に対しての満足度」「上司および人事担当者との面談履歴」「上司からの所感」といったものが含まれます。人事異動にあたっては、マインドも含めて適否を総合的に判断するとよいでしょう。
職務内容
職務内容とは、従業員一人ひとりに課せられている「ミッション」「業務目標」「業務内容」などを指します。職務内容をベースに、その職務内容の重要性や目標達成率などを考慮しながら、人事評価が行われることが多いです。そのため、職務内容のデータも人材データベースのなかでは、重要な項目となります。
製造業が「スキル」を重視した人材データベースを構築する必要性
ここでは、「スキル」を重視した人材データベースの構築が、なぜ製造業で求められているのか、その理由を解説します。
理由には、大きく以下の5つがあります。
- 組織におけるスキル総量の把握
- 事業運営に必要なスキルの維持・管理(スキル・技術の伝承)
- スキルの観点に立った最適配置の実現
- スキルの観点に立った育成計画の策定・実施
- 異動時のスキル情報の共有
それぞれの理由について、詳しくみていきましょう。
組織におけるスキル総量の把握
スキル管理をすることで、従業員の保有するスキルと企業が保有するスキルの総量の把握できます。その結果、自社が現在取り組んでいる事業や、今後取り組む予定のある事業を推進するにあたって必要となるスキルの有無が判断できます。このスキルの有無は、事業を行うべきか否かを判断するための前提条件の一つとなります。
事業運営に必要なスキルの維持・管理(スキル・技術の伝承)
自社の既存事業を継続していくためには、事業の継続に必要なスキルを保有している人材が必要不可欠です。
万が一、不足しているスキルがあれば、外部の企業に業務委託をしたり、必要なスキルを保有している人材を新たに採用したり、現在働いている従業員に教育を施すことによって、スキルを身に付けさせる必要があります。
スキルの観点に立った最適配置の実現
従業員一人ひとりが保有するスキルを一元管理し、さらに製造現場の責任者や人事担当者の間で共有できていれば、人員配置に課題がある事業所や部署はもちろんのこと、ほかの事業所や部署などの人材を含めて、「スキルデータ」という客観情報をベースにした人員の最適配置が可能となるというメリットがあります。
スキルの観点に立った育成計画の策定・実施
自社の従業員全員の保有スキル・スキルレベル・資格が把握できていれば、スキルの観点に立った人材育成計画を立案・推進することが可能となります。
スキルの観点に立った人材育成計画とは、具体的には「いつまでに」「どの程度のレベルで」「どのようなスキルを」「誰が」身に付ける必要があるかを整理したものです。
異動時のスキル情報の共有
自社の従業員のスキル管理を行っていれば、組織変更や人事異動の際に人事担当者個人の主観によらない客観的なスキル情報をベースにした異動が可能となります。
そもそも製造業における「スキル」とは
ここまで、「スキル」という言葉を使ってきましたが、あらためて製造業における「スキル」の定義をしておきましょう。
スキルとは、業務を遂行するにあたって必要な技能・知識を指します。製造業においては、製造現場で利用される機械の操作・製造プロセス・業界の専門知識・社内外のルールの理解や実行力まで「スキル」に含まれています。
また、問題解決能力・チームワーク・コミュニケーション能力などの、一般的なビジネススキルも製造業の「スキル」には含まれています。
製造業がスキルデータベースを構築するポイント
次に、製造業の企業がスキルデータベースを構築するにあたっての5つのポイントを紹介します。
- 必要なスキルの棚卸
- 業務経験・キャリア情報の管理
- 資格情報の管理(有資格者、資格の有効期限、取得タイミング)
- 研修履歴の可視化
- 項目ごとの権限設定
それぞれのポイントについて、下記で詳しく解説します。
必要なスキルの棚卸
自社で管理すべきスキルを明確にするためには、まずは業務に欠かせないスキルの棚卸をすることが重要です。棚卸したスキルは、新規事業の開発や既存事業の継続にも活用されるものであるため、細かく管理する必要があります。
業務経験・キャリア情報の管理
従業員一人ひとりが、これまでどのような業務を経験し、どのようなキャリアを歩んできたかは、スキル管理における重要な管理項目の一つです。
各従業員の業務経験・キャリアを把握することで、従業員に幅広い経験を積ませてジェネラリストとして育てるのか、または、特定の分野に絞って経験を積ませスペシャリストとして育てるのかといった、従業員のキャリア育成の判断にも活用できます。
資格情報の管理(有資格者、資格の有効期限、取得タイミング)
製造業の製造現場では、ある業務を担当もしくは監督するために、特定の資格が必要となる場合があります。そのため、有資格者・資格の有効期限・取得タイミングといったデータも把握しておくことが重要です。
それぞれの資格の有効期限と、資格の更新タイミングを通知できるようにスキル管理システムを活用すると更新忘れによる失効が起きないため、安定した生産が担保できるといったメリットがあります。
研修履歴の可視化
従業員が受講した社内外の研修受講履歴の管理や可視化をすることで、受講する研修が重複してしまうことが防げます。また、スキルレベル別に設定された研修の場合は、その研修の受講条件を満たしているか否かが明確に分かるといったメリットもあります。
項目ごとの権限設定
先述のように、人材データベースで管理する項目(とくに、基本情報)は、従業員のプライバシーに抵触する項目もあります。そのため、業務上必要最小限の参照可能者のみ参照できるように厳格な権限設定を行うことが必要不可欠です。
スキルデータベースを管理する方法
最後に、スキルデータベースを管理する方法を2つ解説します。
- スキルマップの活用
- スキル管理システムの活用(スキルマップのシステム化)
スキルマップの活用
スキルマップとは、スキル管理に必要な情報を集約し可視化したものです。つまり、従業員一人ひとりが保有しているスキルやそのレベルを可視化できるツールと言えます。スキルマップを活用することで、スキルデータベースの管理が効率的になります。
スキル管理システムの活用(スキルマップのシステム化)
上記で解説した、「スキルマップ」をシステム化した機能を持つツールが、スキル管理システムです。スキル管理システムを活用することで、製造現場の従業員一人ひとりのスキル管理が効率的に行え、スキルの入力や更新、期末評価などのスキル管理業務の工数削減が期待できます。
また、スキルや資格・人材教育などの情報の一元化と可視化も可能となり、従業員一人ひとりに合わせた「スキル」をベースにした人材育成計画の立案が可能になるといったメリットもあります。
企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!
「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!
●スキル管理のメリット
●スキル管理がうまくいかない理由
●スキル管理を成功させる3つのポイント
→詳しくはこちらから
- 人材データベースに必要な項目は?
-
人材データベースに登録しておくべき、必須項目を解説します。それは、以下の6つです。
- 基本属性
- 実績・履歴
- 勤怠
- スキル・資格
- マインド
- 職務内容
- 人材DBとは何ですか?
-
「人材データベース」とは、従業員の属性情報をはじめとしたあらゆる情報をデータとしてまとめ、可視化したものです。属性情報の具体例としては、職務経歴や現在の担当業務および、保有しているスキルや資格、会社側からの人事評価などがあります。


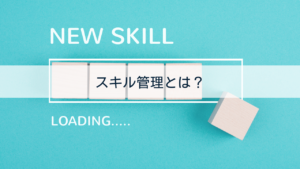



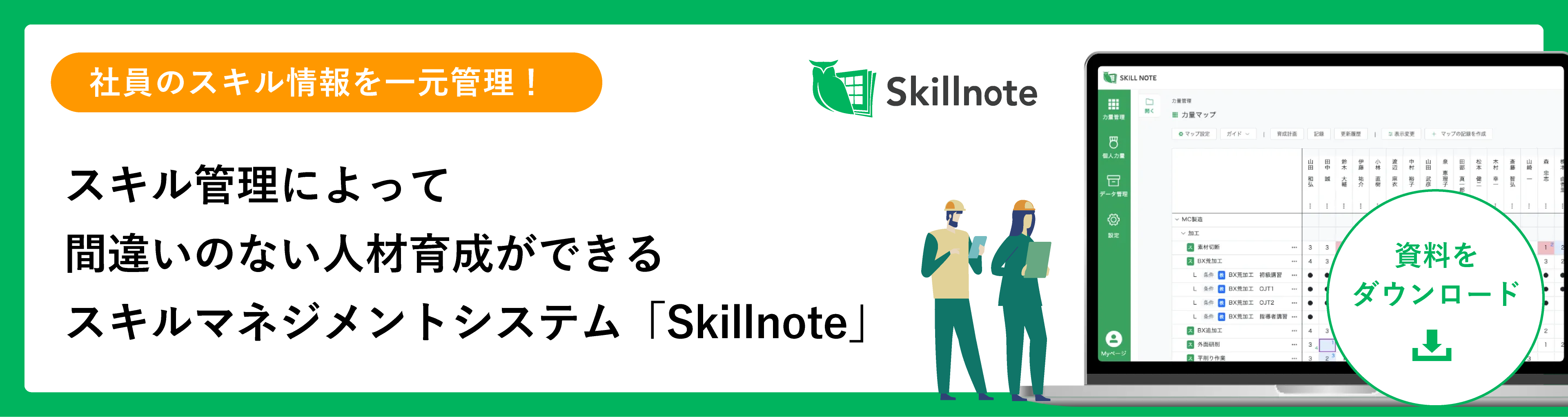
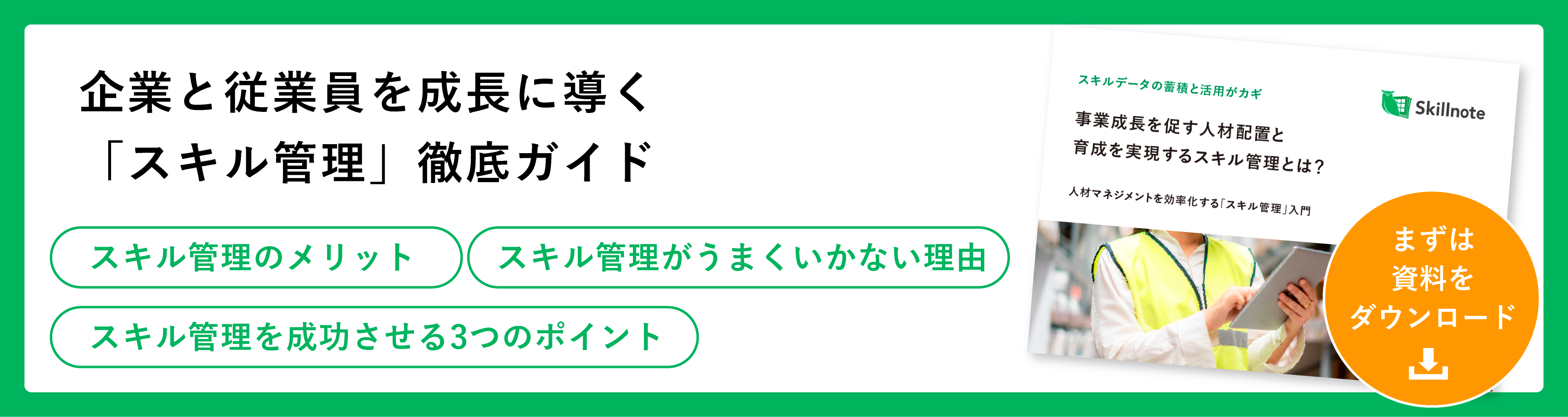
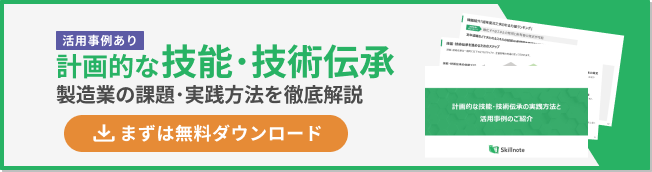
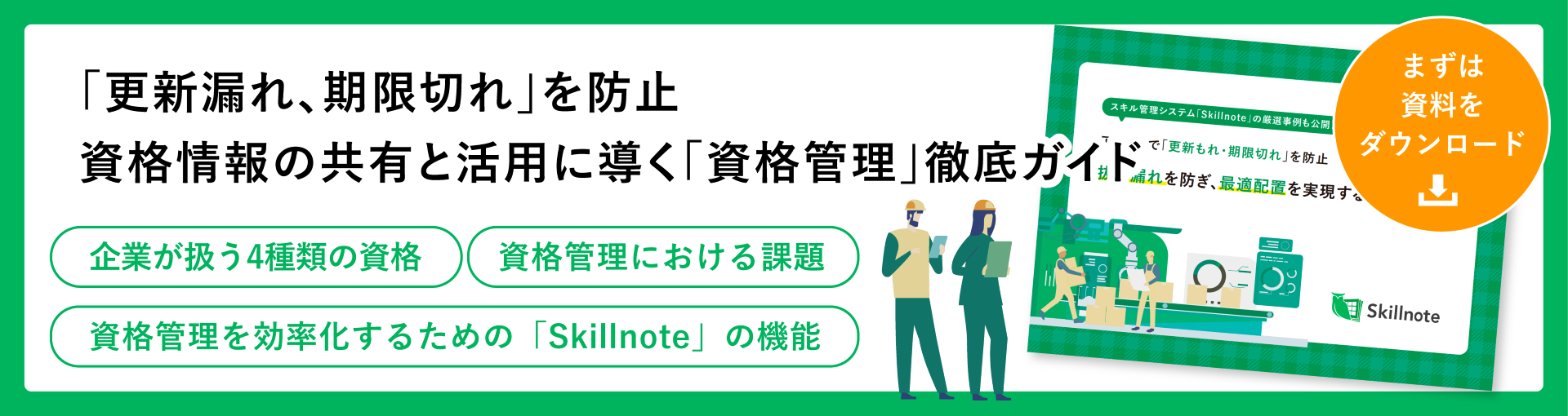
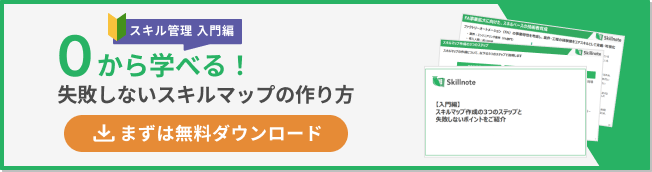





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)













