人員配置図とは?作り方と製造業で重要な3つの目的を解説

人員配置は企業の経営戦略やビジョン、事業目標を達成させるための「人材戦略」に欠かせない要素の1つです。とくに、製造業においては、技術・技能伝承や従業員の多能工化への対応が急務である背景から、人事面での戦略対応も求められています。
このような人員配置をよりスムーズに進めるために「人員配置図」というツールが存在します。人員配置図は表計算ソフトや文書作成ソフトで簡単に作成できるものの、より効果的な配置図を作成する場合には細かなデータの反映が欠かせません。また、作成にあたっては注意点やポイントもあるため、これから人員配置図を導入する場合には基本的な知識だけでなく、効果的に運用するために何が必要なのかを把握しておく必要があります。
本記事では、人員配置図について、目的や作り方、製造業で必要な理由もあわせて解説します。
人員配置図とは、組織内の構造や役割、業務内容などを1つの図にまとめたもの
「人員配置図」とは組織内の構造や管理体制、役割、従業員の配置や能力・スキルなどを1つの図にしたものです。基本的には企業の経営戦略やビジョン、事業目標を達成させるためのツールとして使われています。
人員配置図は従来の組織図や工程表と違い、リアルタイムのデータを重ね合わせられるため、たとえば翌日の欠員から半年先の育成計画までを一元的に管理することも可能です。また、生産ラインのレイアウトや、設備稼働率などのデータと照合すれば、より正確かつ効果的なデータでの検証も可能となります。
人員配置図自体は表計算ソフトで簡単に作成できる一方で、上記のような様々なデータを加えた人員配置図の作成を手助けするサービスも展開されています。

人員配置図を実行する3つの目的
人員配置図は企業の経営戦略やビジョン、事業目標の達成のために使用されるツールです。細かな点では、企業の業績向上や従業員の育成促進、離職防止といった目的を実現できます。
もし、これから人員配置図の導入を検討していれば、自社にとってどのような目的を達成したいかはあらかじめ整理しておくべきでしょう。ここでは、人員配置図を実行する3つの目的について、解説します。
- 業績を向上させる
- 人材育成を促進する
- 従業員の離職を防止する
①業績を向上させる
人員配置図は、作成することによって自社の組織内の構造や役割、従業員ごとの業務内容などを明瞭にできます。このことにより、各部門やチームの生産量や人員、全体リソースなどを可視化でき、部門・チームごとの過不足を整理することが可能です。
もし、過不足があった場合にはすぐ対応できるため、時間的な無駄を大きく省けます。加えて、生産性を意識した戦略・施策の実行も容易になるため、業績の向上を計りやすくなります。
②人材育成を促進する
人員配置図に従業員ごとの知識やスキル、経験などのデータを重ねることで、部門・チームの実情と従業員の状況を一元的に把握することが可能です。
これによって現場は不足している知識・スキルを瞬時に把握し、従業員の教育内容の優先度やレベル感を明確に設定できます。また、部門やチームで不足しているスキルの習得も促すことが可能です。

③従業員の離職を防止する
人員配置図では組織内の構造や役割以外にも、従業員ごとの勤務形態やキャリア希望、現状の負荷状況なども反映させられます。このようなデータを重ねあわせれば、過重労働の未然防止や適性に応じた人員配置の実現もしやすくなるでしょう。
結果、従業員の満足度を高められ、従業員の離職防止に貢献できる可能性が高まります。加えて、人員配置図に従業員のキャリア希望や勤務条件を紐づければ、意向を反映した配置や育成施策を設計しやすくなり、人事制度の運用精度も高まります。
人員配置図に必要な項目
人員配置図は、組織内のあらゆる人員に関する情報をまとめた図です。そのため、組織内の構造や各部門・チームの役割だけではなく、従業員一人ひとりの細かな情報が必要です。具体的には、以下のような項目が人員配置図を作成する際に必要となります。
- 組織階層
- 部署情報
- 部署ごとの従業員数
- 従業員の年齢や性別
- 従業員の雇用形態
- それぞれの業務内容
- 部署ごとに必要なスキル・資格情報
- 業績
- 異動・経験 ほか
このような細かな情報を1つの図にまとめることで、自社の人員配置における課題が細部まで明瞭にできます。経営層や人事担当者がこの図を確認すれば、人員配置の意思決定をスムーズに進められるでしょう。
人員配置図を作る際の5つのステップ
人員配置図の作成は表計算ソフトや文書ソフトなどを使えば、簡単に作成可能です。ただ、自社内のあらゆる人員情報を整理したい場合には、ある程度の段階を分けて作成する必要があります。
明瞭な人員配置図を作成するためのポイントはステップごとに存在するため、より効果的な配置図を作成するためにはポイントを把握しておく必要があります。ここでは、人員配置図を作る際のステップについて、以下のステップで解説します。
- 現状の人員配置の可視化
- 部門・チームごとの課題や能力の整理
- 人員配置の策定とシミュレーション
- 人員配置の実行
- 人員配置図の評価と課題の洗い出し
① 現状の人員配置の可視化
まず、自社内の人員配置の現状を可視化する必要があります。全体の組織図や配置状況、また従業員ごとの業績や就業状況、スキルや資格の保有状況などのデータを全て1つの図にまとめます。
データの一元化ができないと分析が断片化し、改善施策の優先順位が誤る可能性があるため慎重な対応が必要です。
② 部門・チームごとの課題や能力の整理
現状の人員配置が可視化できれば、その図をもとに組織・チームごとの課題や能力の整理を行います。可視化の際に詳細なデータを統合していれば、組織内での課題が発見しやすくなるでしょう。
整理の際には従業員の定量的なデータだけでなく、知識やスキル、キャリアの希望状況などを踏まえて整理しておくと、より従業員に沿った人員配置が叶います。
③人員配置の策定とシミュレーション
人員配置に関する現状のデータが揃えば、次に配置の策定です。
整理したことで判明した課題の解決を図るための配置を優先的に行います。その際、現状に対する評価だけではなく、将来的な予測もシミュレーションしておくとより効果的な人員配置が実現しやすくなります。
ただし、シミュレーションを行う際には「ただの予測」にならないよう、現場での検証や周辺従業員へのヒアリングを事前に実施しておくことがおすすめです。
④人員配置の実行
策定した配置のシミュレーションに問題がなければ、人員配置を実行します。人事異動のルールは各社によって異なりますが、一般的には以下の順番で周知させる流れになります。
- 通達
- 社内システムでの異動情報の公開
- 異動上の手続き
- 後任担当者への引き継ぎ
- 異動
⑤人員配置図の評価と課題の洗い出し
人員配置図は配置の実行だけではなく、その配置図の評価や課題の洗い出しをする必要があります。具体的には、配置したことによる業績上の変化や、従業員ごとの生産の変化などを検証します。加えて、成功事例を社内で共有できるようなテンプレート化も必要でしょう。この工程を繰り返すことによって、人員配置図の精度を高めていきます。
人員配置図を作成する場合は、サービスの利用がおすすめ!
人員配置図は複雑な作業が求められない点で、表計算ソフトや文書作成ソフトで簡易的なものが作成できます。しかし、簡易的な配置図の場合、高度なシミュレーションやリアルタイムでの配置判断ができません。
近年では、様々なデータを一元的に管理できる人員配置サービスが提供されています。このようなサービスを活用すれば、人員配置図に必要な工数を大幅に削減でき、また、事後的な効果検証もスムーズに実行可能です。
サービスは機能やサポート、予算などで幅広い種類が提供されています。しかし、自社に合うサービスは事業規模や予算、抱える課題によって異なるため、慎重かつ丁寧にサービスを選ぶ必要があります。

製造業に人材配置図が必要な理由とは?
製造業では、人手不足とベテラン技術者の高齢化によって、スキルの偏在化が深刻になっています。とくに、生産性が従業員の熟練度に左右されるライン構造では、適切な人材を適切な場所に配置できなければ、計画どおりの生産ができなくなり、最悪の場合には納期遅延や品質事故を招きかねません。 人員配置図はこのような課題に対しても有効に機能し、製造業全体が抱える課題を解消できる可能性があります。ここでは、製造業に人材配置図が必要な理由について、解説します。
- 技術・技能伝承が急がれる
- 多能工化が求められている
①技術・技能伝承が急がれる
製造業において従業員の高齢化が加速しており、現状の従業員が退職してしまった場合に必要な技術・技能が伝承されない可能性が危惧されています。
人員配置図では従業員一人ひとりの技術や技能を、組織全体で把握することが可能です。また、従業員の年齢や就業状況も一元的に管理できるため、優先度の高い技術や技能に対する伝承対応を迅速に行えます。人事の教育や育成制度と連動させていけば、より効果的な人事戦略が実現できます。

②多能工化が求められている
昨今の少子高齢化の加速に伴い、製造業においても人手不足が顕著になっています。このようななかで、事業の生産性を高めるためには、従業員の多能工化が欠かせません。
人員配置図では従業員のデータを技能段階で分けることも可能です。また、教育・育成制度と連動させれば、スキルの習得状況をリアルタイムで可視化でき、効果的な人員配置を実現できます。

人員配置図を使って配置を行う際の3つの注意点・ポイント
最後に、人員配置図を使って配置を行う際の注意点・ポイントについて、以下3点を解説します。
- 現在の人員配置の把握
- 人員の内容や希望の把握
- 人員配置後の効果の把握
① 現在の人員配置の把握
効果的な人員配置の実行には、現在の人員配置の状況や課題、各部門・チームのニーズなどを適切に把握しておく必要があります。把握には部門・チーム全体のデータだけでなく、従業員個々の詳細なデータも欠かせません。現在の人員配置を正しく理解できていなければ、見当違いの配置を実行してしまい、時間だけでなく、手間やコストも無駄にしてしまいます。
② 人員の内容や希望
人員配置図は「人員の配置を決めるためのツール」であることから、従業員一人ひとりの情報が欠かせません。具体的には、年齢や性別、雇用形態や業務内容、保有するスキルや資格情報が挙げられます。加えて、その従業員のキャリア希望や将来のビジョンなども把握しておく必要があります。キャリア希望を把握しておくことで、従業員の満足度を高められる最適な配置が可能です。
③ 人員配置後の効果の把握
人員配置図は配置が終われば役目を終えるわけではありません。配置後に「その人員配置が最適なものであったのか」の効果検証が必要です。効果検証では生産性や業績だけでなく、当人の業務に対する姿勢や意欲、また周辺メンバーとのコミュニケーションなども確認しておく必要があります。細かな点ではあるものの、一つひとつの要素を検証することで、適切な人員配置の仕組みをつくりやすくなります。
企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!
「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!
●スキル管理のメリット
●スキル管理がうまくいかない理由
●スキル管理を成功させる3つのポイント
- 人員配置図とは何ですか?
-
「人員配置図」とは組織内の構造や管理体制、役割、従業員の配置や能力・スキルなどを1つの図にしたものです。基本的には企業の経営戦略やビジョン、事業目標を達成させるためのツールとして使われています。
- 人員配置の考え方は?
-
人員配置とは、企業の経営目標達成に向けて、従業員をどこに配置するか決めることです。一人ひとりの能力を最大限に活かすため、各従業員が持つ専門知識、技術力、経験値、キャリアビジョンなどを総合的に評価し、それぞれの特性に最も適した職務や部署に配置を目指します。現時点での従業員の能力を活かすような人員配置はもちろん、将来的な人材育成の視点も含めた戦略的な配置計画の立案が重要となっています。

執筆者
スキルマネジメントMagazine編集部
スキルマネジメントMagazineは、製造業に関する基礎知識から人材育成・スキル可視化といったスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

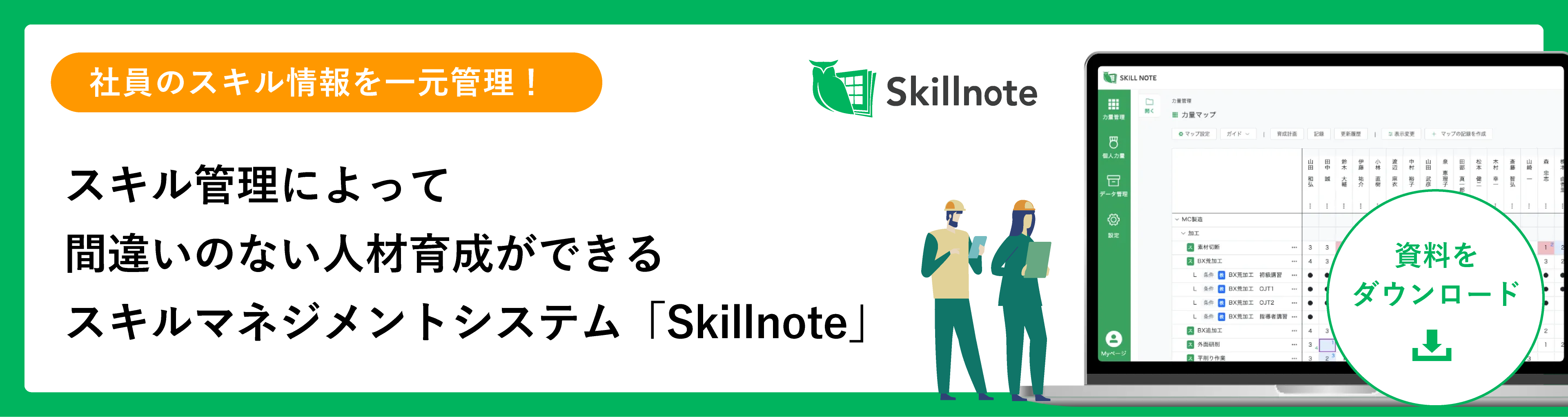





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)














