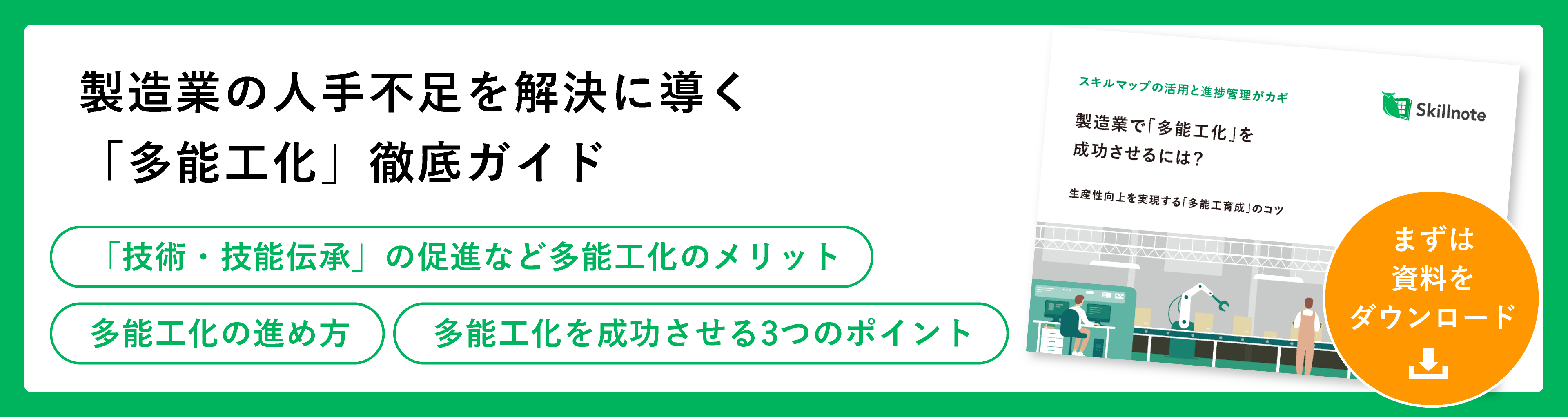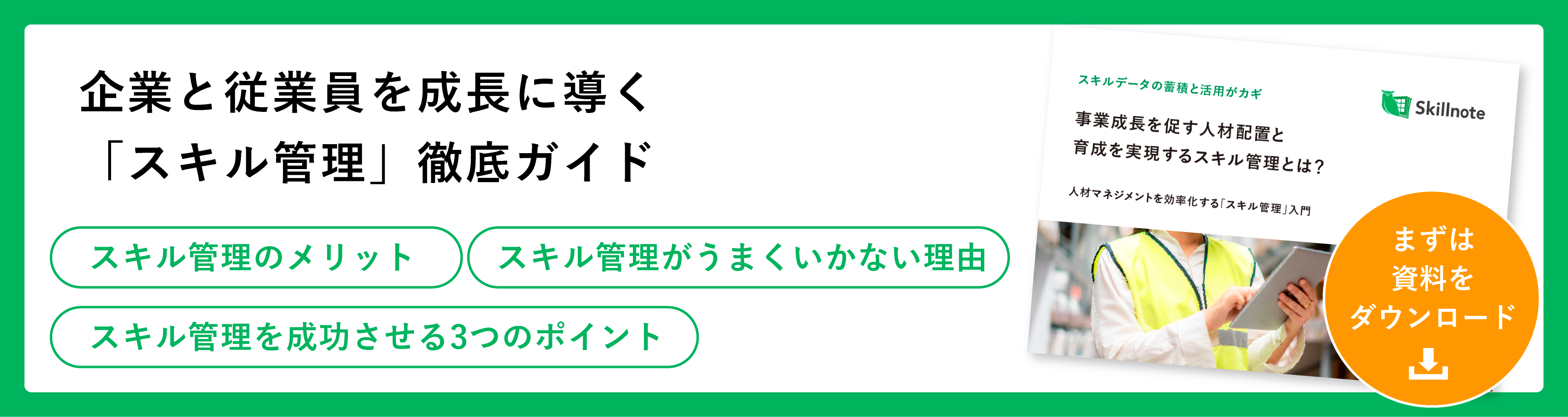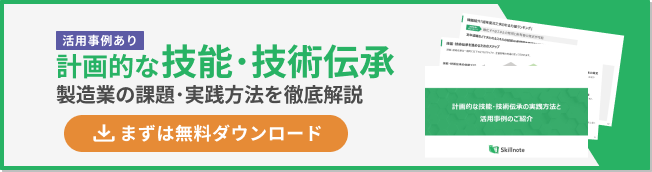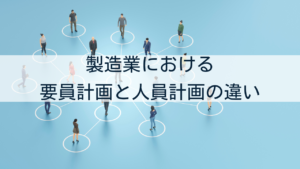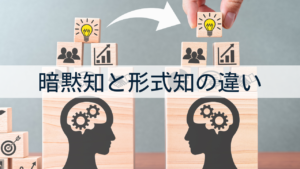製造業におけるタレントマネジメントとは? 目的やメリット、方法、スキル管理とスキルマップを解説

企業が経営目標を達成するためには、企業が成長することに貢献するスキルを持った人材を確保し、適切なポジションに配置することが重要です。近年製造業でも注目を集める「タレントマネジメント」は、従業員のスキルを可視化・育成し、組織力を高める仕組みです。本記事では、その目的やメリット、スキルマップとの関係、導入時の注意点までを詳しく解説します。
タレントマネジメントとは
タレントマネジメントとは、従業員が持つ「タレント(才能・資質、能力など)」を経営資源として捉え、従業員と所属する組織の成果を最大化することで、経営目標の達成を目指す人事手法のひとつです。
タレントマネジメントにおける具体的なアクションとしては、人材の採用や配置、育成、評価などが挙げられます。将来の見通しや企業の方向性、現在の企業及び個人の状況など、さまざまな情報を複合的に検討することで、大きな成果につなげていきます。
タレントマネジメントを進めるためには膨大な人材情報を収集・処理・分析する必要があります。そのため、タレントマネジメントを進めたくても企業の広い範囲に適用することは困難なのが実情でした。しかし、近年ではさまざまなHRテクノロジーの進化によって実現が現実的になったため、多くの企業が取り組みはじめています。
タレントマネジメントの定義や捉え方は、業界・企業によってさまざまです。そのため、解決したい課題にあわせて取り組むことが重要になります。ここでは、代表的なタレントマネジメントの定義を3つ紹介します。
SHRM(全米人材マネジメント協会)の定義
SHRM(米国の人材マネジメント協会)は、世界最大の会員数を誇るHRMプロフェッショナルのコミュニティです。SHRMでは、タレントマネジメントの定義を以下のように表現しています。
人材マネジメントのプロセス改善を通して、職場の生産性改善や人材の意欲を増進させることにより、優秀な人材の維持や能力開発を統合的、戦略的に進める取り組みやシステムを導入すること
参考:SHRM「Talent management: a key component of HR」
ASTD(米国人材開発機構)の定義
ASTD(米国の人材開発協会)は、多数の会員数を誇る人材開発のプロ集団です。ASTDでは、タレントマネジメントの定義を以下のように表現しています。
目標達成に必要な人材マネジメントを、職場風土、仕事に対する真剣な取り組み、能力開発、人材補強の4つの視点から実現しようとする短期的/長期的、ホリスティックな(全体の、関連した、繋がりを持った)取り組み
参考:米国人材開発協会ASTD『Research report 2008』
リクルートワークスの定義
リクルートワークスは、株式会社リクルートが運営する人と組織に関する研究機関で、中長期的な人材ビジネスの基礎研究や人材マネジメントにおける情報発信などを行っています。リクルートワークスでは、タレントマネジメントを以下のように定義しています。
タレントマネジメントとは、優秀な個人の能力とリーダーシップを最速で開花させることにより、ビジネスゴールの達成と、組織内におけるリーダーシップの総量を極大化させるための、本人・上位者・人事による成長促進プロセスである
出典:リクルートワークス「タレントマネジメントの本質」
タレントマネジメントの目的
企業がタレントマネジメントに取り組む大きな理由としては、以下の項目が挙げられます。
経営目標の実現
タレントマネジメントの最大の目標は、人事戦略とその施策によって自社の経営目標を実現することです。
具体的な経営目標としては、市場の拡大、新たな事業領域への進出、売上の拡大などが考えられます。これらを実現するための方策のひとつとして、タレントマネジメントが活用されています。

人材に関する課題の解消
タレントマネジメントによって経営目標を実現するためには、企業が抱えている人材に関する課題を解決する必要があります。
例えば、人材不足への対応や適切な教育環境の構築、多能工化など。これらの課題解決に取り組む際に、タレントマネジメントは効果を発揮します。
タレントマネジメントが必要とされる理由
タレントマネジメントが必要とされる背景には、企業が以下のような課題を抱えている点が挙げられます。
慢性的な人材不足
少子高齢化によって労働力人口が減少することで、新たな人材の確保が難しくなっています。さらに近年では、働き方の柔軟化や流動化が進行しており、職場を離れる選択をする機会が増えています。そのため、これまで以上に人材採用は難しさを増しています。
また、人材が不足している状況では、新たな人材を獲得できても十分な教育機会を提供する余裕がない場合も多いのが実情です。
タレントマネジメントを進めて必要なスキルを持った人材を重点的に育成することで、人材が不足している状況でも優秀人材が効率的に成果を出すことで企業を成長に導ける可能性があります。
環境の急激な変化
近年はデジタル技術の開発が進み、多くの企業が活用を進めています。IoTやDXなどがキーワードとして取り上げられており、企業を取り巻く環境には大きく、急激な変化が訪れています。
また、経済のグローバル化が進展したことで、海外企業との競争を勝ち抜く必要もあります。グローバルな市場競争は激化し続けていますが、厳しい競争環境においても成果を出して生き残れる組織を作り上げなければなりません。
そこで必要となるのがグローバル人材の育成です。グローバル人材の育成にはコストと時間を要するため、タレントマネジメントを進めて計画的に人材をプール・育成していくことが重要になります。
必要とされる人材の変化
市場環境の急激な変化により、企業と従業員に求められるスキルは大きく変化しています。
例えば、グローバル市場で勝ち抜くためには、海外の文化に精通し言語を操る人材が必要です。また、製品の複雑化により、従来とは異なる技術の組み合わせを保有している人材も必要となるでしょう。
このようなことからタレントマネジメントを推進することでこれまではいなかったタイプの人材を計画的に育成することが重要になります。育成計画や教育・研修方法も育成候補者にあわせて柔軟に変更していく必要があります。
働き方の多様化・柔軟化
近年は、働き方の多様化・柔軟化が進んでいます。例えば、コロナ禍をきっかけに定着したテレワークや男性への育児休暇取得奨励、時短勤務の拡大などがその代表例です。
働き方が多様化・柔軟化した職場では、重要な役割を担っていた人材が急に不在になってしまうことも多くなります。そこで、不在になった人材の仕事をカバーできるような体制をあらかじめ構築しておくことが重要になります。
タレントマネジメントを進めることで必要なスキルを可視化したり、効率的な育成計画を実行したりすることは働き方が多様化・柔軟化する現代の職場において必要不可欠であると言えます。
タレントマネジメントのメリット
タレントマネジメントに取り組むことで、以下のようなメリットが得られます。
必要人材の速やかな確保
タレントマネジメントでは企業が必要とする能力やスキルをあらかじめ特定して人材育成に取り組みます。計画的に人材育成を行うため、急に特定のスキルや能力を持った人材が必要になった場合でも速やかに必要人材を確保・アサインすることが可能となります。
そのため市場競争において、必要人材の不足を理由に競合他社に後れを取るリスクを大きく減じることができます。
従業員の満足度・エンゲージメント向上
タレントマネジメントの導入は、従業員の満足度向上にも貢献します。従業員一人ひとりの適性に合わせた育成計画や人材配置を可能にするからです。
このことにより企業と従業員とのエンゲージメントも強化され、結果的に従業員の離職リスクも低減させられます。
タレントマネジメントによってもたらされる従業員の満足度・エンゲージメント向上は人材の流出を防ぎ、経営目標を達成させるための重要な要素となるでしょう。
生産性の向上
タレントマネジメントによって必要な能力・スキルを持った人材の効果的な育成は、従業員ンの適材適所な配置を可能にします。
従業員の適材適所な配置を実現することは、従業員一人ひとりの生産性を向上させ、組織全体の能力を向上させることにつながります。
教育・育成の対象者
誰を教育・育成の対象者として選定するかは企業によってさまざまです。ここでは大きく2つの例を解説します。
1つ目は、幹部候補や特定人材の育成です。特定人材とは、海外で活躍する人材など企業が戦略上重要視する人材のことを指します。これらの対象に対しては、候補となる人材プールを作り、戦略的に育成を進めることが重要です。
2つ目は、全社員を対象とする育成です。タレントマネジメントシステムを活用することにより、人材情報を一元化、全従業員の人材情報を可視化することができます。これにより、これまでは難しかった全従業員を対象とした育成も進められるようになりました。
タレントマネジメントを進める際の流れ
タレントマネジメントには時間をかけて取り組む必要があります。以下の一連のサイクルを理解し、繰り返し続けていくことが重要です。
1.タレントマネジメントを行う目的の精査・明確化
まずは、タレントマネジメントを進めていくことでどのような経営目標を達成したいのか、人材に関するどのような課題を解決したいのかを明確にしましょう。
達成したい目的や解決したい課題は、企業ごとに異なります。他社の取り組みをそのまま真似しても十分な成果が得られないため、自社の状況を分析して目的の精査・明確化することが重要です。
目的を明確にしておくことで、仮にうまくいかないことがあった場合でも、そもそもの目的に戻ってやり直すことが可能となります。
2.人材情報の見える化(タレントマネジメントシステムの活用)
目的が明確にしたら、人材の状況を把握するために人材情報の見える化を進めます。
人材情報の見える化には、タレントマネジメントシステムの活用が効果的です。タレントマネジメントシステムを活用することで、全社的な人材情報の一元管理を実現し、育成計画の立案・実行も効率的に行えます。
なお、タレントマネジメントシステムにはさまざまな特徴を持ったものがあるため、自社の状況と目的に適したものを選定するとよいでしょう。

3.対象となる人材(タレント)の特定・プール化
経営人材や幹部候補などのタレントマネジメントを進める対象人材を、一元化した人材情報の中から特定する作業が必要です。
特定した人材は、目的別に参照できるようにプール化しておくといいでしょう。候補人材の情報にいつでもアクセスできる状態にしておくことで、育成計画や候補人材の変更にも柔軟に対応できます。
4.タレントプールに応じた採用・育成の計画
目的別のタレントプールを準備できたら、対象者ごとに育成計画を立案します。
タレントマネジメントを進めはじめた時点で目的実現のための適当な人材が社内にいない場合には、新たな育成計画や採用計画の立案も進めていく必要があります。立案した計画を実行するためには、経営層や候補人材との合意形成も事前に行っておく必要があります。
5.計画に基づいた人材採用と配置の推進
候補人材の育成計画を立案し、関係者との合意が完了したら、計画に基づいて人材採用や人員配置、教育を推進していきます。
採用や教育では、取り組み結果を確認するだけではなく過程を重視することも重要です。実際に育成計画を実行している候補人材に進捗状況を逐一確認するようにしましょう。
もし進行に不都合が生じていたり、当初の予定よりも遅れが生じていたりする場合には、状況に合わせて柔軟に軌道修正を行うことも大切です。
6.取り組み結果の評価
取り組みの結果が出たら、定量・定性の両方の観点で分析することが重要です。分析の際には過程も含めて確認することで、仮に十分な結果が得られなかった場合にも、目的の達成に向けて「何を」どのように」補完していく必要があるのかの示唆を得られます。
結果を分析する際には、短期的な成果に一喜一憂するのではなく、中長期的な観点から判断することを心がけましょう。
7.結果から改善点を抽出
一連の取り組みを評価した結果、計画段階で期待していたほどの成果を得られなかった場合にはどこを改善するべきか、検討する必要があります。
一方で満足のいく結果が得られた場合には改善に向けた取り組みは不要です。新たな取り組みに進むといいでしょう。
製造業でタレントマネジメントが必要とされる理由
以上のように様々な業界で必要性が増しているタレントマネジメントですが、製造業においてもその注目度は日に日に増しています。製造業がタレントマネジメントを必要とする理由として、下記の2点が挙げられます。
事業に必要なスキルや技術、技能の喪失の危機
少子高齢化による人手不足は日本社会全体の問題ですが、製造業もその例に漏れません。実際、2022年の「ものづくり白書」によると、製造業の56.3%が人手不足を課題に挙げています。熟練工の高齢化も深刻であり、高齢化した熟練工の退職により事業運営の根幹となるスキルや技術、技能の喪失が深刻化しています。そのため、スキル情報をベースにしたタレントマネジメントの実施は製造業にとって非常に重要と言えます。

消費者ニーズの多様化によって多能工や高スキル人材が必要
経済のグローバル化やIT技術の進展により、さまざまなコト(情報)やモノが溢れるようになったことで、消費者ニーズも実に多様化しました。その結果、かつての大量生産大量消費では多様化する消費者ニーズに対応できなくなりました。そのため、製造業において現在求められるのは高度なスキルを汎用化し、汎用化したスキルを複数持って業務に取り組める多能工や高スキル人材です。
このような理由からも、製造業特有の複雑なスキルを適切に管理しながら行えるタレントマネジメントの需要は高まっていると言えます。

スキル管理とは?
人手不足や消費者ニーズの多様化を背景に、昨今、製造業ではスキル管理が注目を集めています。スキル管理とは、「自社に所属する従業員が保有するスキルを可視化し、社内で共有できる情報として集約・活用できるようにすること」です。
なお、スキル管理によって社内で共有されたスキル情報は、新しいプロジェクトへのアサインや人員配置、成績評価、人事関連の業務などに活用できます。つまり、スキル管理とは、製造業に特有なスキル体系に適応したスキル情報をベースにした「タレントマネジメント」とも解釈ができます。
スキル管理の目的
スキル管理の目的には、大きく以下の5つがあります。それぞれ詳しい解説をお知りになりたい方は、下記の記事を参考にしてください。
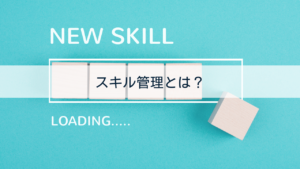
組織としてのスキル総量の把握
自社に所属する個人および社内の各組織がどのスキルをどの程度保有しているのかを把握でき、企業の持つスキル総量を把握します。
事業継続・事業開発に必要なスキルの維持・管理
既存事業を継続していくためには、継続に必要なスキルを保有していることが必要不可欠です。必要スキルの維持・管理・対策を行います。
スキル観点での最適な人材配置
従業員が保有するスキルを管理・共有して、監督する事業所や部署はもちろん、他事業所や他部署などの人材も含めて最適な人材配置を実現します。
従業員の育成計画の策定と推進
スキル管理を行うことで、企業は「いつまでに」「どの程度のレベルで」「どのようなスキルを」「誰が」身につける必要があるかを明らかにし、教育計画を立案・実施することができます。
異動・組織再編時のスムーズなスキル情報共有
組織再編や異動のタイミングで個人の主観によらない客観的なスキル情報をスムーズに共有して配置を実施できます。
従業員のモチベーション向上
組織や個人の持つ保有スキルを可視化して育成計画を立てておくことで、従業員のモチベーション向上につながります。
次世代へのスキル継承
可視化されたスキルの中から継承すべきスキル、そのスキルを次世代に向けて教える従業員、さらにはそのスキルを継承すべき従業員を選定することが簡単に行えます。
スキル管理の方法
スキル管理を効率的に実施するためには、スキルマップの活用がおすすめです。また、スキルマップを紙やエクセルではなくシステム化して運用するスキル管理システムを活用する企業も増えています。
スキルマップとは?
スキルマップとは、従業員が保有しているスキルやスキルレベルを可視化するツールのことです。その有用性からスキルマップは様々な企業で活用されています。しかし、企業によって管理するスキルのレベルや項目は多様であるため、自社に会ったスキルマップの運用が重要となります。なお、スキルマップの作り方を詳しく知りたい方には、下記の記事がおすすめです。

定期的に更新する
スキル情報をベースにスキル管理や人材配置、教育を行う場合には、スキルマップで管理するスキル情報や資格情報を常に最新の状態に更新しておく必要があります。しかし、スキル情報は膨大な量に及ぶため、情報更新にはそれなりの労力と時間が必要となります。そのため、スキルマップの更新タイミングは「年に1回」などと決定して、組織全体で更新をサポートする体制を整えましょう。
管理するスキルは業種・職種に応じて選定する
組織の全ての職種や業種のスキル情報を管理しようとすれば膨大な量に及び、効率的ではありません。そのため、スキルマップを活用する際には、職種や業種ごとに必要なスキルを選定して管理するようにしましょう。
スキル管理システムを活用する
スキル管理システムとは、従業員が保有するスキルを管理するシステムです。組織の持つ従業員のスキル情報(能力や経験、研修の受講歴や資格の取得歴)を一元管理できます。
また、紙やエクセルでは更新や入力、引き継ぎに大きな手間がかかりやすいスキルマップもシステム化して管理できます。スキル管理システムを活用すれば、スキルという定量情報を基盤にタレントマネジメント(計画的な人材育成計画の作成や、戦略的な人材配置)を確実性を高めて実現できます。
タレントマネジメントを導入する際の注意点
管理項目を選ぶ
全ての情報を管理しようとするとシステムが複雑化し、運用が滞ります。職種や目的に応じて「評価」「スキル」「キャリア希望」など、管理項目を明確に絞り込みましょう。
管理情報を常に最新の状態にする
タレントマネジメントは、データが正確であってこそ機能します。人事異動・資格更新・スキル取得などの情報を定期的に更新し、常に現状に即した判断ができる状態を維持することが重要です。
管理者(上司)の教育を行う
タレントマネジメントは現場マネージャーの理解と実践が欠かせません。部下のスキル把握・育成支援・面談スキルなど、上司教育も同時に進めることで定着率が高まります。
導入目的を全社に周知する
システム導入を目的化せず、「なぜ導入するのか」「どのような成果を期待するのか」を社内全体で共有することが成功の鍵です。目的が浸透していないと、現場の協力が得られず形骸化するリスクが高まります。
タレントマネジメントの成功事例
最後に、タレントマネジメントの成功事例を2つ紹介します。
日産自動車株式会社
日産自動車は、グローバル全体での人財最適化や日本人ビジネスリーダーの育成に向けて、
『和魂多才』という人財の定義を行い、新たな育成プログラムを開始しました。
具体的な内容としては、新卒採用の強化、入社後3年以降のタイミングでビジネスリーダー候補の発掘、入社5~7年目でビジネスリーダー候補の選別です。その後も育成を続け、40歳代でビジネスリーダーのポストに着任できる人財の育成を行っています。
候補人財の人選やアセスメント、育成計画、フォロースルーといったサイクルをうまく回していくことで、グローバルに活躍できる日本人ビジネスリーダーの育成を加速させています。
味の素株式会社
味の素株式会社は、2014年~2016年の中期経営計画で、2020年に世界の食品メーカーの中でトップ10入りを経営目標として設定しました。
これを実現するために、これまで行っていた国内を対象とした職能機軸の人財マネジメントから脱却し、国内外の優秀な人財の選定や育成、適材適所を考慮した配置を推進しました。
具体的には、ポジションごとに求められる成果や要件を明確に定義し、社内の管理職向けに広く公開しています。人財委員会を設置し、アクションプランの検討や育成プログラムの拡充を進めています。
タレントマネジメントの成功には「スキルの見える化」から
タレントマネジメントを定着させるには、まず「スキル体系の整備」が出発点です。スキルマップや人材データを活用して、現場に根ざした仕組みづくりを始めましょう。
●スキルマップの作り方を詳しく知りたい方はこちら
●「Skillnote」でできるスキル管理の詳細を見る
●スキルマネジメントの導入事例を見る
→「Skillnote」のサービス資料を無料ダウンロードする
- タレントマネジメントとは何ですか?
-
タレントマネジメントとは、従業員が持つ「タレント(才能・資質、能力など)」を経営資源として捉え、従業員と所属する組織の成果を最大化することで、経営目標の達成を目指す人事手法のひとつです。
タレントマネジメントにおける具体的なアクションとしては、人材の採用や配置、育成、評価などが挙げられます。将来の見通しや企業の方向性、現在の企業及び個人の状況など、さまざまな情報を複合的に検討することで、大きな成果につなげていきます。