製造業における人材マネジメントとは? なぜ必要か、成功のためのステップ、スキルマップの活用方法

近年の日本では、少子高齢化やグローバル化、IT・AI技術の進歩などのさまざまな要因から市場競争が激しさを極めています。企業が生き残るためには、企業全体が成長する他ありません。
このようななかで経営資源の一つである「ヒト」に着目した「人材マネジメント」が注目を集めています。この「人材マネジメント」とは、企業の経営戦略やビジョンの実現のために、人的リソースの管理と活用を行う戦略活動のことです。
ただ、人材マネジメントの実行は誰もが実行できるものではないため、どのような対応が必要なのかを知っておく必要があります。
本記事では、製造業における人材マネジメントについて、なぜ必要か、成功のためのステップ、スキルマップの活用方法などを解説します。
人材マネジメントとは、人的リソースの管理・活用を行う戦略活動のこと
「人材マネジメント」とは、企業の経営戦略やビジョンの実現のために、人的リソースの管理と活用を行う戦略活動のことです。
近年では、IT・AI技術の進化やグローバル化などによって、消費者ニーズは多様化しており、企業はそのニーズに適した商品やサービスを提供しなければなりません。このような市場や環境の大きな変化に対応するためには、企業自体が成長する必要があります。
人材マネジメントでは、企業の人事部門が行う業務だけではなく、企業全体の人的リソースに対して、従業員の採用や教育・育成はもちろんのこと、評価や報酬制度、配置などのフレームワークを一体的に取り扱った戦略を実行し、個々の従業員を成長させることで企業全体の成長を図れます。

人材マネジメントと類似する言葉・考え方との違いとは?
近年注目されている「人材マネジメント」には、類似する言葉や考え方がいくつか存在します。これらの言葉や考え方は、アプローチの方法や実行する施策などの内容が異なるものもあるため注意が必要です。
もし、これから自社で人材マネジメントの実施を検討しているならば、それぞれの言葉・考え方の意味や違いについて適切に理解しておきましょう。ここでは、人材マネジメントと類似する言葉・考え方について、解説します。
人事労務管理との違いは、マネジメント要素の有無
「人事労務管理」とは、従業員が働きやすくするための採用や配置、評価のような制度や、社内研修や福利厚生のような職場環境などを管理することです。
人材マネジメントとの違いは、マネジメント要素の有無です。人事労務管理では企業の人的リソースの管理に注目した考え方であり、人材マネジメントは管理と活用(マネジメント)の双方を融合させた考え方となります。ゴールとする目的の違いもあるため、実行する施策の内容やアプローチ方法が異なっています。
人的資源管理との違いは、学術的な考え方か、実務的な考え方なのか
「人的資源管理」とは、人的リソースを経営戦略に結びつけることによって採用や配置、評価や移動などの人事制度を管理する考え方です。1980年代に登場した理論であり、学術的な考え方が強い側面があります。
人材マネジメントとの違いは「人的リソースの管理・活用をどのようなアプローチで捉えるのか」という点にあるでしょう。あくまでも人的資源管理は学術から派生した考え方であるため、従業員の知識・スキルなどの管理を含んでいません。一方で、人材マネジメントでは、従業員の知識・スキルなども人的リソースの一部とし、包括的な管理・活用を必要としています。

ヒューマンキャピタルマネジメントと大きな違いはない
「ヒューマンキャピタルマネジメント(Human Capital Management)」とは、企業の経営戦略やビジョンの実現に必要な人的リソースを生み出す・育てるための投資戦略のことです。
人材マネジメントとの違いとして、それぞれの内容に大きな違いはありません。両者の違いは考え方のアプローチのみであり、企業の戦略として捉えるのか、投資の戦略として捉えるのかという点にあります。

人材マネジメントが注目される理由・背景
人材マネジメントは1980年代に登場した考え方でありますが、注目されたのはここ最近です(※)。これは人々の価値観や市場、環境の変化が大きく影響しています。
人材マネジメントが注目される理由のなかには、企業を成長させるためのヒントもあるでしょう。ここでは、人材マネジメントが注目される理由・背景について、以下の4点を解説します。
- 少子高齢化により加速する人材不足
- 人材やキャリア、働き方の多様化
- 市場競争・環境の激変
- グローバル人材の育成
(※)参考:労働政策研究・研修機構 上林 憲雄「人的資源管理論」
①少子高齢化により加速する人材不足
少子高齢化の加速にともなって、生産年齢人口の減少が想定されています。これは、国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集(2023)改訂版」で、2020年から2060年の40年間で2,431万人もの減少が予想されており(※)、このような背景からさまざまな企業で人手不足が懸念されています。
人材マネジメントでは従業員一人ひとりに注目した戦略を立てる考え方であり、移行によって人手不足に対する課題の解決も図れます。
(※)参考:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2023)改訂版」

②人材やキャリア、働き方の多様化
働き方改革や副業解禁、新型コロナウイルスなどの要因から、国内でも働き方やキャリア、人材への考え方が大きく変化していきました。このような変化からワークライフバランスが整った職場環境や、やりがいを持った働き方を望む従業員も増えつつあります。
企業はこのような従業員からのニーズに応える必要があり、多様化された価値観に適した人事戦略を実行しなければなりません。人材マネジメントは時代の潮流に適した戦略を企業ごとに策定・実行するものであり、注目される要因となっています。
③市場競争・環境の激変
IT・AI技術の進歩や、価値観の多様化、グローバル化などにともなって、消費者ニーズが大きく変化しています。このような変化にともなって市場競争が激化し、企業それぞれが商品やサービスの品質向上や低価格化、サポートの充実などを求められるようになりました。
このような背景もあり、企業が市場競争で優位に立つためには、消費者ニーズが実現できる知識・スキルを持った人材の採用や教育・育成が必要です。人材マネジメントに移行すれば、従業員一人ひとりの能力を最適化でき、組織全体が成長できる基盤が整います。
④グローバル人材の育成
近年ではグローバル化が加速しており、企業が成長を続ける上で世界市場への進出は必要不可欠な要素となりました。日本では総体的な人口減少が課題となっていることもあり、国内企業の海外における売上比率が高まっています。
ただ、世界市場に対応できる、いわゆる「グローバル人材」はまだまだ少ないのが現状です。このような課題を解決すべく、人材マネジメントの可能性が注目されています。
人材マネジメントの内容
人材マネジメントは大別すると、5つの分野が存在します。これらの分野は人事戦略を策定・実行する上で根幹となる分野です。そのため、それぞれの分野における人材マネジメントの位置付けを理解し、どのような施策や考え方が必要なのかを検討しなければなりません。
ここでは、人材マネジメントの内容について、以下の5つの分野を解説します。
- 採用
- 配置・異動
- 教育・育成
- 評価・報酬
- 入れ替え
① 採用
経営戦略やビジョンを実現する上で、自社の理想となる人材を採用することが必要です。採用は人材マネジメントにおいて「人事戦略の入口」と呼べる重要な要素であり、たとえば採用基準の明確化やダイバーシティを踏まえた採用制度の変化などの対応が求められます。
②配置・異動
企業の経営戦略やビジョンを実現するためには、人的リソースの最適化が必要不可欠です。それぞれの従業員が有する知識・スキルを活かせる部門・部署に配置し、個々のパフォーマンスを最大化させることで、総体的な企業成長につながります。
このような観点から、人材マネジメントにおいても配置・異動の分野は重要な要素として位置付けています。

③教育・育成
人的リソースは従業員個々の知識やスキル、経験がともなうことで、より最大化できる可能性を秘めています。そのため、それぞれが有する知識・スキルや抱える課題、将来的なキャリアビジョンなどを踏まえた従業員への教育・育成が必要不可欠です。
実施する内容は社内研修やOJTだけでなく、外部講師のセミナーや研修、またOff-JTなどの教育・育成制度の拡充が求められます。

④評価・報酬
能力が高い従業員であっても、活躍に見合った評価を行わなければ不満が募ってしまいます。このような不満はモチベーション低下につながり、業務への積極性が失われ、最悪の場合には自社から離れていくリスクを孕んでいます。 このような事態を避けるためにも、従業員一人ひとりの活躍を適正に評価する制度やその評価に対する報酬が必要です。
とは?-300x169.png)
⑤入れ替え
パフォーマンスやモチベーションの低い従業員は、企業全体にとって人的リソースを無駄にしてしまう要因になりかねません。このようなことから従業員を採用で増やすだけではなく、経営状況によっては減らすことも考慮しなくてはなりません。
人材マネジメントを実現するためのステップ
人材マネジメントの実現には、段階的な準備が必要です。急な人材マネジメントへの移行は組織全体の負担となり、経営戦略やビジョンの実現の弊害になりかねません。
このようなことから自社事業の状況やタイミングを適切に見極め、丁寧かつ慎重に人材マネジメントへの移行対応が求められます。
ここでは、人材マネジメントを実現するためのステップについて、以下の流れで解説します。
- 目標達成の人的リソースの明確化
- 現状における人的リソースの可視化
- 人材マネジメントの課題整理
- 戦略の実行
①目標達成の人的リソースの明確化
そもそも企業の人事には、採用や教育・育成、配置や異動、評価などのさまざまな分野が存在します。 それぞれの分野の業務を計画的に実行するためには、具体的な目標設定が必要です。自社にとって「経営戦略やビジョンを実現するために必要な人的リソースとはどのようなものなのか」を明確化する必要があるのです。
②現状における人的リソースの可視化
人材マネジメントの具体的な目標設定を終えれば、次は現状の把握が必要です。人材マネジメントにおいては、以下のような点を把握しなければなりません。
- 自社の人的リソースがどれくらいあるのか
- どのような知識・スキルを有しているか
- 足りないものは何か など
上記のような現状の把握には、従業員の知識やスキルなどを一元管理すると分かりやすくなります。近年では「スキル管理」の考え方も有効な手段として注目されているため、これを人材マネジメントを実現する際に活用するとよいでしょう。
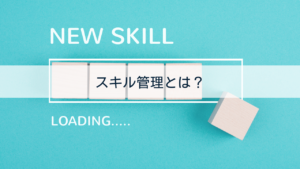
② 人材マネジメントの課題整理
現状の把握ができれば、人材マネジメントに必要な要素を洗い出しましょう。とくに、自社が抱える人事面での課題の可視化は重要です。 目標達成に必要な人的リソースの明確化や現状の可視化を行っていれば、課題はスムーズに整理できます。どのような課題があり、理想と現状ではどういうギャップが生じているかを把握しましょう。 なお、洗い出した課題は課題の大きさや解決に要する期間なども合わせて整理しておくと、優先順位が付けやすくなります。
④戦略の実行
目標の明確化や課題の整理を終えれば、いよいよ人材マネジメントにおける戦略の実行です。 人材マネジメントは中長期的な視野に立った戦略が多いため、短期的な結果に囚われないようにしましょう。また、採用や配置・異動、教育・育成、評価・報酬、入れ替えの各分野で戦略が異なっているため、それぞれでPDCAサイクルを意識して回しましょう。
製造業における人材マネジメントの必要性
人材マネジメントは全ての業種・業界で活用できるものです。なかでも、製造業は、人手不足やスキルの喪失など多くの課題を抱えていることから、人材マネジメントへの移行は効果的といえます。ここでは、製造業における人材マネジメントの必要性について解説します。
事業運営に必要なスキル・技術・技能の喪失の危機
製造業において人手不足は大きな懸念材料です。経済産業省の「2022年版 ものづくり白書」によれば、製造業を営む事業者のうち56.3%もの事業者が人手不足を懸念点として挙げています(※)。
また、近年では、高齢化による熟練技術者の退職が相次いでおり、事業の根幹となるスキルが承継できないことによって倒産を余儀なくされる企業も少なくありません。
このように、製造業においても少子高齢化による影響を受け、人的リソースの不足やスキルの喪失が課題となっています。人材マネジメントは、このような課題を解決する手段として注目を集めています。
(※)参考:経済産業省「2022年版ものづくり白書」
消費者ニーズの多様化=高スキル人材の付加価値
近年では、IT・AI技術の進化やグローバル化にともなって、さまざまなコト(情報)やモノが溢れ、消費者が自分の望む商品・サービスを手にすることが容易となりました。他方、品質の向上や低価格の実現、これまでになかった機能・サービスの導入など、消費者が企業に求める要求は厳しさを増しています。 このような背景もあり、製造業では高度かつ専門的なスキルの汎用化が求められています。このような課題を解決するための人事戦略として、人材マネジメントは注目されています。

スキル管理とは?
昨今では、従業員一人ひとりのスキルを管理する「スキル管理」という考え方が注目されています。この「スキル管理」とは、自社の従業員が保有する技術やスキルを社内でデータとして共有して、スキルデータをベースに人材マネジメントを行うことです。
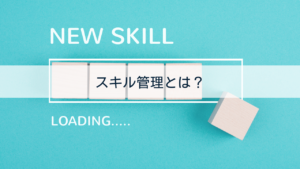
スキル管理の目的・背景
「スキル」は従業員一人ひとりによって保有する内容やレベルが異なります。スキル管理はこのような個人が有する技術やスキルを一元管理します。ここでは、スキル管理の目的・背景について、解説します。
① スキルの把握
製造業が事業をスムーズに運営するためには、組織全体が抱えるスキルの把握が重要になります。スキル管理では従業員それぞれが有する技術・スキルが、事業にどのような影響を与え、どのように機能しているかを可視化します。
②スキルの維持管理
事業を運営するにあたって、業務ごとにどのようなスキルが必要なのかを知っておけば、人的リソースを最大限活用できます。 スキル管理では事業ごとに必要なスキルを洗い出します。また、従業員ごとのスキルの保有状況を簡単に把握できるため、人員配置や異動、応援などを戦略的に行えます。
③スキルに応じた人材配置
適切な人材配置は、円滑な事業運営を進めるにあたって必要不可欠なポイントです。
もしスキル管理を行っていなければ、人材配置を考える際に上長の記憶に頼りがちになり、スキルデータに基づいた人材配置は実現しにくくなります。その結果、従業員のモチベーションが低下したり、事業運営が非効率になったりしてしまいます。
③ スキルの観点に立った育成
教育・育成によって従業員は新たなスキルを獲得したり、既に持っているスキルのレベルを高めたりすることができます。しかし、そもそも企業が事業に必要なスキルや、従業員が保有しているスキルを把握できていなければ、戦略的な教育・育成は実行できません。
スキル管理では企業保有する全てのスキルが可視化できるため、教育・育成においても効果的な施策が実行できるようになります。
④ 次世代へのスキル継承
製造業にとってとくに問題となる点が「スキルの喪失」です。高齢化による熟練社員の退職が相次いでおり、事業の根幹となるスキルが承継できていない企業も少なくありません。 スキル管理を行えば将来的に喪失するスキルをシミュレーションできるため、事業運営に不可欠なスキルを計画的に承継できる施策が確実に実行できるようになります。
スキル管理の方法
スキル管理の方法はさまざまありますが、近年ではツールやシステムを活用した方法が注目されています。ツールやシステムでは定額的なコストが発生する代わりに、簡単な操作や準備でスキル管理をスムーズに進められるメリットがあります。ここでは、スキルマップの作り方とスキル管理システムについて解説します。
① スキルマップの活用
スキルマップとは「業務で必要なスキルを洗い出し、従業員一人ひとりが保有する技術やスキルを一覧にした表」です。スキルマップによって、スキルをデータとして一元管理できます。
スキルマップの活用によって、企業は経営陣から従業員までの誰もが自社のスキルの保有状況を把握できるようになります。経営陣や管理職は組織やチーム全体のスキル総量を把握した上で事業戦略を策定でき、従業員は自身やチームメンバーが有するスキルを把握しながら業務を進めることができます。
② スキル管理システムの活用
近年では、スキル管理をスムーズに進めるためにスキル管理システムが提供されています。スキル管理システムとは、企業が保有するスキルを従業員ごとに細かく可視化し、教育や研修、配置などに活用するシステムのことです。 スキル管理システムには、スキルマップ運営の効率化やスキルデータをベースにした人材配置の最適化などさまざまなメリットがあります。たとえば、生産ラインごとに配置された従業員の保有するスキルを可視化し、スキルの不足しているラインに適切な作業応援の人材を送ることができます。
企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!
「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現! ●スキル管理のメリット ●スキル管理がうまくいかない理由 ●スキル管理を成功させる3つのポイント →詳しくはこちらから
- 人材マネジメントとは?
-
「人材マネジメント」とは、企業の経営戦略やビジョンの実現のために、人的リソースの管理と活用を行う戦略活動のことです。
近年では、IT・AI技術の進化やグローバル化などによって、消費者ニーズは多様化しており、企業はそのニーズに適した商品やサービスを提供しなければなりません。このような市場や環境の大きな変化に対応するためには、企業自体が成長する必要があります。
人材マネジメントでは、企業の人事部門が行う業務だけではなく、企業全体の人的リソースに対して、従業員の採用や教育・育成はもちろんのこと、評価や報酬制度、配置などのフレームワークを一体的に取り扱った戦略を実行し、個々の従業員を成長させることで企業全体の成長を図れます。


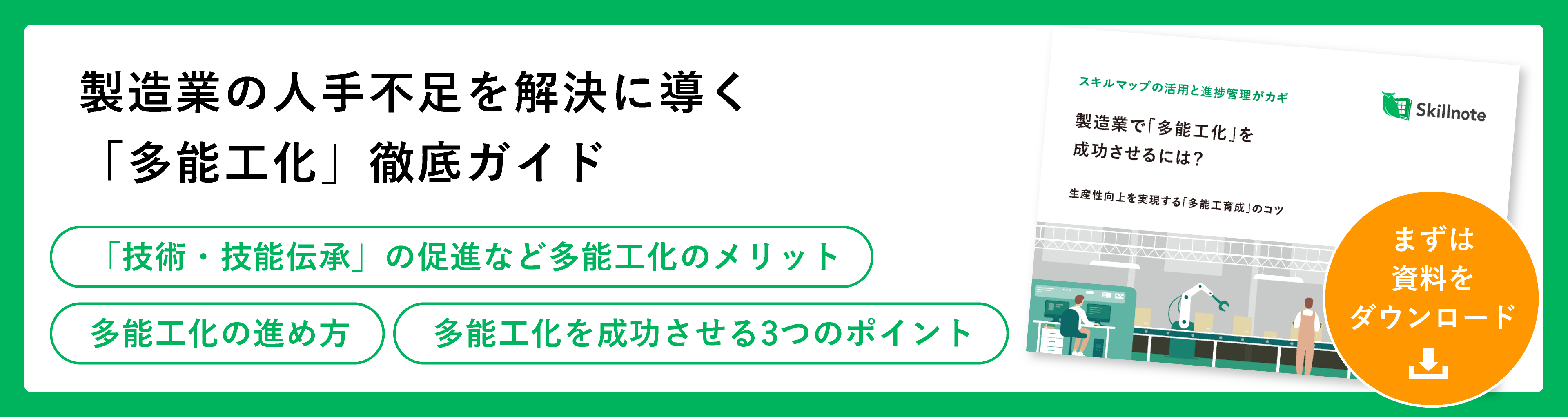
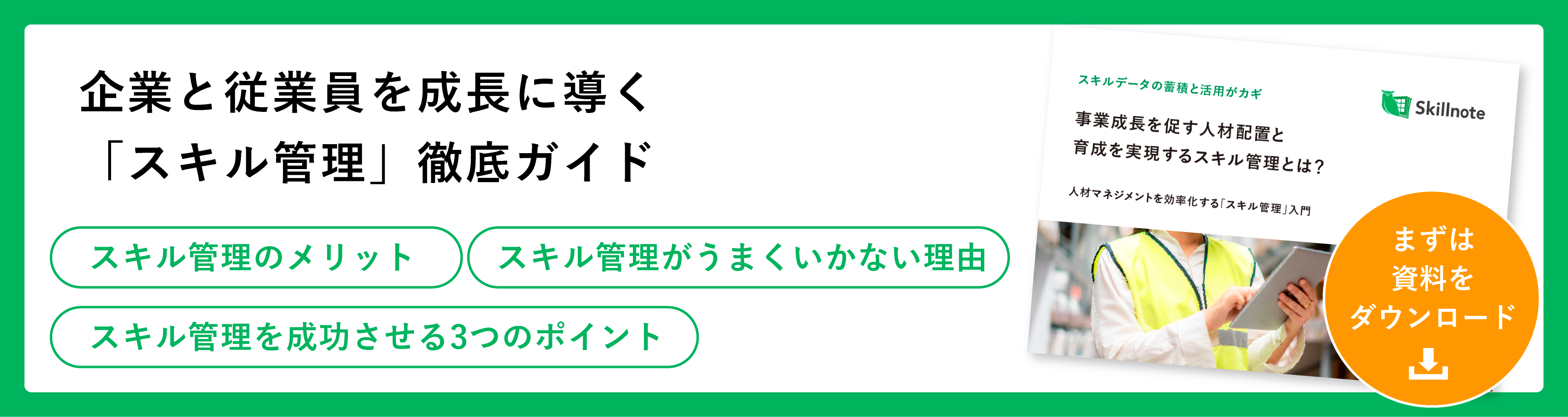
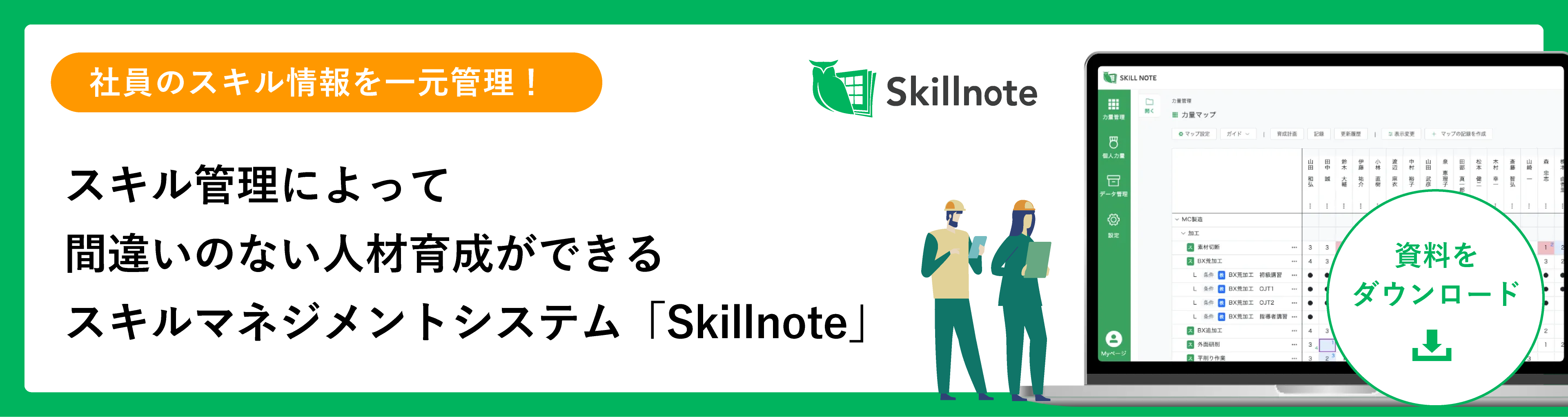
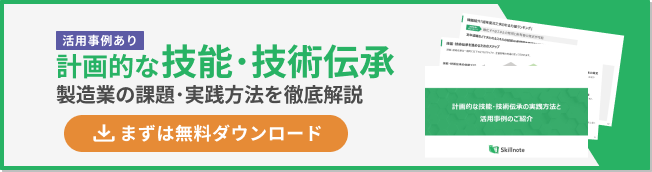
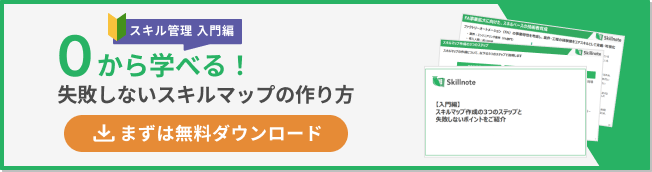
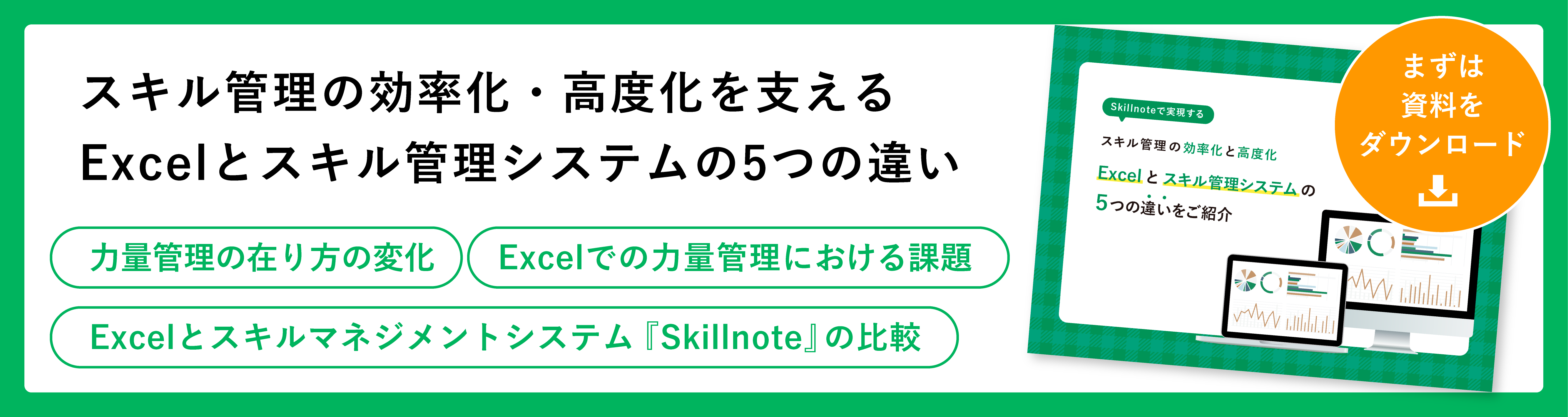





DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)














