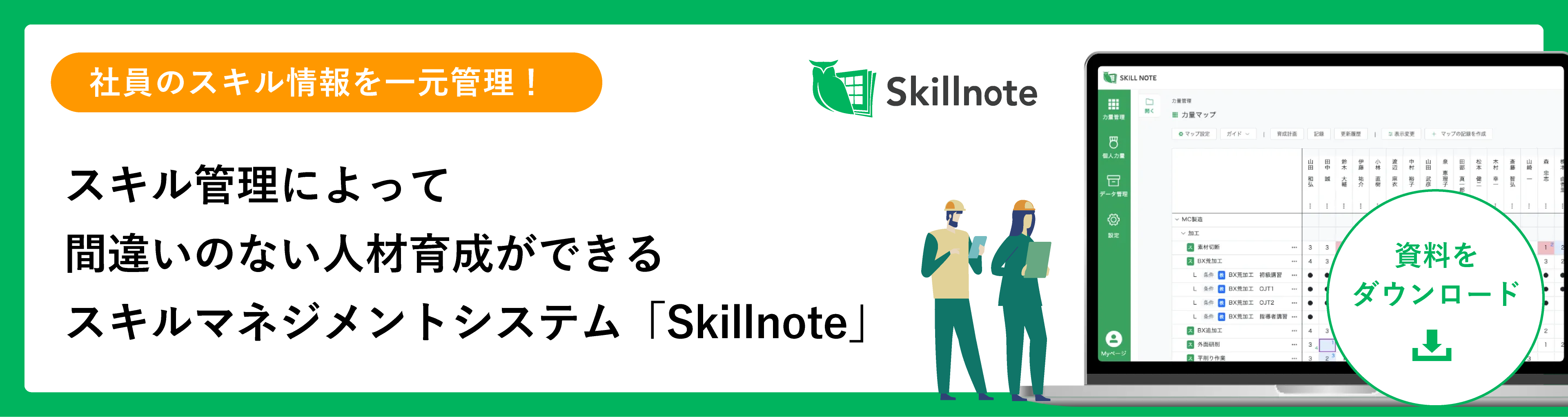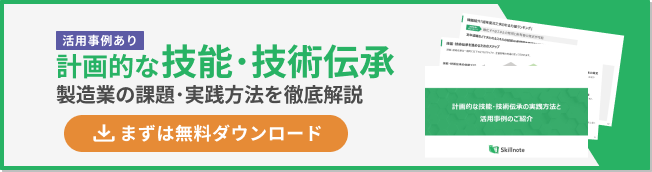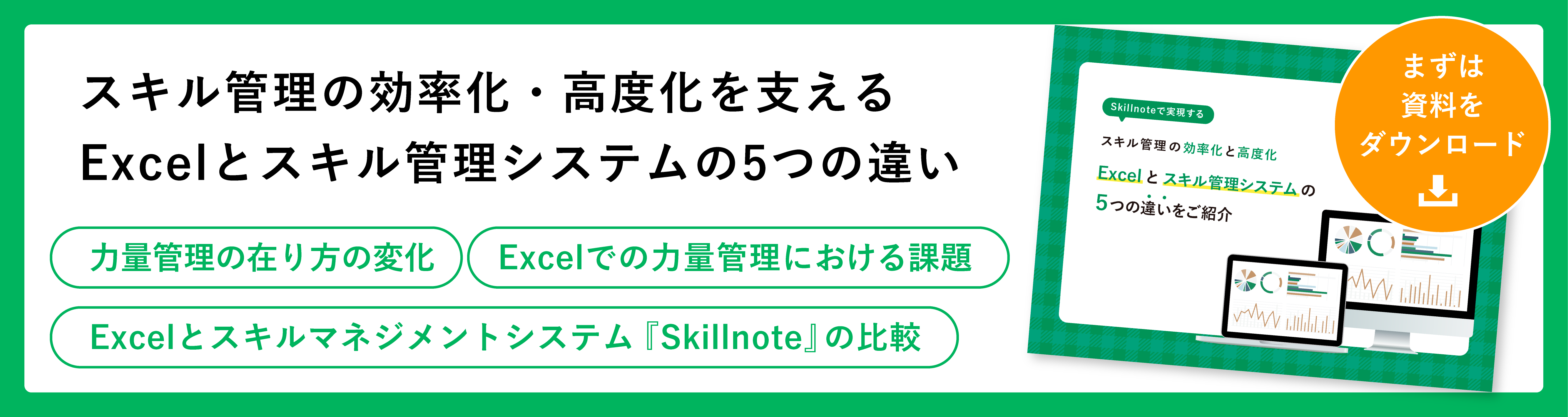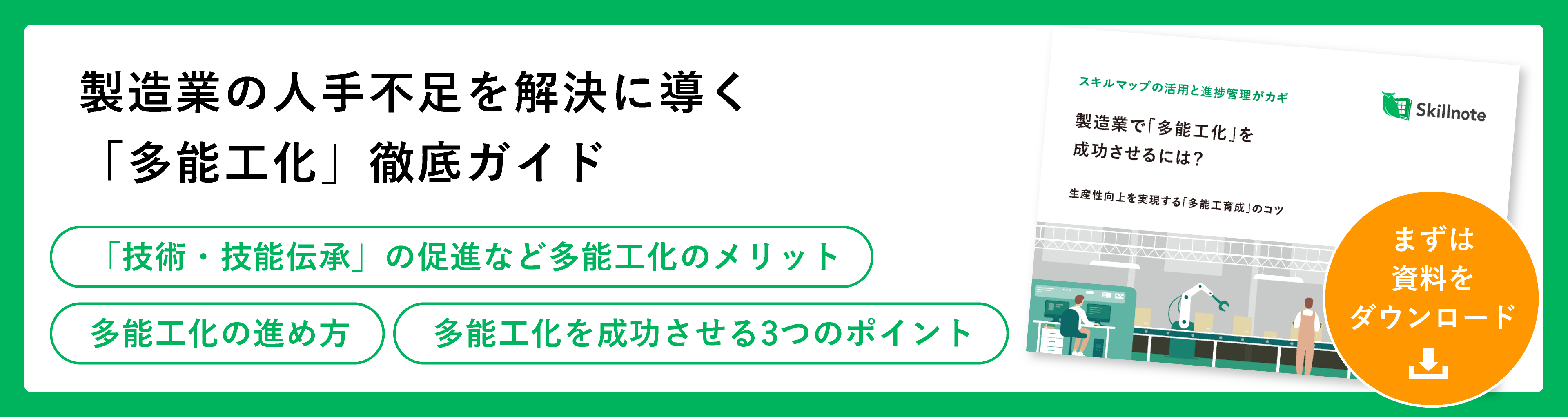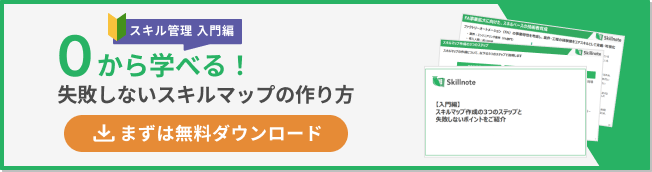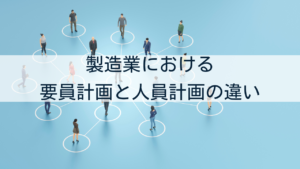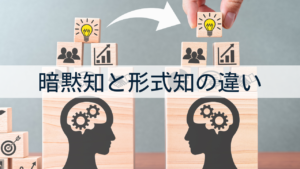タレントマネジメントシステムとは? 導入のメリットや失敗しない選び方について解説

人材獲得が難しさを増す今日において、人材の育成や適切な配置を加速させるタレントマネジメントは重要性を増しています。そのためタレントマネジメントを効果的に行えるようにするタレントマネジメントシステムが注目を集めています。
この記事では、タレントマネジメントシステムの概要と機能、選び方、導入時の注意点などを解説します。
タレントマネジメントシステムとは
タレントマネジメントシステムとは、従業員が保有している能力やスキル、これまでの業務経験などの人材情報を一元管理(見える化)して、蓄積された人材データを評価や配置、育成に活かすシステムのことです。
タレントマネジメントシステムを導入してタレントマネジメントを推し進めることで、経営目標の実現に人材データを有効活用する企業が増えています。
タレントマネジメントとは
タレントマネジメントとは、経営目標の実現に向けて従業員一人ひとりの力を活用することです。従業員が持っている能力やスキル、経験をデータ化してそれを有効活用することで企業の成長に繋げます。
タレントマネジメントによる教育・育成の対象には、幹部候補やマネージャー、企業が重点領域として定めた業務に関わる人材を選ぶことが多いと言えます。候補人材の選出を終えたら、候補人材一人ひとりに適した教育・研修計画を立案し、適宜フォローを行いながら計画を実行していきます。
また、全従業員を対象に教育・育成を行うことも可能です。タレントマネジメントシステムを用いて業務経験や保有スキルに関する人材データを一括管理することで、育成計画の立案や異動・配置、不足人材の採用などへの活用が可能となります。

タレントマネジメントシステムの歴史
タレントマネジメントシステムは、1990年代にアメリカで登場しました。日本では、2010年代に一部の大企業が人事戦略を推進するために導入して、徐々に広がりました。
その後、少子高齢化による人手不足の深刻化や市場環境が大きく変化したことを背景に、従来通りの教育・研修方法ではなく人材データを有効活用して科学的に人事戦略を実行するタレントマネジメントへの注目度は増していきました。
タレントマネジメントシステムを提供する企業は増えており、各社独自の機能やユーザーインタフェースを組み込んだシステムを提供しています。
労務管理システムとの違い
タレントマネジメントシステムと混同されがちな人事関連のシステムに、労務管理システムがあります。一見するとタレントマネジメントシステムと似ていますが、両社は全く別のシステムであり、管理する情報や活用方法に違いがあります。
労務管理システムでは、勤怠や給与計算、社会保険・雇用保険、福利厚生等、労務に関わる情報を管理します。つまり、人事に関わる必要不可欠な労務情報を扱うシステムです。
一方でタレントマネジメントシステムでは、従業員の保有するスキルや資格、職歴、業務経験等を管理します。これらの情報は、従業員の育成、配置、採用に活用され、最終的には経営目標の実現に貢献します。
このように、タレントマネジメントシステムと労務管理システムは、その目的や管理する情報に大きな違いがあります。
タレントマネジメントシステム導入の目的
深刻化する人材不足やグローバル化する市場競争の激化、人材の多様化や働く環境の変化、さらには輸入資材の高騰など、今、日本企業はさまざまな課題を抱えています。
これらの課題を解消するためには、従業員の能力を正確に把握して人材配置や育成計画を最適化していく必要があります。
しかし、今までは人材データを把握するには莫大な工数がかかっていました。また、それを関係者に共有する仕組みの構築も難しかったというのが実情です。
そこで現在、多くの企業でタレントマネジメントシステムの導入が進んでいます。タレントマネジメントシステムでは、人材データを一元管理し、関係者と簡単に共有できます。人材データを有効活用することで適切な能力開発、適切な配置、適切な育成計画を実現することが可能となります。

タレントマネジメントシステムでできること
タレントマネジメントシステムでは、製品ごとに対応している機能が異なります。ここでは主要な機能を紹介しますが、導入を検討している場合、検討中のシステムで自社が必要とすることができるかどうかは、必ず確認しておきましょう。
人材データベース
タレントマネジメントシステムの中心となる機能が、人材データベース機能です。人材データベース機能には、それぞれの従業員が保有するスキルや能力、資格に加えて、これまでの業務経験や職歴などが登録できます。
人材情報の一元管理によって人材データを効率的に共有・活用することが可能になり、戦略的な配置や育成に活用できます。
人材育成の計画・管理
人材データベース機能と並ぶ重要な機能が、人材育成の計画や管理を効率的に行う機能です。
社内で用意している教育カリキュラムをスムーズに運用できることに加え、個人の育成計画の設定と共有、研修・教育の進捗管理も行えます。
研修の受講状況を可視化することで育成計画のPDCAサイクルを楽に運用。教育内容の改廃や受講タイミングの調整などの意思決定にも活用できます。
また、教育の受講結果を共有することができれば、従業員が保有する最新のスキル把握もスムーズに。業務の割り振りも効果的にできるようになるでしょう。
後継者育成・管理
タレントマネジメントシステムを使えば、後継者の育成も効果的に行えます。そのため、多くの時間を要する経営層や職場のリーダー等の後継者育成にタレントマネジメントシステムの活用は、大きなメリットをもたらします。
後継者が必要なポジションや業務を明確化できたら、タレントマネジメントシステムでそのポジションに必要な適正と素養を持った候補人材をリストアップ。候補人材に対する育成計画の管理にも活用可能です。
タレントマネジメントシステム上に候補人材をプールしておくことで、候補人材に休職や退職などの突発的な事象が生じた場合でも、速やかに対策可能です。

従業員個々の目標管理
タレントマネジメントシステムを活用することで、従業員の目標、目標に対して本人や周囲が行ったアクションのモニタリング、上司から部下へのアドバイスやフィードバックを可視化して管理できます。
目標管理を効果的かつスムーズに行うことで、従業員のモチベーションを高め、目標を達成するための可能性を高められるでしょう。
人材配置や要員管理のサポート
人材データベース機能を使って人材配置や採用計画の立案(要員管理)をサポートすることもできます。
人材データベースを参照することで、異動の提案や欠員が生じたポジションに対してスキル・業務経験に基づいた候補人材の選出などが可能となります。最終的な判断は「人」が行う必要がありますが、客観的な人材情報に基づいた提案は重要な参考情報になるでしょう。

採用活動のサポート
採用計画を立案して採用活動を進める際にも、タレントマネジメントシステムは活用できます。
採用候補者をある程度絞り込んでからデータベースに入力すれば、社内の従業員情報と照らし合わせて自社に合う人材かどうか・自社に必要な人材かどうかを確認することができます。また、新たな人材を獲得する際の費用対効果の分析にも活用できます。
報酬の管理
多くの企業において従業員の報酬は、勤続年数や保有資格など目に見える情報に基づいて決定されています。賞与は業務への取り組み姿勢や成果に基づいて判定されますが、判断基準が不明確で説明性に欠ける場合もあるでしょう。
人材データベースには仕事の成果を記録できるため、正確な評価情報や人材データを参考にして賞与を計算することが可能です。また、人材データベース上の情報から、基本給に関しても自動的に算出できます。
社内アンケート
タレントマネジメントシステムの中には、社内向けのアンケート機能が付帯している場合もあります。この機能を活用すれば、従業員の満足度調査、全社で取り組んでいる施策に対する従業員の受け止め方などを効率的に調査できます。
タレントマネジメントシステムの選び方
さまざまな企業が提供しているタレントマネジメントシステムの中から、自社に最適なものを選択するのは簡単ではありません。以下のような観点から絞り込むといいでしょう。
既存の人事システムと連携しやすいか
多くの企業では、労務管理システムなどの人事システムを導入されているでしょう。せっかくであれば、既存のシステムに蓄積されたデータもうまく活用するべきです。
そのため、既存の人事システムと連携しやすいかどうかはタレントマネジメントシステムを選定する上で重要なポイントの一つです。うまく連携できない場合には新たにデータを収集・入力する手間が生じるため、余計な時間と費用がかかってしまいます。
導入目的・課題に適合しているか
タレントマネジメントシステムを導入する際には、解決したい課題や達成したい目標があるはずです。そのため、課題解決や目標達成を実現するために必要な機能が搭載されているかどうかは必ず確認しましょう。
多機能であればあるほど望ましいという考え方もありますが、機能が充実しているシステムは往々にして導入費用・管理費用が嵩んでしまいます。
必要とする機能の使いやすさを確認し、不必要な機能は採用しないなどの観点から選定するといいでしょう。
収集したデータを活用しやすいか
タレントマネジメントシステムで収集・蓄積したデータは、用途に合わせて分析する必要があります。
そのため、集積したデータの管理のしやすさ、出力形式の豊富さ、分析のしやすさ、共有のしやすさなどは、システムを選定するうえで重要なポイントの一つです。
また、データを蓄積していく際には、システムがさまざまな形式の電子データを読み込むことができるかどうかも、効率よく使いこなすうえでは確認しておく必要があります。
セキュリティは万全か
人事情報には、多くの個人情報が含まれています。用途外の使用や流出は厳禁であり、セキュリティには万全を期する必要があります。
タレントマネジメントシステムはネットワークに接続して使用します。そのため、システムに何らかの攻撃を受けた場合には、ネットワークを通じて個人情報の流出等の影響が大きく広がる危険性があります。
タレントマネジメントシステムの導入する際には、導入を検討しているシステムのセキュリティが万全であるかを必ず確認するようにしましょう。
製造業でタレントマネジメントシステムが必要とされる理由
タレントマネジメントシステムは、現在、様々な業界で導入・活用が進んでいます。そしてそれは製造業でも例外ではありません。なぜ製造業でタレントマネジメントシステムが必要とされるのでしょうか?
事業に必要なスキルや技術、技能の喪失の危機
日本社会全体の課題として少子高齢化による「人手不足」が挙げられます。もちろん製造業とて例外ではなく、2022年の「ものづくり白書」によると製造業の実に56.3%が課題として「人手不足」を挙げています。なお、熟練工の高齢化による退職も進んでおり、これにより事業を運営するためのスキルや技術、技能が喪失の危機にさらされている企業も多くあります。
企業にとって必要なスキルを維持・管理するためにも、製造業特有の複雑なスキル体系に適応したスキル情報を基盤とするタレントマネジメントシステム(スキル管理システム)の導入・活用が求められています。

消費者ニーズの多様化に対応するために多能工が必要
経済のグローバル化やIT技術の発展により、諸費者のニーズは明らかに多様化しました。商品を製造して販売する製造業にとってこの潮流の変化は非常に大きく、これまでの単一プロダクトの大量生産では多様化するニーズに応えられないようになりました。そこで現在、製造業が迫られているのは従業員の積極的な多能工化です。高スキルを汎用化して様々なスキルを複数保有して業務にたずっさ割れる従業員を増やすことで、多様化するニーズに対応する「マスカスタマイゼーション」などにも対応できるようになります。
このような理由からも製造業に特有な非常に複雑なスキル体系に対応して抜けもれなく自社に必要なスキルを管理できるタレントマネジメントシステム(スキル管理システム)は求められているのです。

スキル管理とは?
人手不足や消費者ニーズの多様化を背景に、製造業ではスキル管理が注目を集めています。スキル管理とは、「自社に所属する従業員が保有するスキルを可視化し、社内で共有できる情報として集約・活用できるようにすること」です。
スキル管理によって社内で共有されたスキル情報は、新しいプロジェクトへのアサインや人員配置、成績評価、人事関連の業務などに活用できます。つまり、スキル管理とは、製造業に特有なスキル体系に適応したスキル情報をベースにした「タレントマネジメント」と、スキル管理システムとはそのシステムであると解釈ができます。
スキル管理で注意すべき点
スキル管理を実施する際には以下の点に注意しましょう。なお、詳しくは下記の記事をご覧ください。
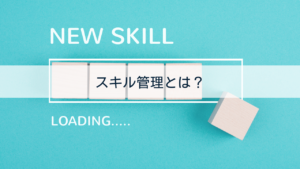
業務で必要とされるスキルの棚卸
管理すべきスキルを抽出するためには、業務に欠かせないスキルを棚卸することが大切です。棚卸したスキルは、新しい事業の開発や既存事業の継続にも直結する内容のため、細かく管理する必要があります。
業務経験やキャリア情報の管理
各従業員がこれまでどのような業務を経験し、どのようなキャリアを歩んできたかは、スキル管理における重要な管理項目のひとつです。
有資格者と資格の取得年月日・有効期限の管理
企業で行う業務の中には、その業務を担当、もしくは監督するために資格や特定の教育を受講している必要がある場合があります。
スキル管理において、資格の取得日や教育の受講日、期限があるものは、それぞれの有効期限と更新のタイミングを通知できるようにしておくと、更新忘れによる失効が起きないでしょう。

研修受講履歴の可視化
社内外で受講する研修の受講履歴を管理することで、受講する研修の重複を防ぎ、レベル別の研修では受講条件を満たしているかどうかを可視化できます。
スキル管理の方法
スキル管理を進めるには「スキルマップ」を活用するのが効果的です。なお、スキルマップをシステム化した「スキル管理システム」を使用すれば作業は効率化できます。
スキルマップとは
スキルマップとは、従業員が保有しているスキルやスキルレベルを可視化するツールのことです。その有用性からスキルマップは様々な企業で活用されています。しかし、企業によって管理するスキルのレベルや項目は多様であるため、自社に会ったスキルマップの運用が重要となります。また、スキルマップを有効活用するには「情報を定期的に更新すること」が非常に重要です。組織ごとに「更新タイミング」を決定して更新するようにしましょう。

スキル管理システムを活用する
スキル管理システムとは、自社の従業員が保有するスキルや資格、研修履歴等の情報を一元管理できるシステムのことです。
紙やエクセルで管理されることの多いスキルマップも、スキル管理システムではシステム化されているため、情報の更新、入力、引継ぎなどが非常にしやすいのが特徴です。スキル管理システムを活用すれば、スキルという定量情報を基盤にタレントマネジメント(計画的な人材育成計画の作成や、戦略的な人材配置)を確実性を高めて実現できます。

タレントマネジメントシステム導入の注意点
タレントマネジメントシステムは有用ですが、導入する際には以下のような点に注意する必要があります。
導入目的を明確にして従業員と共有する
タレントマネジメントシステムに限らず新しいシステムの導入は現場でのオペレーション方法に変化をもたらすものです。タレントマネジメントシステムの場合、評価の記入や基本情報の登録等、現場の従業員に何かしらの作業を依頼することになります。
多くの場合、慣れ親しんだ状態からの変化は嫌われます。そのため、システム導入の目的や導入による成果を従業員と共有することが大切になります。
タレントマネジメントを導入してスムーズな運用へとつなげられるように、変化を被る現場の従業員にはシステムの導入目的や期待される効果をきちんと説明するようにしましょう。
導入成果をあげるには能動的な活用が必要
タレントマネジメントシステムに蓄積したデータやシステムの提案をどう扱うかは、使用者次第です。せっかく費用をかけて導入しても、成果につなげるための能動的な取り組みができなければ意味がありません。
日頃から、どのデータをどう活用すべきかなど人材データの活用方法を考えながら業務に取り組むことが重要です。
無理してすべての機能を活用しようとしない
タレントマネジメントシステムには、さまざまな機能が搭載されています。うまく活用すれば効果が期待できる機能でも、すべての会社がうまく使いこなせるわけではありません。
導入するシステムを選定する際に必要な機能を絞り込んだ上で、導入後に不要だと判明したものがあれば無理に使おうとしないことが大切です。
「多能工化」によって人手不足を解消するには?
「Skillnote」で製造業の多能工化を実現!
●多能工化のメリット
●多能工化の進め方
●多能工化を成功させる3つのポイント